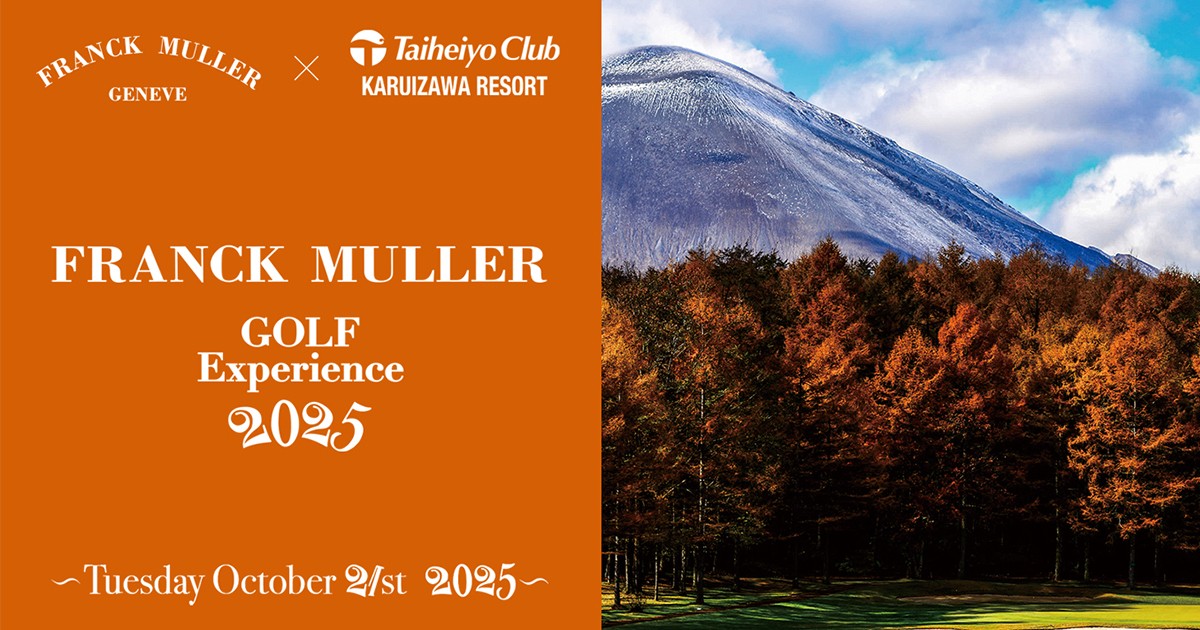人気記事
About&Contact
韓国では、カフェの利用マナーがたびたびニュースでとりあげられる。一部の非常識な客たちの行動が問題視されているのだが、カフェ側はそんな迷惑客の対策に苦慮している。最近の韓国カフェのイシューを紹介する。※画像:Shutterstock.com
洗顔やクレンジングは、毎日のこととはいえなかなか面倒。そんな時は、手軽に汚れをオフできる「ジェル洗顔&クレンジング」がおすすめです。今回は、泡立てやダブル洗顔不要など、時短にもひと役買ってくれる最新アイテムをご紹介します。
Features
マロンとショコラが奏でる、秋の贅沢な出会い
2025.9.12
ジャン=ポール・エヴァン「グルマンディーズ ドトンヌ コレクション」
ジャン=ポール・エヴァン「グルマンディーズ ドトンヌ コレクション」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
ジャン=ポール・エヴァンから、すべての美食家に捧げる「グルマンディーズ ドトンヌ コレクション」が、2025年10月31日までの期間限定で登場。
今シーズンは<新しい世界>をテーマに、メゾンを象徴するショコラと、ジャン=ポール・エヴァンが愛する秋の味覚「マロン」との出会いから生まれた特別なクリエイションが揃う。
トリュフ マロン 9個 4,752円(10月より発売予定) ※ショコラの色味は変更する可能性があります
マロン コンフィ 12個 7,599円
ボンボン ショコラ 16個 オトンヌ 7,884円
注目は、新作「トリュフ マロン」。マロン風味のガナッシュをビターチョコレートでコーティングし、奥行きのある味わいを生み出す。また、イタリア産の大粒の栗をシロップ漬けにした「マロン コンフィ」、期間限定のボンボン ショコラ「マロン カシス」と「ポワール キャラメル」を含む16個の詰め合わせ「ボンボン ショコラ」など、旬を堪能できるラインナップだ。
モンブラン 962円(2026年3月29日までの期間中、金・土・日・祝日のみ限定)
ムニュ モンドレ 2,475円( 9月17日~9月30日の期間限定)
※日本橋三越本店 「バー ア ショコラ」(イートイン)限定
さらに秋の定番「モンブラン」は、2026年3月29日までの金・土・日・祝日限定で発売。また日本橋三越本店では、9月17日から30日までの期間限定で丹波栗を使った「モンドレ」とドリンクのセットメニューが登場。同じく9月30日まで、サブレやショコラ、キャラメルなどを詰め合わせた「ボワットゥ ア グテ」も販売される
(左)ショコラ ショ マロン 1,100円 (右)ショコラ グラッセ モンブラン 1,495円(共に11月30日までの期間限定)
※「バー ア ショコラ」(イートイン)限定
このほか、リッチな香りとやさしい甘さをたたえたマロンをドリンクで味わえる期間限定メニューも。ショコラとの絶妙なハーモニーが、秋のひとときをより豊かに演出してくれる。
マロンとショコラが織りなす多彩な表現。季節を彩るジャン=ポール・エヴァンの特別なコレクションを、ぜひ楽しんでみては。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.9.12
六代目尾上菊五郎をはじめとする大歌舞伎一座の全国巡業記録『戦下の歌舞伎巡業記』
Features
2025.9.12
ザ・リッツ・カールトン東京「グランクラシックアフタヌーンティー〜シェフ エスコフィエ…
Features
2025.9.12
パレスホテル東京で開催。フランス料理「エステール by アラン・デュカス ーChampagne SA…
関連記事
投稿 ジャン=ポール・エヴァン「グルマンディーズ ドトンヌ コレクション」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
江戸指物の真髄に触れる展覧会
2025.9.11
銀座・和光で開催。「江戸指物 木工芸家 島崎敏宏の仕事 蘇れ御蔵島桑」
御蔵島桑拭漆提箱 13.3×32×20.3cm
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
銀座・和光のセイコーハウスホールにて、日本工芸会正会員で木工芸家・島崎敏宏氏による個展「江戸指物 木工芸家 島崎敏宏の仕事 蘇れ御蔵島桑」が、2025年9月26日(金)から10月5日(日)まで開催される。
御蔵島桑拭漆提抽斗箱 15.8×16.6×25.5cm
彩線木画無双箱 13.6×23.3×22cm
江戸指物師の家系に生まれた島崎氏は、父・柾成氏のもとで伝統技法を学び、研鑽を重ねてきた。釘を一切使わずに木材を緻密に組み上げる組手技法によって強度と美しさを兼ね備え、漆仕上げでは一点ごとに異なる木目の個性を引き出すことで、唯一無二の表情を宿す作品を生み出している。
御蔵島桑水輪床脚小箱 12×16.4×7.4cm
会場では、桑材の最高峰とされる御蔵島桑を用いた小抽斗や提箱をはじめ、小机、硯箱、手鏡、ステッキなど多彩な作品を展示。江戸の粋と現代の美意識が響き合う、島崎氏ならではの江戸指物の世界を堪能できる。
神代杉提箱 16.7×37×23.3cm
◆江戸指物 木工芸家 島崎敏宏の仕事 蘇れ御蔵島桑
【会期】2025年9月26日(金)~10月5日(日)
【会場】セイコーハウスホール(東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階)
【営業時間】11:00~19:00(最終日は17:00まで)
【休業日】無休
【入場料】無料
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.9.11
六代目尾上菊五郎をはじめとする大歌舞伎一座の全国巡業記録『戦下の歌舞伎巡業記』
Features
2025.9.11
ザ・リッツ・カールトン東京「グランクラシックアフタヌーンティー〜シェフ エスコフィエ…
Features
2025.9.11
パレスホテル東京で開催。フランス料理「エステール by アラン・デュカス ーChampagne SA…
関連記事
投稿 銀座・和光で開催。「江戸指物 木工芸家 島崎敏宏の仕事 蘇れ御蔵島桑」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Style
Portraits
日本のエグゼクティブ・インタビュー
2025.8.31
スポーツで子どもたちに笑顔を取り戻す 一般財団法人 United Sports Foundation 代表理事 諸橋寛子
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
ゼビオホールディングス株式会社は、福島県郡山市に本社を構え、『スーパースポーツゼビオ』『ヴィクトリア』『ゴルフパートナー』などを展開するスポーツ小売のグループ企業である。その創業者である諸橋廷蔵さんの長女、諸橋寛子さんは、父の後継者として経営を担っていたが、2011年の東日本大震災が彼女の人生を大きく変える。同年9月、『一般財団法人 United Sports Foundation(USF)ユナイテッド・スポーツ・ファンデーション』を設立し、企業経営者から「スポーツを通じた社会貢献」という新たな挑戦へと歩みを進めた。
現在、諸橋さんはゼビオホールディングスのアドバイザリーボード・チェアマンをはじめ、国家機関の委員や国内外の非営利団体の理事・評議員など、約20の肩書を持つ。肩書だけを並べれば「近寄りがたいキャリアウーマン」を思い浮かべるかもしれないが、実際に会うとその印象は一変する。
親しみやすい笑顔と気取らない語り口。その場にいる人を包み込むような温もりがあり、初対面でも自然に心を開かされる。世代や立場を超えて彼女のまわりには人々が集まり、いつしか多くの支援者とともに、財団は来年設立15周年を迎える。
『一般財団法人 United Sports Foundation(USF)』の2024年の事業レポート。
父が一代で築いた事業とともに、父の想いを受け継ぐ
「父の事業を継ぐことを意識し始めたのは、5歳くらいだったと思います」と諸橋さんは振り返る。「弟は心優しいのんびり屋でしたから、父も私のほうが事業には向いていると感じていたようです」。
ゼビオの前身は福島県いわき市の紳士服店。そこからファッション、さらにスポーツウエアへと拡大し、父・廷蔵さんが一代でスポーツ小売業のリーディングカンパニーへと成長させた。諸橋さん自身は事業継承を念頭に、大学はボストンで学び、その後は三井物産繊維部で輸出入業や三国間貿易などの仕事を経験し、やがてゼビオに入社。夫となり、現在ゼビオホールディングスの社長を務める友良さんも商社を経験し、ゼビオに入社して、父の教えの下、共に経営に携わっていく。
ところが2003年に廷蔵さんが事故で急逝するという不幸に見舞われ、突然二人はすべての事業を引き継ぐこととなる。「幼い頃から父に教わり、店舗を見て学んできましたので、経営の基礎は自然に身についていました」と語るが、若干30代の二人には一大企業の経営を背負うにはまだ若く、経験も充分とは言えない状況であった。
一方で、寛子さんの弟・英二さんは父が設立した福島県北塩原村にある「諸橋近代美術館」の館長を務めている。「諸橋近代美術館」は、サルバドール・ダリの絵画・彫刻・版画など、約340点の作品を所蔵する、世界屈指のダリの美術館として知られている。ダリの作品の素晴らしさ言わずもがなではあるが、磐梯山を望む素晴らしい庭園と、ヨーロッパに訪れたかのような美しい建造物も一見の価値がある。この建築物は父・廷蔵さんが馬小屋をイメージして設計されたと聞く。
朝日磐梯国立公園に位置し、美しい自然に囲まれた諸橋近代美術館。
諸橋廷蔵さんが自ら蒐集したサルバドール・ダリの作品の数々が並ぶ。
「父は経営者であると同時に芸術を愛する人でした。私たち兄弟も子供時代から芸術に触れて育ち、私は長くバイオリンを習っており、コンクールでは賞をいただくほど熱中していました。今では驚かれますが、子どもの頃はスポーツが苦手だったんです」と微笑む。
福島に本社を持つゼビオの復興へ向けた取り組み
2011年3月の東日本大震災。当時、諸橋さんは東京へ出張中で、中学生の娘は一人自宅にいた。「帰宅すると、家は全壊状態。駐車場に佇む娘の姿を見つけ、無事を確認できたことがただ嬉しく、安堵をしたことを覚えています」。
ゼビオの店舗も被災したが、無事だった店舗を避難所として開放。社員たちは炊き出しを行うなどして、地域を支えた。「住民の生活をどう守るか、一日も早く日常を取り戻すことが最優先でした」。
被災した店舗からボールなどのスポーツ用品を取り出し、子どもたちに手渡すと、子どもたちは屈託のない笑顔で遊んでいた。「ボールひとつで子どもたちが笑顔になる姿を見て、スポーツの力を実感しました。それまではスポーツが苦手で、関わりも薄かったんです。でも、スポーツには人の心を豊かにし、健康をもたらす力があると感じた瞬間でもありました」。
USFの最初の取り組みとなった無料施設『KIDS PARK』(現在は閉館)。
復興には長い時間をかけて真剣に向き合っていく必要があると、諸橋夫妻は考えはじめていた。企業のCSR活動だけでは限界がある。「株主には利益を出す責任がある。だからこそ、主人は経営に専念し、私は財団を設立して社会貢献に集中することを決めました」。これがUSFのはじまりだった。
オフィスに顔を出すのは週1回程度。毎日スポーツウエアで全国で行われている企画に顔出したり、政府との会合に参加するなど、国内外を飛び回っている。
子どもたちの未来のために、私たちが今できることとは
震災直後、放射能への不安から子どもたちは外で遊べず、心身の成長に悪影響が懸念されたため、無料施設「KIDS PARK」を開設。体を動かせる場を提供したことがUSFとしての最初の取り組みだった。
その後はトップアスリートによるスポーツ教室や宿泊型マルチスポーツキャンプを企画していく。「初めて会う子どもたちが共同生活を送り、さまざまな競技に挑戦する。そこで自分を再発見するんです。子どもの表情が変わる瞬間に立ち会うと、私たちの活動は間違っていないと心から思えました」。
2013年から2024年までのUSFの取り組みに参加した人数は約60万人、イベント回数は約3,000回、共催・賛同企業や団体は80以上。
スポーツは苦手と話していた諸橋さん自身もスポーツに取り組むようになった。震災後の入院や手術をきっかけに、健康の大切さに気づいたのだ。
「スポーツシューズやウエアすら持っていなかった私が、パーソナルトレーナーをお願いして、週3回の筋トレ、さらに毎朝10キロ走り、今はスパルタンレースにも挑戦しているんです。いつしかスポーツが生活の一部になっていて、やらないと逆にエネルギーが湧かないんです」。
同時に歌舞伎や芝居、美術館鑑賞など、芸術に触れる時間もしっかりと設けることで、偏りが生まれないような時間の使い方をしているとも語ってくれた。
財団の活動で見えてきた、日本の部活動文化と社会課題
諸橋さん財団を運営する中で、日本のスポーツ教育に横たわる課題があることに気付いたと語る。
「日本は野球なら野球だけ、サッカーならサッカーだけ、1つのスポーツを徹底的に行うことがヨシとされています。この根底には日本の部活文化が関係していると思います。しかし1つのことしかやらない、そうした偏りは子どもの可能性を狭め、燃え尽き症候群にもつながります。さらには岐路に立ったときに切り替えができにくい思考にもなると思います。これはアスリートのセカンドキャリアの課題にもつながっていると思います」。
現在、子どもたちとスポーツの課題の1つとして、スポーツ庁では、『部活動の地域展開』『地域で子どもを育てる』などの理念を掲げて取り組みを進めている。
教員がボランティアで部活動の指導を担うのではなく、地域が主体となって部活動を行うというもの。この実現によって、教員の長時間労働問題や教員の専門外の指導の問題を解決し、学校を超えた地域校との交流や専門的な指導を受ける機会の創出につながる。
ただし、部活動の費用負担や保護者による送迎の増加、指導者の確保などの課題もあるが、諸橋さんはスポーツ庁の取り組みの支援や相談役にもなっている。
アスリートによる指導を受けるイベントも多数行っている。
スポーツを通じて、子どもたち、日本の未来へ挑戦を続ける
震災を契機に設立された財団は、その歩みを「復興支援」から「スポーツ振興」へと広げてきた。国内外のアスリートとの交流や、企業・自治体との連携を重ねながら、スポーツの持つ社会的な可能性を着実に拓いてきたのである。
「私はトップアスリートを育てたいわけではありません。スポーツを通して、子どもたちに『生きる力』を届けたいのです」。
スポーツ業界は男社会が長く続いてきた。このガラスの天井を破る取り組みも諸橋さんの課題の1つであったと語る。
「日本のスポーツ業界では古くから“根性”“忍耐”が美徳とされている傾向があったが、これらの思考も時代とともに変化していく必要がある」と諸橋さんは語る。
「スポーツは楽しむもの。やる人も見る人も、心と体を豊かにするエンターテイメント。スポーツ体験は子供たちの心身の成長に大きな意義を持つと考えています。そのためには親御さんを含めた大人たちの常識を覆すことも大切です」。
日本社会の課題にもつながっているのが、教育格差、地域格差、居場所を失っている子どもたちの存在だ。スポーツはそれらを解決する万能薬ではないが、子どもの心を開き、つながりを生むきっかけになる。
諸橋さんはまだゴールは見えていないと語るが、この取り組みは日本社会へ、そして大人たちへ、多くの課題を投げかけていると感じる。今後の諸橋さんの取り組みに注目していきたい。
USFの諸橋さんのデスクにて。
諸橋 寛子 Hiroko Morohashi
福島県いわき市生まれ。大学卒業後総合商社勤務を経て、創業者である父が経営する現在のゼビオホールディングスに携わる。2011年3月東日本大震災後、復興支援活動を契機に「スポーツの持つ力」を理念に掲げ、同年9月「一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION」を設立し、代表理事に就任。 「スポーツの力で子どもを笑顔に」をテーマにマルチスポーツイベントを推進し、約60万人の子どもたちにスポーツに触れる機会を提供。2020年から、文部科学省や経済産業省、東京都などの部活動の地域展開に係る委員会やスポーツ推進などに参画し、スポーツを通じて持続可能で健全な社会を形成するための活動を行っている。
島村美緒 Mio Shimamura
Premium Japan代表・発行人兼編集長。外資系広告代理店を経て、米ウォルト・ディズニーやハリー・ウィンストン、 ティファニー&Co.などのトップブランドにてマーケティング/PR の責任者を歴任。2013年株式会社ルッソを設立。様々なトップブランドのPRを手がける。実家が茶道や着付けなど、日本文化を教える環境にあったことから、 2017年にプレミアムジャパンの事業権を獲得し、2018年株式会社プレミアムジャパンを設立。
Photography by Toshiyuki Furuya
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 スポーツで子どもたちに笑顔を取り戻す 一般財団法人 United Sports Foundation 代表理事 諸橋寛子 は Premium Japan に最初に表示されました。
眠らない街・台北で“夜活”しよう! 夜市グルメ、話題のレストラン、台湾らしさあふれる料理で一杯飲める店や深夜便にありがたい深夜営業店まで、今行くべき台北ナイトスポットを厳選紹介。短期滞在でも使える、夜の台北攻略ガイドです。
9月になっても、依然として気温の高い日が続いており、駐車中の車内の暑さには注意が必要です。日差しを遮るのにもっとも手軽なのは「サンシェード」ですが、気を付けたい点もあります。車の専門家である筆者が解説します。※画像:PIXTA

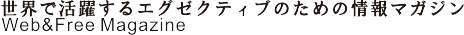







.jpg)