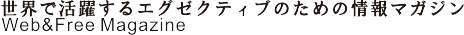人気記事
About&Contact
昨今、若年層を中心に成分に注目して化粧品を購入する人が増えています。肌悩みが増えたり深刻化したりする“40代”こそ、この流れに乗りたいところ。今回は、ドラッグストアで買える「ビタミン系化粧品」の中から、40代におすすめの製品を紹介します。
Features
北欧の名作家具に出会う宿
2025.10.16
カール・ハンセン&サンの名作家具と古民家宿が響き合う「Hygge Stay by Carl Hansen & Søn」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
デンマーク王室御用達の家具メーカー、カール・ハンセン&サンが、瀬戸内の伝統的な日本家屋で北欧のヒュッゲを体感できる、宿泊体験型インスタレーション「Hygge Stay by Carl Hansen & Søn」を開催中。2026年2月15日(日)までの期間限定で宿泊が可能だ。
会場は、香川県丸亀市・本島に佇む一棟貸しの古民家宿「Villa Tomari」。かつて郵便局長が暮らしていた旧松野邸をリノベーションした宿は、当時としては珍しくモダンな造りで、北欧家具との相性も抜群。
伝統的な日本家屋が蓄えてきた「経年の美しさ」が光る空間に、ハンス J. ウェグナーの「CH23」や「CH88P」、ボーエ・モーエンセンの「BM0121 ダイニングテーブル」などの名作家具が自然に溶け込んでいる。
さらに屋外スペースには、カール・ハンセン&サンのアウトドア家具を配したサウナエリアも。風と光、そして静寂に包まれながら“ととのう”ひとときを堪能できる。
館内にはカール・ハンセン&サンの貴重なオリジナルのアーカイブ写真や、デンマークの海の風景、本島の地図などをアートピースとして展示。時の流れとともに深みを増す空間で、時代を超えて受け継がれる名作家具の魅力を体感してみてはいかがだろうか。
◆「Hygge Stay by Carl Hansen & Søn」
【期間】開催中~2026年2月15日(日)(瀬戸内国際芸術祭 秋会期(10月3日~11月9日)と一部重複)
【場所】Honjima Villa「Villa Tomari」(香川県丸亀市本島町泊494-16)
【形式】宿泊体験型インスタレーション(1日1組/4名まで)
【料金】50,000円(税込)~/1泊(食事別途予約制·有料)
【宿泊定員】4名まで
photo: Shinsuke Inoue
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 カール・ハンセン&サンの名作家具と古民家宿が響き合う「Hygge Stay by Carl Hansen & Søn」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Experiences
Spotlight
モータージャーナリスト清水和夫の車探訪
2025.10.15
清水和夫が唸る 新型「フェラーリ849・テスタロッサ(Testarossa)」の特別感
849 Testarossaとともに登場したフェラーリジャパン代表取締役社長ドナート・ロマニエッロ氏(左)と、本国からヘッド オブ プロダクト マーケティング マネージャーマルコ・スペソット氏が登場。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
まだ残暑厳しい9月の終わりごろ、都心の真ん中でフェラーリが誇る最速のスーパーカーが発表された。その会場は高輪ゲートウェイ隣接のコンベンションセンターだが、そこは足を踏み入れることすら躊躇してしまうほど、イベントスペース全体が赤で染まっていた。
赤といえばフェラーリのアイコンだが、今回の新型は「フェラーリ849・テスタロッサ(Testarossa)」と命名された。テスタロッサとはイタリア語で「赤い頭」を意味し、その名の通りエンジンのカムカバーが赤く塗装されている。テスタロッサの名前は1950年代の名車「250 Testa Rossa」の伝統を受け継いでいるが、当時のフェラーリはフロントにエンジンを搭載するFR(フロントエンジン・リヤ駆動)方式を採用していたため、赤く塗られたエンジンはフロントに収められていた。兎にも角にもテスタロッサは、歴史的にレースのDNAを持つフェラーリのフラッグシップモデルだったのだ。
フェラーリの由来とは
フェラーリという名前を知らない人はいないと思うが、その由来は創業者エンツォ・フェラーリの名前にある。1950年代、レーシングドライバーだったエンツォ・フェラーリはその後、レーシングチームを設立し、イタリア北部マラネロにレーシングカーと高性能スポーツカーを製造するメーカーを立ち上げた。
創業時からの哲学は「レーシングカーと高級スポーツカーのみを少量生産する」という方針を守り続け、それがブランドの根幹となった。しかし、フェラーリはただ速さを追求するだけでなく、スタイリングの美しさ、オーケストラに喩えられるエンジンサウンドなど、そのすべてが芸術的と評価されてきた。この「機能美」と「芸術性」の融合こそが、クルマ文化の象徴としての地位を築いたのである。
なお、「テスタロッサ」の名を冠した市販モデルがデビューしたのは1984年。その発表会はパリ・シャンゼリゼ通りの「キャバレー・リド」で行われた。筆者はその記事を自動車雑誌で知ったときから、「テスタロッサ」は特別なフェラーリなのだと感じていた。
プロドライバーも憧れるスポーツカー
私もプロのレーシングドライバーとしてのキャリアがあるものの、フェラーリのステアリングを握ってレースバトルを繰り広げることは夢のまた夢。叶わない夢であっても、そのコクピットに収まる自分の姿をイメージしながら、今回の発表会に出席した。
2025年9月24日、プラグイン・ハイブリッド・ベルリネッタ849Testarossaが日本で初披露された。849 Testarossa Spiderもラインアップされ、14秒で開閉可能なリトラクタブル・ハードトップによるオープンエアも楽しめるという。
ここで簡単にフェラーリ849テスタロッサのプロフィールを紹介しておこう。基盤技術は3モーターのプラグイン・ハイブリッド。プラットフォームは「SF90ストラダーレ」の後継となるが、あえて「テスタロッサ」と命名したのは、現行フェラーリの中で最速を誇るからだろう。中身はSF90ストラダーレをベースにしているが、スタイリングは大きく異なり、新しいフェラーリのデザイントレンドを示している。
フェラーリはまた、SF90ストラダーレをベースによりサーキット志向を高めた「SF90XXストラダーレ」もリリースしている。筆者は幸運にも、この究極モデルをマラネロのサーキットでドライブする機会を得たが、まるで公道を走るレーシングカーのような速さに驚かされた。
ただし「SF90XXストラダーレ」は限定799台。ステアリングを握れるオーナーは限られている。最高出力1000ps超をプラグイン・ハイブリッドとV8エンジンで叩き出すその走りは、まさにF1マシンをロードカーに移植したかのようだった。
このモデルは0-100km/h加速を2.3秒以下で達成すると発表されているが、新型テスタロッサも細部の改良により「SF90XXストラダーレ」に迫るパフォーマンスを実現している可能性が高い。
発表会に参席していたマルコ・スペッソット氏は、テスタロッサの速さは「SF90ストラダーレ」を上まわるとコメント。言葉を選びながらも、孤高の存在である「SF90XXストラダーレ」と肩を並べる性能を秘めていることを示唆していた。ボディスタイルは2ドアクーペのベルリネッタと、格納式ハードトップを備えたスパイダー(オープンカー)が発表されている。
水平なダッシュボードを持ち、ステアリングホイールには各種スイッチ類が配置され機能性を重視。まるで浮遊したかのようなシフトゲートが印象的だ。カーボンファイバー製シートと、コンフォートシートの2種類が設定される。
“849”という新たな称号が与えられた
ボディサイズ=全長4718mm×全幅2304mm(ミラー込み)×全高1225mm、ホイールベース=2650mm。車両重量は1570kg。タイヤサイズはフロントが265/35R20、リヤが325/30R20。
「849」の意味は、V型8気筒エンジンの1気筒あたりの排気量が490ccであることを示している。
この4.0L V8エンジンはターボを備え、リヤミッドに搭載。もちろんエンジンカバーは赤く塗られている。新開発の4.0L V8ターボは従来比+50psの830psを発揮。
さらにプラグイン・ハイブリッドシステムはフロントに2基、リヤに1基のモーターを搭載し、モーターのみで220PSを発揮。システム総合出力は驚異の1050psに到達する。0-100km/h加速はSF90より0.2秒短縮されており、「SF90XXストラダーレ」を凌駕している可能性すらある。バッテリー容量は7.45kWhで、EVモード航続距離は25kmを確保。フェラーリ・ジャパンは国内価格を6465万円と発表した。
タイヤサイズはフロント245/35R20、リア325/30R20で、ピレリ、ミシュラン、ブリヂストンの3社が選べる。ブレーキはバイワイヤシステムが採用され、独自のABS技術を投入する。
テスタロッサは「SF90XXストラダーレ」の化身か?
パフォーマンス的に「SF90XXストラダーレ」と肩を並べるとすれば、849テスタロッサの走りを想像するのは容易だ。ここで筆者が2年前に試乗した「SF90XXストラダーレ」の記憶を呼び起こしたい。
2023年11月、イタリア北部マラネロのサーキットはあいにく濡れた路面だった。冷えたタイヤとマシンへの不慣れさもあり、最初は慎重に走るしかなかった。だが、1030psのモンスターを前にして、スロットルを全開に踏み込む衝動を抑えきれなかった。
瞬間、背後からV8ターボの800psが目を覚まし、モーターのトルクが加わることで強烈な加速Gが身体を押し付ける。まるでロケットにまたがったかのような感覚だった。路面温度が上がり、タイヤの接地感がステアリングを通じて明確に伝わってきたとき、「攻めの走り」に移行できる準備が整った。
1030psを使いこなすにはブレーキングが決定的に重要だ。カーボンコンポジット製ブレンボブレーキと進化型ABS「ABS-evo」の組み合わせは、半乾きの路面でも安定性を失わない。左右で路面状況が異なる場面でも、ダウンフォースと電子制御により不安定な挙動は見られなかった。
さらに高速コーナーでは、大型リヤウイングが250km/hで530kgものダウンフォースを発生させ、F1直系の空力技術が安定性をもたらす。200km/hのコーナーではステアリングがずっしりと重くなり、強い接地感が伝わる一方、低速コーナーではダウンフォースが薄れ、ステアリングは軽快になる。
エアロダイナミクスは、冷却性能の最適化とダウンフォースの増強を狙い、512Sや512M、FXX-Kなど、往年のレースカーを思い起こさせる。ダウンフォースは250km/hで415kgに達し、SF90Stradaleをも凌ぐ。
新世代フェラーリはハイブリッドを駆使するサラブレッド
849テスタロッサは一見、手に余る荒馬のように思えるかもしれない。しかし実際には、最新テクノロジーによって調律され、史上最速かつ最も洗練されたサラブレッドへと進化しているはずだ。
フェラーリが追求するスポーツカーは、単なる速さだけを誇るマシンではない。ドライバーに感動と情熱を呼び覚ます「パッションクリエイター」である。
「山男には惚れるな」という格言があるが、フェラーリ好きの男性にも惚れてはいけない。どんな美女がパッセンジャーシートに座っていようと、その存在を忘れてしまうほど特別な世界がフェラーリにはあるのだ。
清水 和夫 Kazuo Shimizu
国際自動車ジャーナリスト 神奈川工科大学自動車工学部客員教授
1972年のラリーデビューし、1980年代からプロのレースドライバーに転向し、国内外の耐久レースに参加する一方、国際自動車ジャーナリストとして活動。現在はラリーから始まりレースにプロとして参戦し、再び全日本ラリーに復帰。自動車の運動理論・安全技術・環境技術などを中心に多方面のメディアで執筆活動を行うほか、TV番組のコメンテーターやシンポジウムのモデレーターとして多数の出演経験を持つ。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 清水和夫が唸る 新型「フェラーリ849・テスタロッサ(Testarossa)」の特別感 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
ニコライ・バーグマン×PEANUTSがコラボレーション
2025.10.15
25年と75年。ふたつのアニバーサリーが重なり合う限定品
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
フラワーアーティスト、ニコライ・バーグマンが手がけるオリジナルフラワーボックスの誕生25周年を記念して、誕生75周年を迎える『PEANUTS(ピーナッツ)』とコラボレーション。特別なフラワーボックス「Nicolai Bergmann meets PEANUTS.」 が数量限定で発売中だ。
(左から)フレッシュフラワーボックス Imaginary White S(11×11×H9cm) 7,700円、プリザーブドフラワーボックス Imaginary White S(11×11×H9cm) 19,800円(共に数量限定品)
今回のコラボレーションでは、『PEANUTS』の物語の奥深さを2種類のデザインで表現。楽しそうに舞い踊るスヌーピーを、きらめく箔押しで描いた“Imaginary White(イマジナリー ホワイト)は、華やかで心弾むデザイン。⾒る⼈の⼼を解き放ち、無限の想像⼒を掻き⽴てる。
(左から)フレッシュフラワーボックス Journey Black S(11×11×H9cm) 7,700円、プリザーブドフラワーボックス Journey Black S(11×11×H9cm) 19,800円(共に数量限定品)
もう一方は、スヌーピーとウッドストックのコミックのワンシーンを、マットブラックにあしらった“Journey Black(ジャーニー ブラック)”。ボックスの側面や底面には、75個のスヌーピーの足跡と25個のウッドストックの足跡が散りばめられ、過去から未来へと続く“旅路”を象徴している。
今なお世界中で愛される『PEANUTS』と、フラワーデザインを通して感動を届けてきたニコライ バーグマン。節目の年を迎えた両者による、今だけのフラワーボックス。ぜひお見逃しなく。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 25年と75年。ふたつのアニバーサリーが重なり合う限定品 は Premium Japan に最初に表示されました。
Stories
Japan Premium
星のやに泊まる、星のやを知る
2025.10.10
星のや軽井沢「森林養生」プログラム 森に身をゆだね、心身を解き放つ3泊4日の旅
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
“その瞬間の特等席へ。”をコンセプトとする星のやブランドの始まりの地である「星のや軽井沢」。今年開業20年を迎え、「谷の集落に滞在する」をテーマに、「日本の原風景」を描いた美しい景観と心豊かな時間が過ごせる宿として、多くの人々を魅力し続けています。今回ご紹介する「森林養生」プログラムは、ただ休むための滞在ではありません。森を歩き、湯に浸かり、旬の養生食をいただき、体を調えていく。この体験を繰り返すことで、驚くほどに心身がリセットされていく体験プログラムです。今回は3泊4日のプログラムの一部を体験し、その背景を開発者に伺いました。
自然に抱かれ、ゆっくりと深呼吸するように身体が調っていく「森林養生」プログラム
チェックインを済ませると、3泊4日のスケジュールの説明と共に、現在の身体の状況をお話するコンサルテーションが行われます。
ただのんびりするだけではなく、身体を見つめ直して、身体を調えることに焦点を合わせた旅。
どんな旅になるのか、果たして効果を実感できるのか、そんな想いを抱きながら、プログラムがスタートします。
まずは、「深呼吸入浴法」を学びながら大きく呼吸をして身体の緊張を解していく。
その後は、プログラムの主軸の1つである「森林浴ウォーキング」に向けて、ノルディックウォーキングポールの使い方を敷地内でレッスン。ノルディックウォーキングポールは通常のポールとは使い方が異なり、ポールを身体の前で杖として使うのではなく、身体の後ろでウォーキングをサポートするようにして使います。そのためにウォーキングを後押ししてテンポよく歩けて、姿勢を正して足を出すことで身体が温まっていくようです。
説明によると、ノルディックウォーキングポールを使うと、普段よりも腕を大きく振ることで全身運動となり、運動量が高くなるとのこと。緑豊かな環境で身体を動かすことの心地よさを感じながら、頭を空っぽにして歩みを進めることに爽快感を感じていきます。
到着後の緊張した身体をゆっくりとほぐしながら、「深呼吸入浴法」を学ぶ。
いざ、森林浴ウォーキングへ出発。コースはその日の体調に合わせて基本3つのコースから選ぶことができます。もちろん相談すれば、別のコースを選択することも可能とのこと。
軽井沢の名瀑「竜返しの滝」と「白糸の滝」、二つをめぐる道を選びました。途中まで車を走らせ、そこからは歩いて森の深みに分け入ります。足を踏み出すごとに、土の柔らかな感触が体に響き、小鳥のさえずりや木々のざわめきが心を優しく撫でていく。静寂に抱かれた世界で感覚がひとつずつ研ぎ澄まされ、絡まっていた思考がほどけていく。気づけば、胸の奥まで風が吹き抜けるように、心がすっと軽やかになっていくのです。
ポールを使うことで足取りが軽くなり、歩くことが楽しくなっていきます。
「竜返しの滝」まで来ると、一気に空気が変わり、気温も下がり、自然と深呼吸がしたくなっていく。
鍼灸・ボディケアの施術で、身体と深く向き合う
心地いい疲労感に包まれた後は、楽しみにしていた鍼灸・ボディケアの施術。実は鍼灸ははじめての体験。一度はやってみたいと思っていたものの、信頼できる先生でないと不安ということもあって未だに体験できていませんでしたが、星のや軽井沢が選んだ国家資格を有する、鍼灸・柔道整復師の方であれば安心です。
初日のカウンセリングで体調を細かく確認。3日間にわたり、その日の体調に合わせ、丁寧に施術が行われていきます。約150分の施術後は不思議と身体の痛みが和らぎ、さらに血が巡ってきたのか身体はポカポカです。
さらにいえば、朝起きた瞬間から腰痛に悩んでいましたが、翌朝は久しぶりの清々しさに包まれて、「こんなに自分の体は軽かったのか」と効果を実感しました。
完全個室のスパ棟では、水のせせらぎしか聞こえてこない。
施術は痛みを感じることなく、心地いい。
食べることも「森林養生」の大切な要素
「森林養生」のさらなる柱となるのは食事です。このプログラムではスポーツ栄養学に基づいた薬膳仕立ての特別食と星のや軽井沢のメインダイニング「日本料理 嘉助」での食事が三食用意されています。つまり滞在中の食事も徹底的に管理。
今回の夕食は「日本料理 嘉助」で『山の懐石』をいただきます。秋の食材である松茸や鮎、信濃雪鱒、薩摩芋などを使った料理はとにかく美しく、そして体に染み入る優しい味わいに仕上がっています。身体が調っていたせいもあるのか、ペロリと完食。
プログラムでは、2日目の夕食は特別食「山の旬菜鍋御膳」です。旬の野菜や薬膳素材が美しく盛られた鍋は、体に優しいだけでなく、食欲を満たす力強さもあるレシピ。
椀盛「中秋月」は、十三夜豆腐とすっぽんの身を入れた白玉は兎に見立てて。
重陽の節句をイメージした、進肴「被綿」。菊花蕪の中に鹿真薯が入り、上には松茸が乗っています。
素晴らしい環境の中での適度な運動、ボディケア、美味しい食事で大満足の1日の終わりは源泉かけ流しの温泉「メディテイションバス」で「深呼吸入浴法」を実践。ただ湯に浸かるのではなく、呼吸を整え、湯の中で軽く体を伸ばす。体が温泉に包まれながら、深い呼吸を繰り返すと、一日の疲れが取れるとともにエネルギーがみなぎっていくようです。温泉の力を“積極的に活かす”入浴法があることを今回はじめて知りました。
心も体も健やかになり、その日の夜はすぐに眠りにつくことができました。
朝食は、地元の山の恵みを薬膳の知恵と掛け合わせた「山の旬菜粥朝食」をいただく。滋味深いお粥を口に運ぶと、体がじんわり温まっていきます。朝からしっかり食べることは、新たな一日の始まりを整え、体を養う行為だと実感します。
特別朝食「山の旬菜粥朝食」。右奥の養生粥は戻貝柱ほぐし身、銀杏や百合根、小豆などが入った香り豊かで優しい味わい。
今回は3泊4日のプログラムの一部の体験ではありましたが、自分の身体の内に耳を傾け、自然の中で体を調えていく経験でした。都会でトレーニングをするのとは異なり、まさに心身が調っていくことを実感できます。貴重な休日をどう過ごすかを考えた際、食事や運動、そして鍼灸が調った環境にただ身を置くだけで、心も体も驚くほど軽くなっていきました。
完全個室になっているスパ棟。
星のや軽井沢からはじまった「養生」という発想と取り組み
この「森林養生」プログラムの開発背景について、星のや軽井沢総支配人の赤羽亮祐さんと、スパ開発を手掛け、さらには今回の「森林浴ウォーキング」のサポートもしてくださった髙橋明日香さんに話を伺いました。
「養生」とは、自分を養い、健やかに生きるための知恵。そう語るのは、星のや軽井沢総支配人の赤羽亮祐さんです。
「日本には古来から、食や呼吸、休息を通じて自分を整える文化がありました。星のや軽井沢ではその知恵を現代に置き換えて、軽井沢の自然や温泉の力を借りて心身を調える体験として「森林養生」プログラムを開業して間もないころから提供しています。
星野リゾート入社後、プログラム開発に従事。2015年に「星のや軽井沢」総支配人、2019年に「星のや東京」総支配人を務め、2021年から再度「星のや軽井沢」総支配人を務めている。
「森林養生」プログラムが始まったのは開業当初から
「当時はマクロビオティック(マクロビ)が注目されており、健康的な食事への関心が高まっていました。そこで「森林養生」でも食事を中心としたプログラムを行っていましたが、当時は今よりずっとストイックで、玄米を百回噛む、ゴマをすり続けるといった厳格な食事法でした」と赤羽さん。
「当時は食事の際に横に座って指導をするほど徹底的な指導でした。その甲斐あって、滞在中に減量ができたり、フェイスラインがすっきりしたなど目に見えた効果を感じていただきましたが、いまは無理なく続けられることを重視しています。大切なのはゲストが自分のペースで“心地よさ”を見つけることですから」とプログラムを企画・開発した髙橋さん。
「森林養生」プログクラムのスタート当時から企画に携わっている髙橋さん。ご自身もマラソン大会に出場するほどのアスリートである。
さらに髙橋さんは「森林浴ウォーキング」で新たに採用したノルディックウォーキングポールについても話してくれました。
「通常のポールは杖のように使用しますが、このノルディックウォーキングポールは腕を大きく振って、ウォーキングのサポートをしてくれる道具になります。ウォーキングの助けになるとともに、全身運動となることで運動量も増加します。このポールを使ったことで、普段より長い距離を歩けたとおっしゃるお客様もいて、帰宅後にポールを購入されて日常に取り入れているようです。ここでも体験が一時的なものではなく、帰ってからの生活に生かされることは嬉しいですね」と話します。
ウォーキング中は腕に心拍計をつけて、運動による心拍の変化をチェックしていきます。
まずはポールの使い方をレクチャーしていただく。ポールを使うと、姿勢を正して、テンポよく進むことがラクになります。
エビデンスに基づき、あらゆる角度から養生を行っていく
もちろん食事を大切にする発想は、スタート当時から変わることなく反映されています。
「薬膳は特別なものに感じられるかもしれませんが、基本は旬の食材を活かすことからはじまります。信州ならではの恵みを取り入れ、運動や施術の効果を高める献立を提供しています。今回より地元で、アスリートの運動や食事指導を行っている公益財団法人『身体教育医学研究所』と『ニッスイ湯の丸アスリート食堂』の力をお借りしたプログラム構成になっているのも特徴です」。
また鍼灸をはじめとする東洋医学のアプローチも、今回から導入したものです。3日間に渡って行われる鍼灸とボディケアの施術は、それぞれの体調を見ながら行われます。連日の施術で、より体の声に耳を澄ませることで、自分に合った回復法を見つけるきっかけとなるはずです。
星のや軽井沢を象徴するランドスケープ「棚田ラウンジ」を背景に。
さらに特徴的なのは、スタッフ全員がプログラムに関わっている点です。外部講師に任せるのではなく、スタッフ自身が知識や技術を学び、ゲストに寄り添っていく。
「だからこそ小さな変化に気づけるのです。ゲストが自分なりの物語を紡ぐ、そのそばに寄り添うのが私たちの役割だと思っています」と赤羽さんは語ります。
いまではその発想は他の「星のや」にも広がっています。星のや竹富島では「島時間養生」、星のや東京では「深呼吸養生」といった形で展開され、土地固有の自然や文化を取り入れながら、ゲストが自分を見つめ直すきっかけを提供しています。
広大な星のや軽井沢。悪天候の日は、星野温泉 トンボの湯へ続く「イチイの丘」で、軽いランニングなどで身体を慣らすのもおすすめです。
取材を終えて思うのは、このプログラムは「癒し」を超えた存在だということです。森を歩き、湯に浸かり、旬をいただき、ただ休む——。そのシンプルな行為の積み重ねが、自分自身を深いところからリセットしてくれます。
赤羽さんが最後に語った言葉が印象的でした。
「ここは“何かをする場所”ではなく、“何もしないことを思い出す場所”なんです」
森に抱かれながら過ごす3泊4日の滞在は、忙しい時間を過ごす私たちが忘れかけていた“調和・調整”を呼び戻す意味深い時間になりました。
◆星のや軽井沢「森林養生」
・実施 通年
・料金 1名270,000円〜(税・サービス料込)*宿泊料別
・含まれるもの コンサルテーション2回、深呼吸入浴法レクチャー1回、森林浴ウォーキング4回、鍼灸・ボディケア3回・浅間山ストレッチ1回・のびのび深呼吸1回、夕食「日本料理 嘉助・山の懐石」2回、特別夕食「山の旬菜鍋御膳」、朝食「日本料理 嘉助・山の朝食」1回、インルームダイニング朝食1回、特別朝食「山の旬菜粥朝食」1回
・定員 1日1組(2名まで)
・予約 公式サイトで10日前までに受付
・対象 星のや軽井沢宿泊者
・備考 身体バランスや要望、天候に合わせてスケジュールは変更になる場合があります。
仕入れ状況やスケジュールにより食事内容が一部変更になる場合があります。
2名でご予約の場合は一部滞在スケジュールを変更させていただきます。
Text by Yuko Taniguchi
Photography by Natsuko Okada(Studio Mug )
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Japan Premium
星のやに泊まる、星のやを知る
Japan Premium
関連記事
Lounge
Premium Salon
編集部&PJフレンズのブログ
2025.10.9
純米大吟醸「IWA 5 アッサンブラージュ6」が完成。販売開始記念のお披露目会に参加した
10月1日販売開始の「IWA 5 アッサンブラージュ6」。
すでに日本のファインダイニング・シーンではしばしば見かけるようになったのがハイグレードな日本酒「IWA5」である。6年目になる「IWA 5 アッサンブラージュ6」が完成し、そのお披露目会が開催された。
ドン ペリニヨンから日本酒へ
「IWA 5」が世界的な注目を浴びた理由は、創立者がリシャール・ジョフロワ氏だということにある。
彼はドン ペリニヨンの5代目醸造最高責任者として、28年間にわたって伝説のメゾンを率いたレジェンドだ。メゾンを去った彼が次に目指したのは、魅せられてやまない日本酒を擁する日本だ。世界基準の新しい日本酒を造るためだった――。
さて、会場は、10月に新規オープンした「ギンザ サファイア ラウンジ」である。このエクスクルーシブなラウンジの目玉は、パリにあるミシュラン1つ星フレンチの「L’ARCHESTE(ラルケスト)」でスーシェフを務めた佐藤健志氏が腕を奮うフレンチフュージョン料理だ。
当日は、彼の料理を、「アッサンブラージュ6」、「アッサンブラージュ5」、「アッサンブラージュ4」、「アッサンブラージュ2」によって年代を遡って試すという、世にも珍しい日本酒による垂直ペアリングを提供するというのだ。
ちなみに、アッサンブラージュとはブレンドを意味するフランス語である。
「甘鯛うろこ焼き 柚子ブールブランソース」にはさらなる熟成を経た酒「アッサンブラージュ5」を合わせた。
アッサンブラージュと熟成が生み出す至高の味わい
最初にサーブされたのは「鯛カルパッチョ」と「アッサンブラージュ6」だ。「タンニンが感じられるが、バランスが良く複雑味に富んでいます」(ジョフロワ氏)。
確かに、「IWA 5」が持つ甘み、苦味、酸味、スパイス、旨味によって、梅とバルサミコ酢で味付けされたカルパッチョは、口中で融合し、さらに奥深く開いて行った。
続いたのは、「甘鯛うろこ焼き 柚子ブールブランソース」と「アッサンブラージュ5」である。すべての「IWA 5」は、完璧な調和と深みを追求するジョフロワ氏の巧みなアッサンブラージュを経て、16カ月以上にわたり瓶内熟成されてから発売される。つまり、1年前に発売された「アッサンブラージュ5」は、すでに2年半の熟成を経ているのだ。「輝きが抑えられ、ダークな感じになっている。しかし、時間が経ったので丸みが出ています。まるでブルゴーニュのようですね」(ジョフロワ氏)。
彼が指摘する通り、確かにまろやかで柔らかい。マイルドでありながら芳醇なアロマは、甘鯛のうろこの薫香やブールブランソースをさらなる高みに引き上げた。
創立者のリシャール・ジョフロワ氏は、ドン ペリニヨンの5代目醸造最高責任者だった。
進化し続ける純米大吟醸
そもそもの「IWA 5」の出発点に話を戻すと、日本を目指したジョフロワ氏が選んだ土地は、霊峰・立山を仰ぎ見る富山県立山である。なぜかと言うと、1893年創業の桝田酒造店の桝田隆一郎氏との出会いがあったからだ。そこには、2人を繋いだのは建築家の隈研吾氏であるというエピソードもついている。
ジョフロワ氏が桝田氏の協力のもと立ち上げたのが酒蔵「白岩」で、アッサンブラージュ(ブレンド)という日本酒にとっては新たな手法を用いて、革新的な日本酒造りのプロジェクトが始動するのである。
ジョフロワ氏によれば、「4、5、6の違いは年度の違いがあるのは当然のこととして、それぞれにブレンドするアイテムが違う」という。つまり、「IWA 5」は進化し続ける純米大吟醸なのである。
「IWA 5 アッサンブラージュ6」は、公式ウェブショップ
および専門店にて10月1日より販売され(720㎖ 15,730円 税込)、また厳選されたレストランやホテルにて提供される。
Profile
石橋俊澄 Toshizumi Ishibashi
「クレア・トラベラー」「クレア」の元編集長。
関連リンク
Premium Japan Members へのご招待
最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。
Lounge
Premium Salon
編集部&PJフレンズのブログ
Premium Salon
関連記事
投稿 純米大吟醸「IWA 5 アッサンブラージュ6」が完成。販売開始記念のお披露目会に参加した は Premium Japan に最初に表示されました。
Experiences
Spotlight
ラグジュアリーホテル・和光のクリスマスケーキ
2025.10.10
編集部が実食して選んだ!2025年おすすめ東京・クリスマスケーキ12
11.Noël de WAKO(和光)
限定10個|縦30cm × 横30cm × 高さ30cm|¥108,000
冬の夜、灯りが揺れるテーブルに華やぐクリスマスケーキ。ラグジュアリーホテルであるパレスホテル東京・オークラ東京・グランド ハイアット 東京・ウェスティンホテル東京・フェアモント東京・ホテル椿山荘東京・アンダーズ 東京・ホテルニューオータニ、そして名門パティスリーの和光が生み出すケーキは、見た目の美しさだけでなく、口に運んだ瞬間に心を満たす香りや食感を持つ芸術作品である。2025年はPremium Japan編集部が試食し、心からおすすめできる逸品を12点厳選した。
1.ノエル ア ラ ネージュ(パレスホテル東京)
限定50個|直径21×高さ9cm|¥15,000
統括ペストリーシェフの窪田修己シェフが、英国の伝統菓子ヴィクトリアケーキをアレンジした新感覚の味わい。テーマカラーである紫色はクリスマスケーキには珍しい色合いだが、それも美しい。マスカルポーネクリームとしっとりスポンジでサンドしたブルーベリージャムで、幻想的なケーキに仕上げた。上品な甘酸っぱさと爽やかな酸味のハーモニーが口いっぱいに広がる。
編集部の感想
「窪田シェフの技術が生み出すデザインと味わいは、ひと口で幸福感を感じられる。」
2.フルール ド ノエル(パレスホテル東京)
縦27×横6.5×高さ6cm|¥15,000
フランス料理「エステール by アラン・デュカス」 ペストリーシェフの中澤紘平(なかざわこうへい)さんが手掛ける、冬に咲く一輪の花を思わせるケーキ。香ばしいアーモンド生地にエルダーフラワークリーム、タルトタタン、キャラメルクリームを重ね、ひと口ごとに異なる味わいが口の中で溶け合う。華やかなデザインとともに、味の層が心を満たす逸品。
編集部の感想
「味とデザインの両方で、エステール by アラン・デュカスの世界観を存分に楽しめる。」
◆パレスホテル東京
予約期間:10月1日(水)~受取日の6日前まで
引き取り期間:12月20日(土)~12月25日(木)
引き取り場所:ペストリーショップ「スイーツ&デリ」(店頭受取のみ)
予約:パレスホテル東京オンラインショップ
※「フルール ド ノエル」は、6階フランス料理 「エステール by アラン・デュカス」でも予約可能。
問い合わせ:03-3211-5320(予約専用ダイヤル)
パレスホテル東京
3.ラヴィアン・ネージュ(オークラ東京)
直径12cm|¥12,000
青森昌之(あおもりまさゆき)シェフパティシエが率いるオークラ東京のチーム・パティシエが手掛けるケーキは、昨年即完売になったため、今年は個数を増やして登場する。北海道・九州産生クリームと奈良県産苺「古都華」を贅沢に使用し、三層スポンジに挟まれたクリームは優しい甘さとコクを持ち、苺の酸味と香りが絶妙に絡む。上質素材を最大限に生かした、王道ながらも特別なクリスマスの一品。
編集部の感想
「青森シェフの素材へのこだわりと技が光る、究極のショートケーキ。」
◆オークラ東京
予約期間:10月1日(水)~受取日の5日前
引き取り期間:12月21日(日)~25日(木)
引き取り場所:プレステージタワー1階 平安の間(21日12:00~19 :00)、7階 チェルシー(22日~25日12:00~19;00)、オーキッド スイーツ&デリ(21日~25日19:00~20:00)
予約:オークラ東京クリスマスケーキ予約サイト
問い合わせ:03-3505-6072(オーキッド スイーツ&デリ)
オークラ東京
4.サンタ ストロベリームース
限定80個|直径12cm|¥10,000
数々の世界大会で優勝・受賞を果たしているペストリーチーム統括、後藤順一シェフ率いるチームが生み出す「サンタ ストロベリームース」は、愛らしい見た目の中に計算し尽くされた味わいのバランスが光る、華やかで洗練されたクリスマスケーキです。香ばしいピスタチオのクリームと甘酸っぱいストロベリージュレを、なめらかなストロベリームースで包み、表面を艶やかな深紅のチョコレートでコーティング。トップにはフレッシュなイチゴ、ラズベリー、ブルーベリーを贅沢にあしらい、サンタクロースの帽子や白いひげ、ベルトを模したチョコレートを添えて、遊び心あふれるデザイン。
編集部のコメント
「ひと口目の軽やかさ、ピスタチオの香ばしさ、そしてベリーの酸味の余韻。どの層も完璧に計算されており、食べ進めるごとに幸福感が広がるような、デザインと味、双方で心がときめく逸品。」
◆グランド ハイアット 東京
予約期間:10月1日(水)~12月22日(月)※受取日の3日前まで
引き取り期間:12月1日(月)~25日(木)
引き取り場所:フィオレンティーナ ペストリーブティック店頭12月1日~19日、特設クリスマスカウンター(フィオレンティーナ ペストリーブティック前)12月20日~ 25日 ※20:00以降はペストリーブティック店頭にて(21:00まで)
問い合わせ:03-4333-8713(フィオレンティーナ ペストリーブティック)
グランド ハイアット 東京
5.バタークリームケーキ“ノエル フルール”(ウェスティンホテル東京)
限定10個|直径21cm ×高さ10 cm|¥16,000
金井智幸(かないともゆき)ペストリーシェフによる懐かしさと新しさを併せ持つバタークリームケーキ。特製フレッシュバターを用いたメレンゲベースの特製クリームと、ドライフルーツをたっぷり練り込んだフルーツケーキの層が口の中でほどけ、アプリコットコンフィチュールが奥行きを添える。手作業で仕上げたバラのデコレーションは限られたシェフにしかできない技。
編集部の感想
「バタークリームケーキの概念を覆す、軽やかなクリームとフルーツの酸味が楽しめる一品。」
◆ウェスティンホテル東京
予約期間:10月1日(水)~12月10日(水)
引き取り期間:12月18日(木)~12月25日(木) 11:00~20:00
引き取り場所: パティスリー・バイ・ウェスティン12月18日~19日、宴会場「楠」12月20日~25日
予約:ウェスティンホテル東京 クリスマスケーキ予約
問い合わせ:03-5423-7865(ウェスティンホテル東京 レストラン予約)】
6.スカーレット シルクハット(フェアモント東京)
限定25個|高さ12cm×直径15cm|¥18,000
2025年7月に開業した「フェアモント東京」が初めて迎えたクリスマスケーキには期待が集まっている。エグゼクティブペストリーシェフのデイビッド・グイマラエスシェフが手掛けたのは、ベルチームのシルクハットから着想を得たデザインのケーキ。ホワイト・ミルク・ダークチョコレートムースに、パールクラッカンやヘーゼルナッツ、プラリネを加え、香りと食感のハーモニーを生み出す。豊かなカカオの味わいが口中で溶け合い、食べるたびに驚きと幸福感をもたらす。
編集部の感想
「グイマラエスシェフの遊び心と技術が融合したケーキ。チョコレートの深い香りとナッツの食感が口の中で繊細に踊り、思わず微笑んでしまう。」
◆フェアモント東京
予約期間:10月25日(土)~12月14日(日)
引き取り期間:12月20日(土)~25日(木) 11:00~20:00
引き取り場所:35階ロビーラウンジ「Vue Mer(ビュメール)」
予約:フェアモント東京 クリスマスケーキ予約サイト
問い合わせ:03-4321-1111(フェアモント東京〈代表〉)
フェアモント東京
7.極 ガトー・オー・フレーズ(ホテル椿山荘東京)
数量限定|直径15cm×高さ6cm|¥15,000
シェフパティシエ髙木厚志シェフが手掛けるのは、毎年即完売になる王道クリスマスショートケーキ。平飼い有精卵「卵皇」のスポンジに、和三盆の優しい甘さと発酵バターのコクをプラス。北海道・根釧地区の生乳を主原料とした濃厚生クリームと国産いちごが重なり、絶妙な甘酸っぱさを生む。口に運ぶたびに幸福感が広がる逸品。
編集部の感想
「髙木シェフのこだわりを感じる素材の重なり。苺の香りとクリームの豊かなコクが、口の中で柔らかく溶け、幸せな時間を演出する。」
◆ホテル椿山荘東京
予約期間:10月1日(水)~11月30日(日)
引き取り期間:12月23日(火)~25日(木)
引き取り場所:ホテル棟3階 サロン
予約:ホテル椿山荘東京クリスマスケーキ予約サイト
問い合わせ:03-3943-7613(ホテルショップ「セレクションズ」)
ホテル椿山荘東京
8.ブッシュ ド ノエル(アンダーズ 東京)
⾧さ20cm ×幅11cm ×高さ6cm|¥7,500
今年でアンダーズ 東京で2度目のクリスマスを迎えるノルマン・ジュビンシェフ。今年は日本のエッセンスを意識したケーキが並ぶ。中でも、日本の伝統工芸「組子細工」をデザインに取り入れた和洋折衷ケーキは、カカオ風味豊かなビターチョコクリーム、チョコスポンジ、クランチ、白味噌入りミルクチョコムースを重ね、和の風味を感じさせつつ、食感の変化も楽しい。
編集部の感想
「ジュビンシェフ率いるチームが生み出した独創性が光る一品。和のエッセンスとチョコレートの濃密さが絶妙に絡み合い、口に運ぶたびに驚きと喜びが広がる。」
◆アンダーズ 東京
予約期間:10月1日(水)~12月18日(木)
引き取り期間:12月21日(日)~25日(木)
引き取り場所:アンダーズ 東京「ペストリー ショップ」
予約:アンダーズ 東京クリスマスケーキ予約サイト
問い合わせ:03-6830-7765(アンダーズ東京「ペストリー ショップ」)
アンダーズ 東京
9.エクストラスーパーダブルショートケーキ(ホテルニューオータニ)
直径18cm×高さ9cm|¥34,000
総料理長中島眞介シェフが開業40周年を記念して生み出した「スーパーショートケーキ」の進化系。博多あまおうと糖度14度以上のマスクメロン、玄米卵のスポンジ、九州大牟田産生クリームを贅沢に使用。フルーツの香りとクリームのコクが口の中で調和し、まさに最高峰の贅沢ショートケーキである。
編集部の感想
「噂通りの美味しさに圧倒されるはず。中島シェフの熟練の技と素材の選定が光り、苺とメロンの華やかな香りと濃厚クリームのバランスが絶妙で、食べる度に特別な気持ちになれる。」
10.新スーパーあまおうショートケーキ(ホテルニューオータニ)
直径18cm×高さ6.5cm|¥14,040
厳選した博多あまおう苺を贅沢に使用し、九州・大牟田産生クリームと玄米卵のスポンジが繊細に重なる。砂糖控えめのクリームは苺の酸味と香りを引き立て、口に含むと驚くほど軽やかに消えていく。素材そのものの美味しさを最大限に生かした、シンプルながらも完成度の高いケーキだ。
編集部の感想
「中島シェフが生み出した“王道の極み”。見た目はシンプルながら、口にすれば計算し尽くされた甘味と酸味のバランスに驚かされる。これこそ日本を代表するショートケーキ。エクストラスーパーショートケーキには手が届かないという方におすすめ」
◆ホテルニューオータニ(東京)
予約期間:2025年10月1日(水)~12月22日(月) ※受取日の3日前まで
引き取り期間:2025年12月20日(土)~12月25日(木) 11:00~21:00
引き取り場所:パン&ケーキ「パティスリーSATSUKI」
予約方法:ホテルニューオータニ(東京)公式サイト
問い合わせ:03-3221-7252(パン&ケーキ「パティスリーSATSUKI」)
ホテルニューオータニ(東京)
◆ホテルニューオータニ幕張
予約期間:2025年10月1日(水)~12月22日(月) ※受取日の3日前まで
引き取り期間:2025年12月20日(土)~12月25日(木) 11:00~19:00
引き取り場所:パン&ケーキ「パティスリーSATSUKI」
予約方法:ホテルニューオータニ幕張 公式サイト
問い合わせ:043-299-1639(パン&ケーキ「パティスリーSATSUKI」)
ホテルニューオータニ幕張
◆ホテルニューオータニ大阪
予約期間:2025年10月1日(水)~12月23日(火) ※受取日の2日前まで
引き取り期間:2025年12月19日(金)~12月25日(木) 10:00~20:00
引き取り場所:パン&ケーキ「パティスリーSATSUKI」
予約方法:ホテルニューオータニ大阪 公式サイト
問い合わせ:06-6920-7325(パン&ケーキ「パティスリーSATSUKI」)
ホテルニューオータニ大阪:
11.Noël de WAKO(和光)
限定10台|縦30cm × 横30cm × 高さ30cm(箱サイズ)|¥108,000


銀座の象徴・和光の建物をそのままケーキに表現。シェフの手仕事によるダックワーズ生地は香ばしく軽やかで、イチゴ・キウイ・パイナップル・マンゴーの瑞々しい果実をクリームで包み込む。トップの繊細なチョコレート細工は夜の銀座の煌めきを思わせ、見た目の美しさとともに味わいも心を躍らせる。
編集部の感想
「シェフの繊細な手仕事が随所に光り、果実とクリームの層ごとの味わいの変化が幸福感を呼ぶ。」
12. ネージュ ド ノエル(和光)
長さ17.5cm × 幅9cm|¥6,480


銀座・和光のショーウィンドウを思わせるような、雪の静けさと華やぎをまとった逸品。
小野雄大シェフが手がける「ネージュ ド ノエル」は、幾層にも重なるマロンの香りが主役。国産の和栗をベースに、イタリア産マロンペーストとフランス産マロングラッセを繊細に組み合わせ、栗本来の深みと香ばしさを引き立てている。
バニラムースのなめらかな甘さと、カシスジャムの酸味が絶妙なコントラストを生み、ひと口ごとに奥行きのある味わいが広がる。まるで雪景色の中に温もりを見つけるような、静かな幸福を感じさせるケーキ。
編集部の感想
「小野シェフの栗への情熱が伝わる、完成度の高い一品。
口に含んだ瞬間、マロンの甘やかで芳醇な香りがふわりと立ち上り、バニラとカシスが優しく寄り添う。
見た目の美しさと味の余韻、どちらも“和光らしい上質”そのもの。」
◆和光
予約期間:2025年10月15日(水)~12月16日(火)
引き取り期間:2025年12月20日(土)~12月25日(木)
引き取り場所:和光アネックス1階 ケーキ&チョコレートショップ
予約方法:和光クリスマスケーキ予約
問い合わせ:03-3562-2111(和光〈代表〉)
和光
※価格は税込みです。
※クリスマスケーキの予約や引き取り方法は各ホテルやショップに確認ください
※アレルギーの対応に関しては各自でご確認ください。
※クリスマスケーキはすべてテイクアウトでの提供です。
※ケーキの内容は、仕入れ状況などにより変更する場合があります。
Premium Japan Members へのご招待
最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。
関連記事
投稿 編集部が実食して選んだ!2025年おすすめ東京・クリスマスケーキ12 は Premium Japan に最初に表示されました。