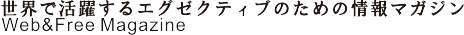人気記事
About&Contact
Stories
Japan Premium
星のやに泊まる、星のやを知る
2025.10.28
「星のや竹富島」宿泊記 その3 「種子取祭」を迎える竹富島の文化を「ミーニシ島時間」で満喫する
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「星のや竹富島」宿泊記の第3回は、「種子取祭」を迎え、竹富島の文化を最も色濃く感じることができる秋に実施される「ミーニシ島時間」を紹介。竹富島の畑文化に触れる貴重な体験をはじめ、秋限定の特別な朝食や、祭事でしか耳にすることのできない音楽など、秋ならではの島時間を満喫する充実プログラムが、訪れる人を待っています。
「星のや竹富島」宿泊記 その1 島に伝わる「ウツグミ」の精神と、流れる時間に身をゆだねる はこちらをクリック
「星のや竹富島」宿泊記 その2 降り注ぐ無数の星に見守られながら味わう極上フレンチ、「群星(むりかぶし)ディナー」のひととき はこちらをクリック
降り注ぐ太陽の光は煌めき、樹々の緑は鮮やかに輝いていますが、ふと気がつくと北風が吹いています。竹富島に秋がやってきました。季節の変わり目を島に告げるこの北風は、島言葉で「ミーニシ」。この「ミーニシ」が吹くと、島の最大の伝統行事、「タナドゥイ」と呼ばれる「種子取祭」が近づいてきたことを、島の人々は実感します。
「星のや竹富島」では、9月1日から11月30日までの間、「ミーニシ島時間」と名付けた滞在プログラムを実施。「種子取祭」に向け、次第に色濃くなっていく竹富ならではの島文化を肌で感じることができる貴重な体験が、訪れる人を待っています。
「ミーニシ島時間」を味わうには、まず「種子取祭」のことを知っておく必要があります。国の重要無形民俗文化財にも指定されているこの祭は、毎年旧暦9月(新暦では10月から11月)の間、干支(えと)では甲申(きのえさる)から癸巳(みずのとみ)にあたる10日間に開催される、五穀豊穣と子孫繁栄を願う竹富島の伝統行事です。とりわけ奉納芸能が執り行われる2日間は、竹富を離れた人々も数多く帰郷し、島は一年で最も賑わいます。600年の歴史を持つといわれる「種子取祭」を迎える秋は、いわば竹富島に流れる島時間が、祭に向けて次第に凝縮されていく時期。そんな秋の竹富島を堪能する滞在、それが「ミーニシ島時間」です。
五穀豊穣を願う神事の一端で、特別なお出迎え
チェックイン後、「ミーニシ島時間」を考案したスタッフの一人の與那城 日南楽(よなしろ ひなた)さんに案内していただき、施設内の一画へ向かいます。その一画にはなんと畑が広がっていました。竹富島特有の畑文化を継承するために設けられたその畑では、粟をはじめとして、「ヌチグサ」と呼ばれるさまざまな薬草や、小浜大豆などが栽培されているそうです。
この畑に、「サン」と呼ばれる、魔除けの意味を込めて先端を結わえた、ススキの葉を3本立てます。與那城さんが、「サン」の前で手を合わせ祈り始めました。
「サン」の前で端座した與那城さんの敬虔な姿は、畑を清浄な“気”で包みこみ、見る者の心まで豊かになったかのような気分にさせてくれます。
畑にススキの葉の先端を結わえた、3本の「サン」を挿して土を清め、五穀豊穣を願う。
「ミーニシ島時間」は、種子取祭にちなむ、特別なお出迎えから始まる。
お出迎えを終えた與那城さんに話をうかがいました。
「沖縄本島で生まれ育った私が、スタッフとして竹富島に住むようなり、最初に感じたのは沖縄と竹富の文化の違いでした。もちろん、沖縄にも独自の文化が残っていますが、竹富島の方が残っている文化の色合いが濃く、それが日常生活の中にしっかりと根付いているような気がします。『星のや竹富島』に足を運んでくださる方々に、こうした竹富独自の文化を少しでも味わっていただければと思い、種子取祭が行われる秋ならではの『ミ―ニシ島時間』を考えてみました」
「島のお祭の準備を手伝わせていただくことで、少しづつ、島に迎え入れられているような気がします」と、與那城さん。
「今年(2025年)の種子取祭は、干支の関係で11月11日から20日までですが、その前からさまざまな神事が始まります。いま私が行ったのは、種子取祭の期間中に行われる、『種子下ろし』という儀式の一部です。結んだすすきの葉の右は地の神に、左は天の神に、真ん中は病魔から竹富を救ったという伝説の漁師、アールマイにそれぞれ捧げられています。こうして清められた土地に粟の種を蒔き、その豊かな収穫を祈るのが、種子取祭の起源といわれています」
「サン」を作る際に用いるススキの葉と、種籠。籠のなかには、粟の種が入っている。
「私自身、竹富で暮らし始めた直後は、右も左も分かりませんでしたが、数多くある島の祭事のお手伝いを何度かさせていただくと、逆に『今度はちょっとここを手伝って』と声をかけていただけるようになりました。そうなると、少しづつ島の暮らしに溶けこんでいるような気がして、嬉しくなります。種子取祭を迎える秋は、もしかしたら竹富島がもっとも竹富島らしくなる季節かもしれません。『ミーニシ島時間』で体験することができる幾つかのプログラムで、お客様が少しでも多く竹富の文化に触れていただければ、と思います」
祭事にちなんだ唄と踊り、そして三線の音色を楽しむ
部屋で少し寛いだ後、「ゆんたくラウンジ」へ。ラウンジでは「ミーニシ島時間」のプログラムのひとつとして、竹富島出身の唄い手と踊り手による「夕凪の唄~秋の調べ~」が開催されます。秋の祭事や、種子取祭でしか見ることのできない奉納芸能が演目となるこの30分の公演で、種子取祭の雰囲気を一足先に味わうこともできます。
陽も次第に傾き、窓の外に見えるプールの水面が少し陰り始めたころ、唄と踊りが始まりました。揺蕩(たゆた)うような三線の音色に合わせ、ゆったりとした、そして、どことなくユーモアを感じさせる動きの踊りが続きます。
竹富島に伝わる古謡の調べにのった、ゆったりとした踊りに酔いしれる。種子取祭の際にしか見ることのできない演目が演じられることも。
唄われるのは主に「古謡」。竹富島の暮らしの中から生まれ、唄い継がれてきた、まさに土地の歴史そのものが刻み込まれた唄です。種子取祭ならではの五穀豊穣を願う唄から、長寿を願う唄、あるいは恋愛を題材にした唄など、内容はさまざま。「ゆんたくラウンジ」のソファーで寛いでいるゲストの誰もが、ゆったりとした島時間に包まれています。気が付くと、空は藍色から茜色に変わり、夕闇が少しづつ迫ってきていました。
踊を披露してくださった、宮良次子(みやらつぐこ)さんと、三線と唄を担当してくださった、花城敏明(はなしろとしあき)さん。
八重山の島々特産の豚や海の幸、そして命草(ヌチグサ)と呼ばれる野菜やハーブをふんだんに用い、そこにフレンチのエッセンスを駆使して美しく仕上げられた「星のや竹富島」の夕食は、「島テロワール」と名付けられています。この独創的な「島テロワール」を、お薦めのワインで堪能したあとは、再び「ゆんたくラウンジ」へ。八重山の焼酎をナイトキャップ代わりにいただき、部屋へ戻ります。夜空を見上げると、零れ落ちてくるかのような星空でした。
八重山の食材をふんだんに用い、そこにフレンチの手法を組み込んだ「島テロワール」は、ワインとも好相性。この日のメインは「熟成牛サーロインとマグロの炭火焼き 島醬油と黒糖のアクセント」©Hoshino Resort
種子取祭にちなんだ食材をふんだんに用いた「種子取祭朝食」
翌朝は爽快な目覚め。箒目も鮮やかに掃き清められた庭に小鳥が降りたち、囀っています。「ミーニシ島時間」の朝食が待っています。名付けて「種子取祭朝食」。その名の通り、種子取祭にゆかりのある食材をふんだんに取り入れた、竹富島の食文化を目と舌で味わう、楽しく美味しい朝食です。
まずは、「ミシャク」と呼ばれるお神酒の一種をいただきます。甘酒にも似たほのかな甘みと微かな酸味が、食欲を搔き立ててくれます。ノンアルコールなので、お酒が苦手な人でも平気。9つの升目に区切られた器には、9種類の料理が美しく盛り込まれています。ラフテースンシ―煮添え、ピンタク枝豆入りアーサー餡添え、島豆腐の粟味噌のアンダンスー添え……。料理の名前が記された紙片と照らし合わせながら、ひとつひとつ確認。料理名に入っているわからない言葉は、スタッフが教えてくれました。ちなみに、「ピンタク」とはニンニクとタコのこと。ニンニクのことを、竹富島では「ピン」と呼ぶそうです。
9つの升目に入った料理は、どれも身体に優しい味わい。「ラフテースンシ―煮添え」は中央下、「ピンタク枝豆入りアーサー餡添え」は左下。
初めて目にする料理が多いのですが、いずれも優しい味わいで、竹富島に流れる土地の力が、身体に届けられるような気がします。びっくりするくらい大きな車麩が入った味噌汁と、滋味豊かな穀物の混ぜご飯もおいしくいただきました。
竹富島は珊瑚礁が隆起してできた島で、土壌が豊かではないために米作りには適さず、島の人々は粟や麦などの穀物を大切に育ててきたそうです。「種子取祭朝食」は、五穀豊穣を願った島人の暮らしと、そこから生まれた「種子取祭」が持つ意味を、改めて思い起こさせてくれます。
神司(かんつかさ)の祈りが込められたお守りを作る
「ゆんたくラウンジ」には、約100年以上前に作られた、はた織り機が置かれています。このはた織り機でお守りの外袋を作るのも「ミーニシ島時間」のプログラムのひとつ。予め経糸(たていと)がセットされている織り機に向かい、緯糸(よこいと)を左右に通しながら打ち込んでいきます。打ち込む度に、ほんの少しづつ、布が織りあがってくるのが分かり、嬉しくなります。
昔ながらのはた織り機で織っていく。根気のいる作業だが、少しづつ織りあがる様子を目の当たりするのは楽しい。
祈祷を受けた五穀と塩を、織りあげた外袋で包んでお守りは完成。はた織りに仕組まれている糸は、竹富島の植物で染めたもの。
與那城さんにお守りの意味を説明していただきました。
「祭事の衣裳を織る際に使われていたはた織り機で織った外袋で、祭事にちなんだ五穀と魔除けの塩と詰めた小瓶をくるみます。このお守りは、竹富島の伝統的な祭事で、神様と人をつなぎ、人々の気持ちを神様に届ける役割を担う、神司(かんつかさ)と呼ばれる女性の祈祷を受けています。神様とともに生きている島の人々の思いが込められたお守りなのです」
「種子取祭」を迎える秋の竹富島で過ごす時間は、それ以外の季節より色濃く、島ならではの文化に触れることができます。五穀豊穣を願う祭事の一端を目の当たりにし、祭事でしか耳にすることができない音楽を聴き、祭事ゆかりの食材を用いた食事を味わう。そんな「ミーニシ島時間」で、島時間を五感で堪能することができました。
◆星のや竹富島「ミーニシ島時間」
・島の暮らしを始める特別なお出迎え
2025年9月1日~11月30日
・夕凪の唄~秋の調べ~
無料/2025年9月1日~11月30日 火曜日/16時45分~17時15分/ゆんたくラウンジ
・種子祭朝食
2025年9月1日~11月30日/1名4,961円(税・サ込)/7時~10時/ダイニング
・五穀のお守り作り
2025年9月1日~11月30日 火曜日・土曜日/1名4,000円(税・サ込)/10時30分~、11時30分~/ゆんたくラウンジ/
各回1組2名/当日10時までに予約
内容が変動する場合もあります。
photos by Nathuko Okada(Studio Mug)
text by Sakurako Miyao
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Japan Premium
星のやに泊まる、星のやを知る
Japan Premium
関連記事
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
2025.10.30
伊勢神宮の三節祭の一つ、最も重要なおまつり神嘗祭(かんなめさい)
外宮の由貴夕大御饌(ゆきのゆうべのおおみけ)の儀のため、斎館を出る黒田清子祭主。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
静謐、かつ清浄な空気が、夜の神域を満たしている。頭上には星。時折、カカカカカ、と鳴くムササビの声が、木立の中でひときわ響いて聞こえてくる。
年間に、約1500ものおまつりが行われる伊勢の神宮。なかでも三節祭と呼ばれる10月の神嘗祭(かんなめさい)と、6月・12月の月次祭(つきなみさい)は、浄闇(じょうあん)と呼ばれる清らかな闇の中で行われる。昼間のざわついた空気は一掃され、明かりも、手や足元を照らすごくわずかな松明やかがり火だけ。
今回は、そんな非日常の神域で行われる夜のおまつりの、なかでも神嘗祭についてご紹介しよう。
天照大御神に新穀を奉り、収穫の感謝を捧げる祭典、神嘗祭(かんなめさい)
毎年10月に行われる神嘗祭は、その年に収穫された新穀を、何よりまず天照大御神をはじめとする神々にお供えし、その恵みに対して感謝を捧げる、神宮で最も重要視されてきたおまつり。
この日は由貴大御饌(ゆきのおおみけ)と呼ばれる特別な神饌がお供えされ、米を蒸して作るという御飯(みいい)や小判型の御餅(みもち)、さらに御酒(みき)も新穀が用いられる。
神々が新穀をお召し上がりになり、新しいエネルギーを得ることによって、その威光が大いに高まると信じられてきたのである。
神様の衣も新調。榊も一新され、神嘗祭当日を迎える。
神嘗祭では、新穀だけでなく、さまざまなものが新調されるという。
たとえば、神饌やお祓いに不可欠な御塩(みしお)もその1つ。夏の間、御塩浜と呼ばれる塩田で、日本の伝統的な製塩法によって精製された荒塩(あらじお)は、毎年10月と3月に土器に詰めて焼き固められ、堅塩(かたしお)に仕上げられて保存される。
10月5日の御塩殿祭(みしおどのさい)では、御塩がうるわしく奉製されるように祈願された後、荒塩を土器に入れて焼き固める作業が行われる。
昔ながらの織機で10日ほどをかけて織られる和妙(にぎたえ=絹)。
また、神御衣(かんみそ)と呼ばれる神様の衣も、毎年10月1日から約10日間、昔ながらの織機(おりき)を用いて和妙(にぎたえ=絹)と荒妙(あらたえ=麻)が織られ、神嘗祭前日の神御衣祭(かんみそさい)で、天照大御神に奉られる。
さらに、神嘗祭の前日には、神職たちによって御正殿の御掃除も行われ、鳥居や御門、神垣などを飾るすべての榊と、榊に付けられた和紙製の紙垂(しで)も一新されるという。
神々の衣食住すべてを清らかな状態にして、おまつり当日を迎えるのだ。
一方、奉仕する神職たちも、心身を清浄にしておまつりに臨む。まず前月の晦日、つまり9月30日に、大祓(おおはらえ)で各自の罪や穢れを祓い清め、その後、神嘗祭の前々日から斎館に籠るという。
神宮を訪れるたび、心身ともに清らかですがすがしい心持ちになるのは、1000年以上もの長い間、神職や奉仕員たちが手をかけ、心を尽くして神々の衣食住を整え、自らも清浄さを心がけておまつりを続けてきた、その積み重ねによるのだろう。
神御衣祭に奉る和妙(にぎたえ=絹)が美しく織り上がったことに感謝を捧げる神御衣奉織鎮謝祭(かんみそほうしょくちんちゃさい)の様子。布のほか、針や糸なども奉納される。
おまつりに先駆けて行われる、伊勢市民による初穂曳
神嘗祭の中心となるのは、神々にご馳走をお供えする由貴大御饌(ゆきのおおみけ)の儀。外宮は10月15日と16日、内宮は16日と17日、それぞれ2度行われる。神宮のおまつりは、すべて外宮先祭(げくうせんさい)、つまり外宮から先に行われるのだ。
もっとも、夜のおまつりに先駆けて、10月15日の午前中には、ハッピ姿の伊勢市民が奉曳車に初穂を乗せ、木遣歌(きやりうた)やかけ声もにぎやかに伊勢市街を練り歩いた後、外宮の宮域内に曳き入れる陸曳(おかびき)という市民行事が行われる。
神嘗祭では、天皇陛下が皇居内の水田でお手植えされ、また収穫された御初穂をはじめ、全国の一般農家からも初穂が奉献されるのだ。これらの稲束は懸税(かけちから)と呼ばれ、感謝を込めて神々へ捧げられる。
さらに、翌10月16日の午前中には、やはり奉献された初穂を、今度は初穂舟と呼ばれる舟に乗せ、五十鈴川を遡って内宮の宮域内に曳き入れる川曳が行われる。
全国の農家から奉献された懸税(かけちから)は、御正殿から2番目の垣に当たる内玉垣(うちたまがき)に掛けられる。古くは年貢のようなものだった考えられている。
内宮の宮域内に初穂を曳き入れる初穂曳きの様子。伊勢市民たちが五十鈴川を遡る形で、初穂舟を曳いていく。途中、橋の下を舟が通るときは、橋を渡る人や車を一時通行停止にする場面も。稲魂(いなだま)が宿る尊いお米の上をまたがないという、日本人独特の心遣いが感じられる。
神嘗祭のはじまりは、地主神への祈りと、
奉仕する神職一人ひとりが神の御心にかなうかを占う神事から
神嘗祭のはじまりは、夕刻5時。
夜に行われる由貴大御饌(ゆきのおおみけ)の儀に先立って、まず内宮の御正宮で、興玉神祭(おきたまのかみさい)と御卜(みうら)の儀が行われる。
興玉神は、天照大御神がご鎮座される場所である大宮処(おおみやどころ)の地主神。御正殿の周囲をぐるりと囲む垣の内側、つまり、御垣内(みかきうち)の西北の隅に祀られている。その神前で、奉仕する神職全員が、これから始まる神嘗祭が支障なく行えるように、祈りを捧げるのだ。
その後、やはり御垣内(みかきうち)の中重(なかのえ)と呼ばれる、清浄な石が敷き詰められた上に、祭主以下、すべての神職たちが着座。その1人ひとりが神の御心にかなうかを占う、御卜(みうら)の儀が行われる。
古式の姿をとどめる庭上座礼(ていじょうざれい)
神宮の祭祀は、他の神社のように社殿などの殿内の床上ではなく、すべてこの中重(なかのえ)のように、屋外の白石が敷き詰められた上に、薄い敷物(舗設=ふせつ)を敷いて座る、庭上座礼(ていじょうざれい)という作法で行われる。
おまつりの一場面。拝礼をする神職たち。
社殿がなかった時代の古代の祭祀は、神は人々の招きや願いに応じて天から降り来たり、しばし巨岩や大木を依代として人間界で過ごした後、再び天へ戻ると考えられていた。神宮の庭上座礼には、そんな古式の祭祀の姿がうかがえるのだ。
神慮にかなうかを、音で知らせる日本独特の音への感性
さて、御卜の儀は、3人の神職によって進められる。まず1人が、今回奉仕する神職1人ひとりの名前を読み上げ、そのつど、別の神職が息を吸って、まず「うそぶき」と呼ばれる口笛のような音を、続けて別の神職が、笏(しゃく)で箏板を叩き、コンという音を鳴らす。無事両方の音が鳴れば、名前を呼ばれた神職の奉仕は、神意にかなったとみなされる。
なかでも注目したいのは、「うそぶき」が、息を「吐く」のではなく、「吸う」ことによって音が鳴らされること。これについては、鎌倉時代に書かれた『皇太神宮年中行事』に、以下の一文が記されている。
『音の鳴るをもってきよらかとしる、鳴らざるをもって不浄としるなり』。
「つまりうそぶきの音が、清浄か不浄かを知らせるということです」。神宮の広報室次長の音羽悟さんは言う。
「神慮にかなうか」という判断に、「清浄か不浄か」が重視され、その告知を音が担うということに、日本独特の音への感性を垣間見る思いがする。
30品目ものご馳走が並ぶ豪華な由貴大御饌。心を尽くしてお供えされる神饌
そして、夜。
太鼓が3度打ち鳴らされ、いよいよ由貴夕大御饌(ゆきのゆうべのおおみけ)の儀が始まる。由貴大御饌の儀は、宵(午後10時)と暁(午前2時)の2度行われ、宵を夕(ゆうべ)、暁を朝(あした)と表現されているのだ。
ほどなく、太鼓が再び3度鳴らされ、遠くから神職が参進する音が聞こえてきた。玉砂利を踏みしめ歩く一糸乱れぬその音は、途中修祓(しゅはつ)を行うために祓所(はらえど)に参入したときにしばし止み、その後は御正宮を目指してひたすら近づいてくる。
間近に迫ってくる参進の音。それに伴って聞こえてくる、ひそやかな「おー」という警蹕(けいひつ=先祓い)の声。静かな、だがたしかな存在感を放つ音とともに、純白の斎服を身につけた神職たちが、かがり火の中に浮かび上がる。その姿は、ほどなく白い御幌(みとばり)の向こうに消えていった。
ここから先は、時折聞こえるさまざまな音と文献を頼りに、祭祀の様子を想像することになる。
外宮の御幌(みとばり)の向こうに姿を消す神職たち。
大正時代の神職、阪本廣太郎の著書『神宮祭祀概説』によれば、由貴大御饌は、御正殿の前に置かれた素木(しらき)の案と呼ばれる大きな机の上にお供えされるという。
ちなみに、由貴とは「神聖でこの上なく尊い」、大御饌は「立派なお食事」という意味。その言葉通り、神饌には、神宮御園(みその)と呼ばれる菜園で収穫された野菜や果物のほか、海川山野の旬の食材が30品目も並ぶという。
特にアワビは、内宮の由貴大御饌の儀の直前に、御正宮正面の石階段の下にある御贄調舎(みにえちょうしゃ)で、生のアワビを調理する儀式が行われる。
この儀式では、天照大御神のお食事を司どる御饌都神(みけつかみ)であり、外宮の御祭神でもある豊受大御神(とようけのおおみかみ)をお迎えし、その神前で、神職が清浄な小刀と御箸を用いて、アワビに3度切り込みを入れ、御塩で和えるという。
いかに心を尽くして神饌をお供えするか、この儀式1つからもうかがい知ることができる。
外宮の御正宮へ向けて参進する祭主以下神職たち。
内宮の別宮、荒祭宮で行われる由貴大御饌の儀。神嘗祭は、内宮、外宮の両正宮だけでなく、別宮、摂社、末社、所管社に至るまで、125社すべてで行われる。
さらに、神饌をお供えする際は、龍笛(りゅうてき)や篳篥(ひちりき)などの楽の音に合わせて、神楽歌が歌われる。
ちなみに由貴大御饌の儀では、御酒は3献差し上げることになっていて、その1献ごとに、言葉や節を変えて楽が奏でられ、神楽歌が歌われるのだ。
神宮独特の拝礼作法である八度拝と八開手(やひらで)、そして楽の音や神楽歌
清らかな音に満ちた夜のおまつり
大宮司が微音(=神様だけに聞こえるような微かな声)で祝詞を奏上するのは、1献目の御酒を差し上げた後。続いて、神宮独特の拝礼作法である八度拝、八開手(やひらで)が行われる。
この拝礼作法は、座した状態から立ち上がる「起拝(きはい)」という所作を、まず4度繰り返し、次に伏した姿勢で柏手(かしわで)を8つ打つ。そして、座したままで一拝。再び同じ順序で、4度の起拝と8つの柏手を繰り返すという流れになっている。
八度拝の様子。2025年9月に行われた遷宮関係のおまつり御船代祭の一場面。八度拝と八開手という一連の作法を神職全員で行うことにより、個の存在が消え去り、自ずと全員の呼吸が1つになっていく感覚が生まれると、先の『神宮祭祀概説』には書かれている。
浄闇の中、時折聞こえる楽の音と神楽歌。そして、しめやかな八開手の音。年に1度の新穀をお供えする神嘗祭の夜のおまつりは、真心の奉納と表現したくなるような、清らかな音に満ちていた。
天皇陛下から奉献される幣帛を、勅使が奉る奉幣の儀
最後を締めくくる御神楽(みかぐら)の儀
翌10月16日は、外宮で正午から(内宮は17日)、天皇陛下が奉献される幣帛(へいはく)を、勅使が奉る「奉幣の儀」が行われる。幣帛とは、神饌以外のお供え物のこと。貨幣がなかった時代は、絹織物などが最も貴重な品とされていたことから、神宮では今もその伝統を受け継いで、五色の絹など、数種の織物を奉献していただくという。
最後は、神宮の楽師による御神楽(みかぐら)の儀。夕刻から夜にかけて、4時間にわたり奉納される楽と舞で、神嘗祭は締めくくられる。
「夜は神様が活動される時間です。日が暮れて暗くなると1日が終わり、新たな1日が始まる。そのもっとも大切な1日のはじまりのときに、神様の御心をお慰めさし上げる。そんな古代人の考え方が今に受け継がれています」と音羽さん。
古式をとどめた神宮の祭祀には、日本人が大切にしてきた心が詰まっている。
おまつりの間中、焚かれるかがり火。
Text by Misa Horiuchi
伊勢神宮
皇大神宮(内宮)
三重県伊勢市宇治館町1
豊受大神宮(外宮)
三重県伊勢市豊川町279
文・堀内みさ
文筆家
クラシック音楽の取材でヨーロッパに行った際、日本についていろいろ質問され、<wbr />ほとんど答えられなかった体験が発端となり、日本の音楽、文化、祈りの姿などの取材を開始。<wbr />今年で16年目に突入。著書に『おとなの奈良 心を澄ます旅』『おとなの奈良 絶景を旅する』(ともに淡交社)『カムイの世界』(新潮社)など。
写真・堀内昭彦
写真家
現在、神宮を中心に日本の祈りをテーマに撮影。写真集「アイヌの祈り」(求龍堂)「ブラームス音楽の森へ」(世界文化社)等がある。バッハとエバンス、そして聖なる山をこよなく愛する写真家でもある。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
Premium Calendar
関連記事
投稿 伊勢神宮の三節祭の一つ、最も重要なおまつり神嘗祭(かんなめさい) は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
木と語らい、愛を描く
2025.10.30
藤田理麻新作絵画個展『Evergreen 〜木魂の愛と智慧〜』
SecretPond©RimaFujita2025
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
アーティスト・藤田理麻による新作絵画個展『Evergreen ~木魂の愛と智慧~』が、11月12日(水)から18日(火)まで伊勢丹 新宿店アートギャラリーで開催される。会期中の11月15日(土)午後2時30分からは、会場にてアーティスト・トークおよびインスタライブも実施予定だ。
Sunrise©RimaFujita2025
本展のテーマは、藤田が暮らす北カリフォルニアでの夜の散歩から着想を得たもの。毎晩のようにジュニパー(西洋ネズ)の並木道を歩く彼女は、その中の一本と対話を重ねてきたという。「今回の新作は、そんなジュニパーの木が夢に現れたビジョンをもとに描かれた。「木も人間と同じくこの地球に生きる存在。私たちよりも長く、深くこの星を見つめ続けている」と語る藤田は、木々が授けてくれる愛と智慧を絵筆に込めた。
Butterflies©RimaFujita2025
また本展では、今年90歳を迎えたダライ・ラマの生涯を描いた絵本『The Extraordinary Life of H.H. The Fourteenth Dalai Lama(ダライ・ラマ法王第十四世の生涯)』の一点物の版画も特別展示。藤田が描く穏やかな色彩と祈りの筆致が、法王の壮大な人生を静かに讃える。
アートを通して愛と祈りを描き続ける藤田理麻。私たちのそばに静かに寄り添う木魂の愛を、彼女の作品世界を通じて感じてみてはいかがだろうか。
◆藤田理麻 新作絵画個展「Evergreen ~木魂の愛と智慧~」
【会期】2025年11月12日(水)~11月18日(火)
【会場】伊勢丹新宿店 本館6階 アートギャラリー
【アーティスト・トーク&インスタライブ】11月15日(土)午後2時30分~
※最終日は午後4時終了
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.10.30
星野リゾート トマム「アイスヴィレッジ」開幕
Features
2025.10.30
食べる”と“学ぶ”で、お米文化を未来へ
関連記事
投稿 藤田理麻新作絵画個展『Evergreen 〜木魂の愛と智慧〜』 は Premium Japan に最初に表示されました。
Experiences
Spotlight
帝国ホテル総料理長杉本雄のサステナブルな視点
2025.10.30
帝国ホテル総料理長・杉本雄の探求 ~持続可能な美味への旅・石川~
帝国ホテル 東京の厨房で、日々料理を生み出す杉本雄総料理長。その眼差しが今、遠く石川県の豊かな大地と海に向けられている。
杉本シェフは、2021年より持続可能な食のあり方を考え、食品ロスの削減に取り組み、ラグジュアリーとサステナビリティーの両立を掲げ、「おいしく社会を変える」というテーマに取り組んできた。
「世間の潮流でサステナブルと言っているように聞こえますが、調理現場と生産現場で起きていること、思っていることの温度差、生産現場での課題など、現地に行ってたくさんわかることがあります。現地で生産者の顔を見て、その思いを汲むと、食材をどのように扱うべきかということが、おのずと見えてくると思います」
きっぱりと語る杉本シェフの言葉には、単にラグジュアリーであることや、美味しさの追求を超えた、深い想いが込められている。気候変動や資源問題が叫ばれる今、一流の料理人として、また一人の人間として、持続可能な食材への探求は避けて通れない道だ。
そんなシェフが昨年より選んだ舞台が、日本海の恵みと豊穣な土地を持つ石川県。能登の里海、加賀の里山で育まれる食材には、どんな可能性が秘められているのか。杉本シェフの石川への旅が始まった。
豊かな山、海に育まれた優れた石川県の農林水産物を見つける
石川県は、日本海に面した本州の中央部に位置し、能登半島と加賀地方という個性豊かな二つの地域から成り立っている。北の能登半島では、複雑に入り組んだ海岸線が生み出す豊かな漁場と、伝統的な里海文化が息づいている。一方、南の加賀地方は、白山連峰から流れる清らかな水に育まれた肥沃な平野部と、日本三霊山の一つである白山の恵みを受けた里山の自然が広がる。
石川県の豊かな大地では、歴史ある伝統野菜から県が新たに開発したブランド農産物まで、実に多彩な農産物が育まれている。杉本シェフはまず、「加賀丸いも」を栽培する岡元農場を訪ねた。
「加賀丸いも」は、石川県の能美市・小松市で栽培される特産のブランド山芋だ。ヤマノイモ属ツクネイモ群に属する黒皮種の大和芋で、ソフトボール大の大きさがあり、すりおろすと驚くほどの粘りと食感がある。
石川県の能美市・小松市で栽培される特産のブランド山芋、「加賀丸いも」。
杉本シェフは味見をしながら、「これは楽しめる食材ですね。何か違う食べ方のアイデアをいただいたような気がします」とにっこりした表情を浮かべ、「卵とかお魚とか、密着する食材に使っていくと、広がる感じがしますね」とあれこれ考えていた。
次に訪れたのは、能美市の米どころの「たけもと農場」だ。たけもと農場では自家製の生藁堆肥や白山の雪解け水を活かし、稲作技術や土作りに徹底してこだわっているという。2011年からイタリア米の栽培を開始し、試行錯誤を重ねてきた。現在では8品種の米を扱う中で、日本でのイタリア米の第一人者的な存在となっている。
「カルナローリ」は、本場イタリアのリゾットやパエリアに最適な国産米として高い評価を受けているそう。杉本シェフは黄金色に輝く稲穂を見つめながら、生産者の方の言葉に真剣に耳を傾けていた。
ついで訪れたのは、ホテルやレストランのシェフなどプロからも支持されているという「本田農園」だ。本田農園は地元の小学校や幼稚園から出る給食の生ごみを堆肥に使用し、作物が丈夫で健全に育つ土壌造りをしている。また、農薬の使用を控えつつ、失敗の分析と改善を徹底することで、安定して高品質なトマトを生産していると定評がある。
6棟のハウスから始まった本田農園だが、今では約70棟あるという。栽培されているのは中玉トマトが多いそうだ。
ハウスの中で食べてみてくださいと言われ、杉本シェフが枝から取り、かじってみる。「おいしい!皮が柔らかくて、みずみずしく甘みがありますね」と、笑顔に。華小町や華おとめ、フルティカなどの品種が人気だ。
石川の漁港で出会う旬の海の幸
実はこの日、9月1日は底引き網漁の解禁日であった。杉本シェフは橋立漁港を訪れ、漁を終えて帰港した船からの水揚げや選別の様子を見学し、底引き網漁の解禁日で活気あふれる夕方のセリにも立ち会った。
この漁港の最大の特徴は、その立地が生み出す抜群の鮮度である。橋立漁港は地形的に、漁場が港から非常に近いため、漁に出た船は十数時間で帰港することができる。そのため鮮度を落とすことなく新鮮な魚をセリにかけることができる。
港には底引き網ではノドグロや甘エビ、ガスエビ、カレイ、ミズイカ、毛蟹、定置網では、サワラやサバなど多彩な旬の魚が次から次へと水揚げされていた。杉本シェフはその様子を間近で眺め、漁師さんから直接いただいた獲れたての甘エビを試食。港や船を見ながら味わえるなんて、最高の気分!
その後しばらく魚市場の中を回り、白ガスエビの8パターンにも及ぶ選別風景や毛蟹の状態などを眺めた後、杉本シェフは県オリジナルの農産物を栽培するほ場へ向かった。
石川県が誇る、極上の果実たち
石川県が誇る宝石のようなブドウ「ルビーロマン」をご存じだろうか。石川県が14年の歳月を費やして育成したオリジナル品種であり、黒色の大粒ブドウ「藤稔(ふじみのり)」をもとに、味や色、房、粒の大きさなどの品質や栽培のしやすさを徹底的に調査・研究して誕生した。石川県最高峰のブドウだ。県内6つのJAの管内で栽培されており、2025年の初セリでは、1房100万円の値を付けた。
この日はルビーロマンの生産者のうちの1軒「丸山ぶどう園」を訪ねた。栽培時のご苦労についてお話しを伺っている途中、なんとルビーロマンの味見をさせていただくことに。杉本シェフは「一粒が重く、おいしく、ジューシーです!」と感嘆の声を挙げた。
もう一つの石川県オリジナル品種が「加賀しずく」だ。これは、石川県が16年の歳月をかけて育成した新しいナシの品種。そのナシの産地のひとつである奥谷梨生産組合を訪ねた。
大玉で高い糖度と、整った形をもつものは、1玉1,000円以上の価格がつくことも。昼夜の寒暖差に恵まれているので、味(あじ)が引き締まるそうだ。おしゃれなネーミングや上品な甘さとなめらかな食感があいまって、石川県のブランド梨として人気を誇る。
ずっしりと重い「加賀しずく」を手に取る杉本シェフ。
橋立漁港での思い出 セリの熱気、漁師との出会い
杉本シェフは、再び橋立漁港へ。橋立では一年を通じて多彩な漁が営まれている。春から夏の潜水漁をはじめ、定置網、刺し網漁など。秋には底びき網漁。そして、なんといっても冬の加納ガニ・香箱ガニ。一年を通し豊富な魚種が水揚げされる。杉本シェフが求める「素材の力を最大限に引き出す」料理にとって、この橋立の魚介は理想的な食材と言えそうだ。
そろそろセリの時刻となった。橋立漁港の底びき網解禁日のセリは、秋の訪れを告げる伝統的なイベントだ。前日の夜、漁船は出港し、朝または昼過ぎに漁から帰港する。水揚げされた魚は種類ごとに素早く仕分けされ、すぐにセリ場へ運ばれる。港や市場には漁協職員や仲買人が集まり、威勢の良い掛け声のもと活発にセリが行われる。杉本シェフもその様子を見学。初物を求める消費者や見学者も多く訪れ、港は活気にあふれていた。
帝国ホテル杉本総料理長と漁師との座談会
石川県の豊かな食材を巡る杉本シェフの旅は、翌日橋立漁港での座談会で幕を閉じた。出席者は杉本シェフと石川県漁業協同組合の橋本勝寿会長、橋立漁港で長年海を知り尽くした辺本准船長(第十八薫勝丸)、北川智生船長(愛明丸)、遠塚谷透船長(第五恵比寿丸)の3名だ。
今回のツアーのコーディネートをしてくださった石川県農林水産部水産課の島田拓土氏は、座談会の進行を務め、こう語った。
「2024年に発生した能登半島地震と豪雨災害により、石川県の漁業は大きな打撃を受けました。ほぼすべての地区で漁を行えるようになったのが2024年11月。今年、石川は震災復興元年として、4月から新しい未来を見据え、PRも含めて気合を入れていこうとしていました。そうした中、帝国ホテル 東京でのイベントの実施もあり、杉本シェフ自らが2度にわたり石川に足を運んでくださり、石川県の状況に気を遣っていただきました。今回、漁師と膝を突き合わせ、漁師の本音も聞くという初めての試みとして、この座談会の開催に至りました」
座談会の参加者左から「第十八薫勝丸」船長 辺本准さん、「第五恵比寿丸」船長 遠塚谷透さん、帝国ホテル総料理長 杉本雄さん、石川県漁業協同組合理事 加賀支所運営委員長橋本勝寿さん、「愛明丸」船長 北川智生さん
座談会では、能登半島地震復興後の漁協によるイベントを通じた集客の取り組みや、石川県内の各地域が一つになって復興を盛り上げている様子、困っている輪島の漁師たちに橋立漁港の漁師が不足のロープを支援した話、気候変動による海水温の変化、若い漁師や船長の育成など、多数の話題が出た。
杉本シェフは、こう語った。
「昨日水揚げされた新鮮な魚を、漁師さん行きつけのお店で、これ以上ない鮮度でおいしくいただき、まさに最高の味わいを体験させていただきました。今まで2回石川に来て、県外の我々がどれだけ支援や復興に貢献できるかを考えていました。漁師の仲間たちが助け合っている姿を見て感銘を受けました。私はそうした石川の人々の想いを、料理に込めてお客様に伝えるようにしています」
杉本シェフの言葉からは、石川県への想いがひしひしと伝わってくる。石川の食材の素晴らしさは、その背後にある人々の想いの深さにあるのだと訴えかけているようだ。
「これからも生産者の方との対話を積極的に行い、石川のおいしい食材をどんどん使い、食材を単なる素材として扱うのではなく、その背景にあるストーリーと想いを理解し、それを料理で表現し伝えることができればと思いました。より一層、料理への意欲が湧きました」
石川での旅を終えて
「地元の第一線で働いている人たちがカッコいい、いい顔をしている。汗だくで働く姿もカッコいい。食材がなければ我々は何もできない。食材の一生を考えれば、料理人が最後に手を加えるのはほんの数%に過ぎない。生産者と料理人の双方が互いの想いを共有し、持続可能な食の未来に向けて歩み続けることの大切さを改めて確認する貴重な機会となりました」
杉本シェフの言葉は深く心に響いた。
杉本 雄 Yu Sugimoto
1999年、帝国ホテルに入社し、料理人としてのキャリアをスタート。2004年に退社し、渡仏。2006年にパリの名門ホテル「ル・ムーリス」の3つ星レストランに入り、ヤニック・アレノやアラン・デュカスのもとで、シェフとして研鑽を積み、責任者の役割も担った。2017年帝国ホテルに再入社し、2019年に東京料理長就任。2025年4月、帝国ホテルの全事業所で500人の料理人を束ねる第3代総料理長に就任。
文・粟野真理子 Mariko Awano
ジャーナリスト。パリに20年以上在住し、日本の女性誌など多数の雑誌や旅行書で取材・執筆活動を行っている。現在は東京を拠点に活動。著書に『パリから一泊!フランスの美しい村』(集英社)など。
関連リンク
Premium Japan Members へのご招待
最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。
関連記事
投稿 帝国ホテル総料理長・杉本雄の探求 ~持続可能な美味への旅・石川~ は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
詩楽劇『八雲立つ』——伝統と革新が織りなす舞台
2025.10.29
尾上右近、紅ゆずる、尾上菊之丞らが登場。豪華出演陣が紡ぐ神話の世界
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
2025年12月29日(月)から31日(水)まで、東京国際フォーラム ホールB7にて詩楽劇『八雲立つ』が上演される。出演は、歌舞伎俳優の尾上右近をはじめ、元宝塚歌劇団星組トップスター紅ゆずる、バイオリニストの川井郁子、日本舞踊尾上流四代家元の尾上菊之丞ら。本物の装束を纏い、古典芸能と音楽が響き合う壮大な舞台が繰り広げられる。
本舞台は、“伝統と革新”をテーマに日本文化の新たな魅力を発信するプログラム「J-CULTURE FEST」の一環として上演されるもの。
古代神話に描かれた神々の物語を題材に、プロフェッショナルたちが本物の装束をまとい演じる詩楽劇『八雲立つ』は、2022~2023年の年末年始公演で大きな反響を呼んだ作品。今回の公演では、日本という国の構築に大きな役割を果たした神・スサノオの成長物語を軸に、岩長姫との魂の交わりを音楽と舞で描く。
脚本を手がけるのは、新作歌舞伎『風の谷のナウシカ』などで知られる戸部和久。構成・演出は、新作歌舞伎『刀剣乱舞』でも高い評価を得た日本舞踊尾上流四代家元の尾上菊之丞が担当。
須佐之男命(スサノオ)役には、歌舞伎界の若き俊英・尾上右近。岩長姫役を、元宝塚歌劇団星組トップスターの紅ゆずるが演じ、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)役に佐藤流司、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)役に和田琢磨、木花咲耶姫(このはなさくやひめ)役に梅田彩佳と、ジャンルを超えた豪華キャストが集結。
音楽は、ヴァイオリニスト川井郁子と和楽器が共演。さらに石見神楽 万雷の大蛇の舞が舞台を彩り、神話世界の神秘と迫力を体験できる内容となっている。
本公演にあわせ、東京国際フォーラムで「和の伝統に親しむ」をテーマにしたワークショップも開催。いけばなや鼓(つづみ)、江戸木版画(浮世絵)、巨大書道パフォーマンスなど、日本の文化を体感できる多彩なプログラムが予定され、現在公式サイトで予約を受付中だ。
本作冒頭では、2025年の穢れを払い2026年を寿ぐ神職による修祓(しゅばつ)が執り行われ、新年を迎えるにふさわしい舞台として注目を集めそうだ。
◆J-CULTURE FEST presents 詩楽劇『八雲立つ』
【公演日程】2025年12月29日(月)〜12月31日(水)
12月29日(月) 15:00/18:30
12月30日(火) 15:00/18:30
12月31日(水) 11:30/15:00
【会場】東京国際フォーラム ホールB7(東京都千代田区丸の内3-5-1)
【出演】尾上右近、紅ゆずる、佐藤流司、川井郁子、尾上菊之丞 ほか
【脚本】戸部和久
【構成・演出】尾上菊之丞
【チケット】全席指定・税込・一般販売開始11月1日(土)10:00
SS席12,000円、S席10,000円 、A席6,000円
※未就学児入場不可
※車椅子でご来場される方は、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.10.29
星野リゾート トマム「アイスヴィレッジ」開幕
Features
2025.10.29
食べる”と“学ぶ”で、お米文化を未来へ
関連記事
投稿 尾上右近、紅ゆずる、尾上菊之丞らが登場。豪華出演陣が紡ぐ神話の世界 は Premium Japan に最初に表示されました。
Stories
Premium X
鹿児島の「宝」を巡る旅
2025.10.28
鹿児島が誇る工芸、薩摩切子を手掛ける二つの工房を訪ねて
「幻の工芸品」とされてきた薩摩切子は40年前、職人たちの努力により「島津薩摩切子」として蘇った。なかでも江戸時代当時の姿を再現した「復元」シリーズは、圧倒的な存在感を放つ。「薩摩ガラス工芸」にて。(価格は後述)
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
どうすれば、こんな美しいグラスができるのだろう? 切子に出会った人は、誰しもその美しさに心を奪われ、そして不思議に思う。切子とはカットガラスの日本での呼び名である。日本各地に残る切子のなかでも、名が知られているのは薩摩切子と江戸切子。とりわけ薩摩切子は、厚めのガラスに施された精緻なカッティングが生みだす文様と、光を受けて煌めく艶やかなグラデーション、手に持ったときにずしりと感じる重厚感を特徴とする。「南の宝箱 鹿児島」を巡る旅、今回はこうした薩摩切子を手掛ける二つの工房「薩摩ガラス工芸」と「ART DESHIMARU」を訪れた。
薩摩ガラス工芸
100年以上も製造が途絶えた薩摩切子を復元
薩摩切子は、島津家28代当主の島津斉彬が、近代化事業の一環としてガラス製造を進めたことに端を発するものの、明治維新やそれに続く西南戦争の混乱により、100年以上も製造が途絶えてしまった。そのため「幻の工芸品」とも称されてきた。
薩摩の紅硝子(びーどろ)と呼ばれ、かつては島津家から公家や大名家への贈答品として珍重されてき薩摩切子を、なんとか復元させたい。人々のそんな熱い思いがかない、1985年から「薩摩ガラス工芸」として、復元に向けての取り組みが始まった。翌年には工場が完成。場所は島津家ゆかりの地「仙巌園」の隣で、復元の中心となったのは、やはり島津家だった。工場の建設と並行し、残っていた資料などをもとにした試作品製作の試行錯誤が繰り返され、1986年にようやく復元に成功し、商品化も始まった。100年以上の歳月を経て、こうして蘇った薩摩切子は「島津薩摩切子」と名付けられた。
厚さ1㎜前後の薄手の色ガラスにシャープなカットを入れ、全体的に軽やかな仕上がりを特徴とする江戸切子に対し、薩摩切子は、時には5㎜もの厚さの色ガラスへのカッティングと、クリスタルガラスならではの透明感が複雑に入り混じったさまざまな文様が、ひと際華やかな表情を醸し出す。
なかでも、クリスタルガラスと、その外側に被せた色ガラスという2層ガラスの接面点への繊細なカッティングが醸し出す、「ぼかし」と呼ばれる独特のグラデーションの風合いが、文様により深い奥行きをもたらす。
「薩摩ガラス工芸」は「島津薩摩切子」を生み出す工場と、工場に隣接するショップ「磯工芸館」などがあり、見学が可能な工場で、こうした特徴を持つ薩摩切子が出来上がっていく様子を、間近に見ることができる。
「薩摩ガラス工芸」の工場は見学が可能。薩摩切子が生みだされていく様子を間近で見ることができる。
阿吽の呼吸で合体する、高温の色ガラスとクリスタルガラス
「吹き場」と「カット場」。工房は大きく二つに分かれている。「吹き場」は薩摩切子の生地を作る場。文字通り、吹き竿でガラスを吹いて成形していく場だ。二人の職人がそれぞれステンレスの吹き棒を持っている。片方の吹き棒の先端には、窯から巻き取られた色ガラスの塊が、もう片方の先端にも窯から巻き取られたクリスタルガラスの塊がついている。もちろん竿の先のガラスは、窯から取り出したばかりの、ドロドロに溶けオレンジ色に発光している液状の高熱ガラスだ。
色ガラスの吹き棒を持った職人が金型に色ガラスを吹き込んだ後、すぐさま今度はクリスタルガラスの吹き棒を携えた職人がその金型の中へクリスタルガラスを吹き込む。阿吽の呼吸でその二つを合体させることで、外側が色ガラス、内側がクリスタルガラスという生地が作られていく。作業は高温の室内のなか黙々と進む。二人が声をかけあうこともない。お互いの技術を信頼した熟練の職人技がそこにはある。
吹き竿に巻き取られた約1400度の高温のガラスの塊を成形していく。
吹き竿の先の二層となったガラスは、やがて金型の中に吹き込まれ、形が整えられていく。
内側にクリスタルガラス、外側が色ガラスでできた分厚い生地をカッティングすることで生まれる薩摩切子ならではの美しさ。製造現場を見学することで、その美しさの成り立ちを肌で感じることができる。
「色被せ」(いろきせ)と呼ばれるこの工程の後、色ガラスとクリスタルガラスの2層となったガラスの塊は、再び金型の中に吹き込む「型吹き」、16時間かけて冷却する「徐冷」(じょれい)を経て、検査した後に「カット場」へ運ばれる。
「吹き場」が“動”の作業ならば、「カット場」は“静”の作業だ。職人は椅子に座り、各々の作業をこなしていく。金型から取り出された原型に、カット模様の線を油製ペンで描く「当たり」。描かれた線にそっておおまかな模様をグラインダーで削る「荒ずり」。そしてさらに細かな模様を施す「石かけ」と最終工程の「磨き」。集中し、黙々と作業を進める職人の姿は美しい。
文様の下書きとなる縦横の分割線を油性ペンで引く、「当り」(あたり)と呼ばれる作業。
高速で回転するダイヤモンドホイールと呼ばれる工具で、ガラスの表面が削り込まれていく。
「吹き場」ではどろどろに溶け、オレンジ色に発光していた液状の高熱ガラスが、「カット場」では、紅や藍を纏った硬質な薩摩切子へと変貌していく工程を目の当たりにすると、100年以上も前にこの複雑な工法を編みだした人々の知恵と、途絶えていたそれを再現した薩摩の人々の熱意に胸を打たれる。
20年前に再現された、気品あふれる「島津紫」
ショップ「磯工芸館」は工場のすぐ隣の建物だ。足を踏み入れると、煌びやかな色彩の洪水にまず圧倒される。藍、緑、黄、紅、金赤、島津紫。6色の色ガラスを纏った数多くの薩摩切子が一斉に微笑みかけてくる。厚目のガラスが発する重厚な赤や青、軽やかに輝く緑と黄色。精緻なカッティングがこうした色彩をより鮮やかに引き立てている。展示されている商品も豊富だ。花瓶、鉢、タンブラー、小皿、猪口、愛らしいペンダントトップ……。工場で日々行われている大変な作業を目の当たりにしてきただけに、ひとつひとつの商品がより存在感を増してくる。
色とりどりの薩摩切子が並ぶショップは、まるで万華鏡の中を歩いているかのよう。
江戸時代に作られた当時の姿を今に伝える「復元」シリーズは、薩摩切子らしい重厚感と存在感を放つ。右、酒瓶「亀甲」・407,000円 左、丸十花瓶・407,000円(価格は税込)
「復元シリーズ」には、猪口などの小物類も豊富。右から、小付鉢・48,400円、猪口大・33,000円、猪口大・36,300円、脚付杯(中)107,800円。(価格は税込)
なかでも目を引くのが、「島津紫」と呼ばれている、気品溢れる紫だ。島津斉彬が所持していた薩摩切子の茶碗に使われていた優美な紫色をもとに、20年前に再現された紫色が彩る鉢やタンブラーが、薩摩切子の伝統と格式を象徴する。また、2025年は薩摩切子復元の40周年にあたる記念すべき年で、記念作品や限定商品も幾つか作られている。
復元40周年を記念して作られた、大鉢・1,210,000円と、タンブラー・82,500円。(価格は税込)
世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成遺産として登録されている「仙巌園」は、鹿児島を訪れた人の多くが、旅の目的地とするスポット。薩摩藩主の別邸だった御殿と尚古集成館で島津家の歴史や薩摩藩の偉業に触れたあとは、「薩摩ガラス工芸」で、薩摩の人々が育んできた美意識に触れる。こうした充実のひとときを、桜島が静かに見つめている。
薩摩ガラス工芸
鹿児島県鹿児島市吉野町9688ー24
Tel:099⁻247-2111
営業時間:8時30分~17時
定休日:月曜日、第3日曜日
ART DESHIMARU
試行錯誤して辿り着いた、黒の薩摩切子
「黒豚、黒牛、黒糖、黒酢、そして黒麹を使った本格焼酎。鹿児島は黒の文化が息づく土地です。だとしたら、黒い薩摩切子があってもよいのでは。そう考えたのが始まりです」
「美の匠 ガラス工芸 弟子丸」の代表で、切子師を名乗る弟子丸 努さんは、自身が手掛けた作品を前にそう語る。弟子丸さんは、島津家が中心となって進められた薩摩切子復興事業に当初から関わり、薩摩切子が出来上がるまでのプロセスを当事者としてつぶさに見てきた。その貴重な体験を活かし、自らの技術を磨きながら、2011年に「美の匠 ガラス工芸 弟子丸」を立ち上げた。
黒い薩摩切子を弟子丸さんは「霧島切子」と命名した。工房の所在地が霧島であることもさることながら、黒という色が持つ深みは、神々が住まうといわれてきた聖なる山、霧島にも通じると考えたからだ。漆黒にも近い黒は、薩摩切子独特の重厚感と相まって、荘厳な趣を作品にもたらしている。
「霧島切子」と名付けられた、黒の薩摩切子。黒と透明ガラスのモノトーンの世界は、静謐にして荘厳。
「黒いガラスをカッティングするのは、高度な技術が求められます。なぜならば、黒色は光を通さないので、カットする際に刃がどの深さまで入っているか、目で見えないのです。カッティングの要は、どこまで彫り込むかをミリ単位で調節すること。刃が見えないので、手先の感覚で彫っていくしかありません」
試行錯誤して辿り着いた黒の薩摩切子は、弟子丸さんの代名詞ともなった。
悠久の歴史の重みを感じさせる黒と、どこまでも透明なクリスタル。そこに彫り込まれた弟子丸さんならではの独自のカッティング。しんと静まり返った、静謐という言葉が相応しい、気高さが薫る作品だ。また、「霧島切子」には、まったく色を被せず、無色透明なクルスタルの輝きと、そこに施された精緻なカッティングを味わう作品もある。
「霧島切子」には、無色透明なクリスタルに刻み込まれた高度なカッティングが生みだす、美しい文様を味わうシリーズもある。
もちろん、伝統的な「薩摩切子」も弟子丸さんは数多く手がける。修業時代に培ったオーソドックスなカッティングに、独自の技法を組み合わせることによって生まれた文様は、「薩摩切子」ならではの「ぼかし」によるグラデーションと相まって、独特の美しさを醸し出している。さらに、製作の過程で生じてしまうガラス廃材を利用し、ペンダントトップやさまざまなアクセサリーに再生した「eco KIRI」 や、カッティングを施したステンドグラスからの透過光を室内で味わう「fusion」など、弟子丸さんは、これまでの「薩摩切子」の概念にとらわれない、新たな試みに絶えず挑戦している。
右から、繁盛升・150,000円、ハイボールタンブラー彩雲・230,000円、天開タンブラー極黒・110,000円(いずれも税別)
彩も鮮やかな作品が並ぶショップ。さまざまなカッティング技法を見比べるのも楽しい。
体験工房でアクセサリーやグラスなどのカッティングに挑戦
弟子丸さんを中心とした「美の匠 ガラス工芸 弟子丸」のスタッフが手掛けた作品のショップが「ART DESHIMARU」である。店内は「霧島切子」をはじめ、「薩摩切子」「eco KIRI」など、さまざまな作品が並ぶ楽しいスペースとなっている。「ART DESHIMARU」では、カッティングの体験も行われている。作ることができるのは、アクセサリーからタンブラーまでさまざま。
グレーと赤とのコントラストが印象的な「ART DESHIMARU」のたたずまい。
瀟洒なショップには、「霧島切子」をはじめ、さまざまなラインの作品が並ぶ。
ショップに併設された体験工房では、所定の料金を払い、アクセサリーやタンブラーなど、さまざまなタイプの切子に挑戦することができる。
アクセサリーに挑戦してみた。コイン状のブルーのガラス片を両手で持ち、高速で回転するダイヤモンドホイールと呼ばれるカット工具に、恐る恐る押し当てる。ギーンという金属音とともに、削られた部分の奥にある透明ガラスが白いラインとなって現れる。縦横斜めと、均等の放射線を4本入れようとするも、線の長さや間隔が揃わず、無様な放射線となってしまった。削る深さが均一でないために、ラインそのものの幅も異なっている。
カッティングを実際に体験し、切子の製作がいかに高度な技術を必要とするか、改めて実感した。
「炉火純青」を座右の銘として
「中国には『炉火純青』という言葉があります。炉の炎が青くなった時にもっとも温度が高くなることから転じ、学問や技芸が最高の粋に達することを意味します。この言葉を常に心に抱き続け、新しい煌めきを生み出したいと思います」
切子師、弟子丸さんの切磋琢磨は今日も続く。
薩摩切子の製作に40年近く携わり続けてきた弟子丸さん。まさに切子師と呼ぶにふさわしい。
ART DESHIMARU
鹿児島県霧島市隼人町小浜1817⁻1⁻2
Tel:0995⁻73ー4747
営業時間:10時~18時
定休日:木曜日
豊かな自然と、そこで暮らす人々の知恵が結びついたとき、その土地にはさまざまな「宝」が生まれる。鹿児島県の各地で生まれ、光り輝く数々の「宝」。それらは今や、世界が注目する存在になりつつある。
そんな鹿児島の宝を巡る旅は、これからも続く。これまでの「南の宝箱 鹿児島を巡る旅」は以下から。
Photography by Azusa Todoroki(Bowpluskyoto)
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Premium X
鹿児島の「宝」を巡る旅
Premium X
関連記事
投稿 鹿児島が誇る工芸、薩摩切子を手掛ける二つの工房を訪ねて は Premium Japan に最初に表示されました。
Stories
Premium X
旅館の矜持 THE RYOKAN COLLECTIONの世界
2025.10.27
新潟「旅館ホテルryugon」井口智裕社長 日本の地方が生きる道を地域全体で実践!
レセプション前の和の空間と井口社長。建物は文政年代のもので、国の重要文化財に指定されている。大きな赤いソファは地域の雪をモチーフにしたもの。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「ザ・リョカンコレクション」に加盟する旅館の女将や支配人を紹介する連載「旅館の矜持」。今回は「ryugon(龍言)」の社長・井口智裕氏を紹介する。
その宿は上越新幹線の越後湯沢駅から車で30分、上越線の六日町駅からは車で4分ほどの距離にある。東京駅で新幹線に乗れば、たった2時間以内に到着できる。新潟県南魚沼市で異彩を放つ「旅館ホテルryugon(龍言)」は、幕末期の古民家を移築した木造建築の宿だ。
居心地の良い広大なラウンジに感嘆
外観は木造と白壁のコントラストが見事で、その美しさに目を奪われる。誰もが感嘆するのは、レセプション前から、何室にもわたって奥へ奥へと広がるラウンジだ。
「日本の旅館にこうしたラウンジはどこにもないですよね。だからこそ価値があると思って造りました。念頭にあったのは、特に海外のお客さんにくつろいでもらえることでした」
と語るのは「ryugon」の井口智裕社長である。
「旅慣れた外国のお客さんや日本の方が、ここで本を読んでくれていたりすると、狙いにハマってくれたと嬉しくなりますね」
囲炉裏ラウンジにて。秋から春までは火がともされる。丸いクッションも雪のイメージだ。
囲炉裏を囲む一画があり、バーカウンターがあり、趣味の良い本を揃えた図書室があったりする。しかも、アーティスティックな椅子もあれば、昔ながらの座椅子もあり、テーブルもソファも多種多様だ。中にはカップルが座るのに最適な、かまくら型のソファもある。
それでいて雑多な印象はない。窓から見える景色が変わるから、気分も変わる。実際に、夕食が済んだ後に、このラウンジでまったりと過ごす宿泊客が多いのは印象的だった。部屋に帰るよりも、居座りたくなるのだろう。
この部屋も文政年代のもの。しっとりと落ち着くラウンジだ。
重要なのは地域全体のボトムアップ
井口社長が街と宿の関係について語る。
「『ryugon』がある南魚沼市の六日町は、観光客が来るような街じゃありません。宿の外を散歩すれば綺麗な田んぼの風景があって農作業をしている人たちがいる。田舎の日常の暮らしが感じられる土地です。宿から街の中心部も近いので、地元の人が行く居酒屋でご飯を食べるとか、そういう楽しみ方もできます。一方で、坂戸山の裾野に宿はありますから、自然も充分に感じられます。ここは街と自然の両方が堪能できる絶妙な位置なんですね」
確かに、客室やラウンジなど宿の至るところで、山の緑が目前まで迫ってくる。
ヴィラへと続く雪国伝統の雁木(がんぎ)の廊下と池。画面奥の緑は、もう山の裾野だ。
社長は続ける。
「私が望むのは連泊してもらうことです。1泊では、とても地域の文化は分からないからです。この宿に滞在しながら、地域の文化や暮らしを楽しんで欲しいのです。地元の人と触れ合う、そうすることで初めて、文化としての重みを感じることができるのではないでしょうか。連泊すれば、今日の晩御飯は街で食べて、宿に帰ってきて、バーは12時までやっていますから、軽食を食べながら一杯やる。あるいは今日の夜は軽くそばでいいとか、カレーライスでいいとか、ビーフサンドにするとか。そのために館内フードメニューがあるんです。もちろん、ルームサービスでもご利用できます。
そんな風に宿を使ってもらいたいですね。宿はあくまでも街全体を楽しんでもらうための拠点基地にすぎません」
ちなみに、宿泊しなくともラウンジ利用と入浴ができるプランもある。なにしろ、思いつく限りのサービスが用意してある。
宿をリピートする3つの条件
思考はさらに深化してゆく。
「‶地元にいいお店があれば、宿の稼働率は上がる″というのが僕の‶思想″です。自分のところでも料理は頑張りますが、地元にいいレストランが増えることのほうが楽しい。宿を拠点にして2泊3泊したくなりますよね。
僕は世界中を旅行しているので、行きたくなる場所には必ずと言っていいほど‶必勝の法則″があります。
1に泊まりたくなるような宿があり、2に体験したくなるようなアクティビティがあって、最後はいい食文化があること。この3つが掛け算となって、魅力を生み出す。条件が1個でも欠けると、人はリピートしないんじゃないでしょうか」
「ryugon」が多彩なアクティビティを提案するのもそのためだ。恐るべき数のメニューがある。
山菜狩り・きのこ狩り、田んぼを自転車で走るポタリング、坂戸山トレッキング、まちぶらツアー、冬ならば雪かき体験や雪上のガストロノミーや雪原スノーピクニック、施設内なら土間クッキング、煎餅焼き体験、土鍋ごはんで作る絶品おにぎり体験……まだまだ続く。
ちなみに、10台ある電動アシスト自転車はBESV(ベスビー)という台湾製で、連続で90kmの走行が可能だそうだ。どこにでも行けちゃう。
軽トラックをレンタルして野山を走るプログラムもある。
「僕らがアメリカに行ったらピックアップトラックをレンタルして砂漠を走りたいとか、ハワイに行ったらオープンカーに乗りたいという発想と同じです。20代の女子が麦わら帽子をかぶって、軽トラで田んぼ道を運転したら、インスタ映えしませんか」
これはイケてるかも。
玄関前に立つ井口社長。木造と白壁のコントラストが美しい。
宿とは‶思想〟の集積である
井口氏がここに至るには、実は、積み重ねた思考の長い歴史があった。
宿の原型である「温泉旅館 龍言」は、1960年代に出来た。建物は幕末時代に建てられた地元六日町の豪農の館や武家屋敷を移築したものだ。大小16の家の集合体で、本館は重要文化財に指定されている。その経営が井口社長に譲渡されたことを機に、リニューアルが施され、現在の姿になった。それが2019年のことだ。
「私は17年前の2008年から『雪国観光圏』という活動してきました。課題は、地域固有の雪国文化をどうやって地域に根付かせるかでした。ですから、『龍言』をリニューアルする際に主眼を置いたのは、この地域の文化や暮らしを宿の中で表現することです。
日本の文化を体験しながら、ある程度は高品質な時間を過ごしつつ長期滞在できるということ。そのためには、ただ古い建物だけじゃダメですから、現代の快適性も入れ込みました。
目指したのは、フランス・ブルゴーニュ地方のワイナリーのシャトーに1週間連泊するような旅のリテラシーを持った人が、居心地が良いと感じられる宿です。宿というのは、一つ一つの思想の集積なんですね」
門を壊し、地域になじませる
「この土地に高級旅館を造ったという感覚はあまりありません。第一、旅館は門構えが立派で、そこから先は宿泊者しか入れないような‶結界″を感じさせますよね。だから、まず、その立派な門を壊して、名前も『龍言』から『ryugon』に変えました。そうすることで、格式を取っ払って、地域になじませたかったのです。
だから、ここはいわゆる高級旅館ではありません。旅館ホテルなのです」
門を入ってすぐ左手にあるryugon cafeの横で。中は土間スペースになっている。
門をくぐるとすぐ左手にカフェがあり、右手には地元の品々を揃えたかなり大きなセレクトショップを配したのも、人が敷居を越えやすくするためなのだろう。
「日本人は敷地内だけで完結するいい旅館を求めていますよね。だけど、海外から日本のローカルを味わいに来た人にとっては、別にとびきり高級な旅館である必要はありません。4スターぐらいでいいのです。彼らは旅のプロセスがどうあるかを優先させていますから」
そうは言っても、客室は居心地が抜群に良かった。部屋の価格はクラシックルームの2万円余から、新築したヴィラ・スイートの20万円と幅広いところから選択できる。
ヴィラ・スイートのテラスに備わった露天風呂。目の前に雪があったら最高だろう。
「雪国文化」とは何か
では、さきほどから出てくる「雪国文化」とは何なのか。
「雪国文化って言うと、古い建物だとか茅葺屋根とか藁細工とかを想起しやすいですよね。それだと過去の継承のままで終わってしまう。文化というのは、過去・現在・未来の文脈の中にあると思うのです。僕らは雪とともに生きてきたので、そこで育まれた暮らしの知恵みたいなものを、未来に向けて表現したい。例えば、赤い円形の大きなソファや囲炉裏の周囲にある丸いクッションは、この地域の湿度がある重たく丸い雪を表現しているものです。ライブラリーの横にあるソファも、かまくらのイメージです。それらはすべて特注の家具です」
いちばん奥にあるラウンジ「図書室」から眺める雪景色。
「雪国観光圏」構想とは何なのか?
「そもそもは新幹線が金沢まで延伸する2014年問題がやって来るということがきっかけでした。それまでは越後湯沢から金沢までは特急だったのですが、新幹線が金沢まで伸びたら、われわれのような途中の街はどうすればいいのか。それで、新潟や群馬などの7町村の有志が集まって雪国観光圏を作ったのです。要は、エリア全体で金沢に匹敵するようなブランドを創らなきゃいけないということでした。
その核心部分はやはり雪国文化なんですね。同じ新潟県からは『里山十帖』の岩佐社長、群馬県みなかみ村からは『仙寿庵』の久保社長なども参加しています。僕らは宿ですから、施設に雪国文化をいかに落とし込むかをずっと考えてきたわけです」
井口氏の雄弁さは17年間に及ぶ思考の帰結だ。
冬の稼働率は、何とほぼ100%!
従って、冬がいちばん分かりやすいのだそうだ。
「1階部分は完全に埋まってしまって2階まで雪が積もる。赤ワインを片手に雪を眺めながらボーッと過ごすのがいい。雪そのものに価値があるわけです。冬の稼働率はほぼ100%ですから、お客様も冬の良さを感じていらっしゃるんです。なんか居心地がいいんだよねーってことでしょうね」
ほかに、提案するものは?
「新潟と言いますと、米と酒のイメージしかないでしょう。スキーなら長野県のほうがいいよねと思われちゃうし。世界遺産があるわけでも、名所旧跡があるわけでもない。南魚沼は日本の地方のどこにでもあるような街なのです。そこで、地域の文化に根ざした格好をつけない丁寧な旅を提案したいのです。名物料理なんかないけれども、冬の料理には雪国文化が詰まっています」
しかし、食事も相当なものだ。「雪国ガストロノミー」なるフルコースは地域の食材に溢れていてとても良かった。
「もちろん、お客さんが求められるレベルのものはお出ししています。一年でメニューは5回変わりますが、3泊ぐらいでしたら、全部のメニューを替えられます。何ならビーガンやベジタリアン対応も100%できます。当日に言われても対応できます。メニュー開発はずっとやっていますから、ビーガンで3泊分も問題なく出せます」
コースの〆に出される炊き立ての魚沼産コシヒカリ塩沢地区限定一等米とけんちん汁。このご飯の甘さ、ねばり、粒立ち、その美味しさと言ったら経験したことがないほどだ。地方の野菜で作ったけんちん汁も凄まじく美味しい。
いちばん食べて欲しいものは、春先の山菜だそうだ。
「山菜の存在を、世界に向けて発信したいですね」
印象深かったのは、朝食のバイキングでご飯をよそってくれる地元のおばちゃんスタッフの言動だ。日本語をまったく解さない白人に向かって、「ご飯はどうする?」「もう少し入れるが?」「味噌汁はどお?」と普通に話しかけていた。こういう触れ合い方は、最高に素晴らしいと思う。
地域が持つ絶対的な価値に紐づいた宿
井口社長の発想は相当に珍しい。というか、宿を街との関係性の中で捉えているところがまったく斬新だ。
そもそも、どういう経歴の人なのか?
「もともとは越後湯沢駅前にある旅館『越後湯澤 HATAGO 井仙』の4代目です。地元の高校を卒業してアメリカの大学に留学しました。ワシントン州のスポケーンにあるイースタン・ワシントン大学の経営学部でマーケティングを専攻しました」
そのままMBAを取ろうと思ったが、社会経験がないことに気づき、実家に戻る。
「当時の実家は駅前の温泉旅館で『湯沢ビューホテル井仙』という名称でした。1泊1万円ぐらい。経営が大変だったので、立て直す必要があり、2005年に『越後湯澤 HATAGO 井仙』としてリニューアルオープンしました。
そんなことをしているうちに、湯沢という土地そのものをリブランドしなきゃダメだと思い始めた。湯沢はスキーと温泉というイメージが強すぎるから、スキー以外の時期は困ってしまう。そこで、17年前に雪国観光圏を自分で立ち上げて、取り組んできました。その経緯の中で、『ryugon』をリニューアルした話につながります」
井口社長はこう締めくくる。
「高級旅館だけだったらライバルはいくらでもいるし、お客さんにしてみれば、ウチじゃなくてもいい。ならば、雪国文化というブルーオーシャンで戦いたい。
旅館単体だったらすぐに負けちゃう。でも、地域というものは、他の地域が真似したくともできません。地域が持つ絶対的な価値に紐づいた宿を造れば、とても強固なものになります。この戦いを宿一軒だけで取り組むのならば勝負になりませんが、私たちは地域全体としてそれをやっているのです。他の旅館さんも関連する飲食店さんもそうです。
そこにこそ日本の地方の生きる道があると考えています」
井口智裕(いぐちともひろ)
1973年新潟県南魚沼郡湯沢町生まれ。Eastern Washington University経営学部マーケティング科卒業。旅館の4代目として家業を継ぎ、2005年「越後湯澤HATAGO井仙」をリニューアル。2008年に周辺7市町村で構成する「雪国観光圏」をプランナーとして立ち上げ、運営に尽力し、観光庁の観光産業検討会議の委員も務める。2013年一般社団法人雪国観光圏を設立し、代表理事に就任。観光品質基準、人材教育、CSR事業など広域観光圏事業を中核的に推進している。著書に『ユキマロゲ経営理論(2013年、柏艪舎)』。
構成/執筆:石橋俊澄 Toshizumi Ishibashi
「クレア・トラベラー」「クレア」の元編集長。現在、フリーのエディター兼ライターであり、Premium Japan編集部コントリビューティングエディターとして活動している。
photo by Toshiyuki Furuya
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Premium X
旅館の矜持 THE RYOKAN COLLECTION…
Premium X
関連記事
投稿 新潟「旅館ホテルryugon」井口智裕社長 日本の地方が生きる道を地域全体で実践! は Premium Japan に最初に表示されました。
Stories
Premium X
グルメ最前線 トップレストランを探訪する
2025.10.25
大阪・関西万博「EARTH MART」in「飛鳥Ⅱ」レポート 日本の新しい食を生み出す前例なき交差点
国内外から選ばれた「食の未来を輝かせる25人」。
大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」のフィナーレが、大阪港を出港するクルーズ船「飛鳥Ⅱ」内にて、開催された。
食に関わる200名が集結
総合プロデューサー小山薫堂のもと、食の未来を語り明かすべく、料理人、生産者、研究者、経営者、投資家、ジャーナリストなど200名が一堂に会した。
「そもそも大阪・関西万博『EARTH MART』の企画を始めたのは今から5年前、ただの埋立地だった会場予定地に立ちました」
小山は語る。
「そのフィナーレとして、食に関わる分野の異なる人々が、船の上で1泊2日を過ごします。この場所で、新たに出会い、未来に向かって新たな種を蒔く。そこにこそ最大の意義があります」
確かに、食を取り巻く異業種の人々がこれほど参集するのは、まさに空前の画期的な試みである。ちなみに、「飛鳥Ⅱ」は郵船クルーズによる貸し切り提供だ。
「食の未来を輝かせる25人」を選出
当イベントの目玉は3つ。1つ目が、「食の未来を輝かせる25人」を国内外から選出したことだ。
その一部を紹介すれば、「飯田商店」の飯田将太(神奈川県・湯河原町)、「リージョナルフィッシュ株式会社」の梅川忠典(京都市)、「タネト」店主の奥津爾(長崎県雲仙市)、「FARO」シェフパティシエの加藤峰子(東京・銀座)、「味の素株式会社 食品研究所」の川崎寛也(神奈川県川崎市)、「里山十帖」料理長の桑木野恵子(新潟県南魚沼市)、「MAZ」ヘッドシェフのサンティアゴ・フェルナンデス(東京・紀尾井町)、「北三陸ファクトリー」の下苧坪之典(岩手県・洋野町)、「サスエ前田魚店」の前田尚毅(静岡県焼津市)、「中央葡萄酒株式会社」の三澤彩奈(山梨県・勝沼町)、「ESqUISSE」のリオネル・ベカ(東京・銀座)……らである。
2つ目は、その25人が12組に分かれて、「食の未来会議」でトークセッションを行ったことだ。
RED U-35のシェフ6人と監修した落合シェフ(中央)。
RED U-35のグランプリシェフたちによる饗宴
そして最後に、2013年から開催している新時代の若き才能を発掘する日本最大級の料理人コンペティションである「RED U-35 (RYORININ‘s EMERGING DREAM U-35)」で、過去にグランプリを受賞した10名のうち6名が、200名の招待客にコースディナーを提供してくれたことである。
そのシェフたちを列挙すると、福岡市「Restaurant Sola」の吉武広樹、東京都「スーツァン レストラン 陳」の井上和豊、小松市「Auberge“eaufeu”」の糸井章太、山梨県「nôtori」の堀内浩平、京都市「日本料理 研野」の酒井研野、東京都「ESqUISSE」の山本結以の面々だ。
様式としてはフレンチ、日本、中国にまたがるシェフたちの料理を、1人1皿で合計7皿(山本がデザートも担当)の見事なコースに仕立てた。監修したのは「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」の落合務である。誰もが口々に歓びの声を上げた。
「スーツァン レストラン 陳」井上和豊による「発酵唐辛子と鮮魚の蒸しスープ」。
それに先んじたランチバイキングでは、ミシュラン2つ星の「ESqUISSE」リオネル・ベカの「見守る海 牡蠣水寒天ゼリー」、さらにはアジアベストパティシエで「FARO」の加藤峰子が金谷亘と共作した「薔薇と杏仁の錦玉羹」などが供されるという豪華さだった。
白熱のトークセッション
「食の未来会議」についてもう少し詳しく説明したい。先ほどの25名が、テーマを立てて基本的に1対1でトークセッションを行う。同じ時間帯に4つの分科会が同時進行しそれが3セットなので、梯子をすれば別だが、基本的には3つしか傍聴できないシステムだ。
どのセッションも魅力的で、選ぶのは困難だったが、筆者が参加したセッションはいずれも素晴らしかった。
「Oishii Farm」古賀大貴×「北三陸ファクトリー」の下苧坪之典のセッション。
そのうちから2つを紹介すると、まず、「Oishii Farm」古賀大貴×「北三陸ファクトリー」の下苧坪之典のセッションで、テーマは「日本発『食のGAFAM』は生まれるか」。古賀はニューヨーク近郊で日本のイチゴを工場生産している。
「ハチによる受粉がなければ不可能と言われた、イチゴ、トマトなどを新しい技術で作っています」(古賀)
空輸したイチゴを試食したが、実に甘く豊かに広がる味がした。未来においてはあらゆる作物が栽培可能になると予告する。どんな条件下でも無農薬で美味しい農産物が作れるから、食糧難を解決する革命的な植物工場と言える。
「ウニは海藻を食い尽くし、磯焼けを引き起こす海のギャングです。また、海産物には『2048年問題』というものがあって、海に対して何も施さなければ、その頃には、海産物が食べられなくなってしまうと予測されています。それを養殖の割合を増やすことで解決したい。ウニの再生養殖から始めてみようと考えました」(下苧坪)
寿司が食べられなくなる時代は確実にやって来る。それは、魚が卵を産み付ける海藻がなくなってしまうからだ。それを止めるための一つの方策が陸上での再生養殖の技術なのである。
「人々は野菜や肉には関心を示すが、海の危機に対してあまりに無関心であることが最大の問題です。現在日本の天然8割・養殖2割、この割合を変えていかなければなりません」
「味の素株式会社 食品研究所」川崎寛也×ジャーナリスト・仲山今日子のセッション。
フェラン・アドリアとの対峙
もう一つは、「味の素株式会社 食品研究所」川崎寛也×ジャーナリスト・仲山今日子で、テーマは「食は『消えるアート?』『再現可能なデザイン?』本物のおいしさを継承するために必要なこと」。
世界の料理を変えたスペイン「エル・ブジ」のフェラン・アドリアが日本料理について本を書いているという。セッションでは、日本料理の本質を知ってもらいたいと、彼のプロジェクトをサポートする仲山が、フェランを味の素の研究所に連れてきた際に、川崎に引き合わせたエピソードを披露した。
「フェランはとても影響のある人。ほんまに理解して日本料理のことを発信してもらわなあかん」
と川崎は思い、様々な質問に対して丁寧に答えるのだが、
「フェランの質問は、基本的に西洋社会のルールに当てはまるか、なんです。日本料理を本当の意味で理解しようとしているようには思えなかった。拙速に、『日本料理を確立したのは誰なのか?』とか『その文献はあるのか?』と矢継ぎ早に。日本料理は文章に残すものではなく、あえて技術は秘密にしておくことが重要だったので、明確に記述されたものはほぼないのです。彼らの概念ではなく、こっち側の論理で理解して欲しい」
川崎はそう語った。
仲山も、「明文化されていない文化は消えてしまう。日本料理を美意識や文化も含めて文字で残して行くべき」と持論を展開し、さらには会場の参加者も巻き込んだ議論にまで発展した。
ある意味、衝突とも見えた二人の激論は、本対談中の白眉だった。とはいえ、両者は共に最後の未来に残す言葉として、「日本料理の言語化されない部分に着目するべき」と総括した。
小山薫堂によれば、「衝突こそが新しい進歩を生む」のである。
中田英寿がオーガナイズした日本酒が振る舞われた。
平原綾香のパフォーマンス
また、最上階では、中田英寿がオーガナイザーとなり、秋田県の「新政」、三重県の「而今」、栃木県の「仙禽」、熊本県の「産土」、京都府の「日日」の各種日本酒が、ディナー前に振る舞われた。
アフターパーティでは、フルコースディナーで満腹状態の平原綾香がパワフルな歌声を夜のしじまに響かせた。
平原綾香の歌声が海上に響きわたった。
2日目、下船前の朝食もまた印象的なものだった。新米「晴天の霹靂」の白米に、目玉は、サスエ前田魚店の自家製イワシの干物と、里山十帖の桑木野による山菜汁が供された。フィナーレを締め括るに余りあるほど美味しい朝食だった。
このイベントが数年に一度は開催されることを切に願いたい。 (文中・敬称略)
Toshizumi Ishibashi
「クレア」「クレア・トラベラー」元編集長
Premium Japan Members へのご招待
最新情報をニュースレターでお知らせするほか、エクスクルーシブなイベントのご案内や、特別なプレゼント企画も予定しています。
Stories
Premium X
グルメ最前線 トップレストランを…
Premium X
関連記事
投稿 大阪・関西万博「EARTH MART」in「飛鳥Ⅱ」レポート 日本の新しい食を生み出す前例なき交差点 は Premium Japan に最初に表示されました。