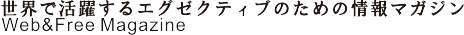人気記事
About&Contact
Style
Portraits
日本のエグゼクティブ・インタビュー
2025.7.7
パティシエ 鎧塚俊彦 唯一無二のお菓子への追求と共に、地方創生へ情熱を傾ける
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「Toshi Yoroizuka(トシ ヨロイヅカ)」のオーナーパティシエである鎧塚俊彦さんの人生は、常に挑戦の連続である。たとえ周囲の反対という逆風にさらされようとも、自らの信念を貫き、決して曲げない。その精神力、胆力はどこから湧き上がるのか―――。今回は、日本を代表するパティスリー「Toshi Yoroizuka」の誕生と、鎧塚さんが見据える未来へのビジョンを伺った。
パティシエという仕事が認知される前に、敢えて洋菓子の世界へ飛び込む
子どもの頃にテレビで見たフランス料理に心を奪われ、将来は料理人になることを夢見ていた鎧塚さん。しかし高校卒業後、一旦は別の仕事に就くものの、当時はまだ職業として認知されていなかったパティシエの道に自ら飛び込む選択をした。
「子どもの頃からお菓子が大好きだったこともありますが、当時はまだ洋菓子をつくる仕事は一般的ではなかったからなのかな」と語る。
「小さな頃からお菓子が好きだったこともありますが、まだあまり知られていない世界だったからこそ、逆に惹かれたのかもしれません」
日本で修行を経てヨーロッパへ渡り、スイス・オーストリア・フランス・ベルギーなどの
名店を渡り歩いた8年間。その中で得たことは洋菓子職人としての技術も当然あるが、それ以上にメンタルが鍛えられ、感謝の心を得る機会につながった。
「海外へ行けば見たことのない技術や素材があって、目から鱗が落ちる体験にあふれている、そういう時代は私たちの師匠の時代で終わっているんです。私が修業した時代には海外の技術や素材はすでに日本に入っていました。しかし、現地で言葉も通じず、コネもなく仕事を探し、住居を見つけ、食うにも困るような日々の中で、メンタルが強くなったと同時に、多くの人の優しさに触れる機会になりました」。
では、やはりいまの若者たちも海外修行をするべきなのかを聞いてみた。
一年中、忙しく日本中を走り回る鎧塚さんだが、時間があるときはカウンターに立ち、いまもデザートをサービスしていると言う。
海外で修業をすることはマストではない。すべては本人の志である。
「明確な目標や目的を持っているなら行けばいい。でもチャンスがあれば行きたい程度なら止めた方がいいと思います。だってパリのパティスリーからぜひうちに来てください、なんてお誘いはないですから」。
確かに、そんなドラマのような展開は早々ないだろう。
「実際のところ、日本と海外の洋菓子に関する技術の差はほとんどないと思います。むしろ衛生面などは日本の方が優れていますよ。もし日本でお店を持ちたいと思っているなら、日本でしっかりと基礎を学んで、お金を貯めて日本でお店を持てばいいんです。日本で何も見つけられないのに、海外へ行ったらなら何かが見つかるかなと考えているのなら、海外に行く必要なんてありません」と話す一方、海外でお菓子屋さんをずっとやっていこうという気持ちがあるのなら、一刻も早く行くべきだとも語る。
日本を代表するパティシエは、直感を信じて突き進んでいく
鎧塚さんは、様々な修業期間を経て、2004年、東京・恵比寿に6席だけのカウンターデザート専門店「Toshi Yoroizuka」を開店。店名は“即決”だったと聞き、驚いた。
「店を始める際、お世話になった人に店名を相談したら『名前なんて何でもいい。どんなにかっこ悪い名前でも、自分がかっこ良ければ、その名前もかっこ良くなる。逆に、どんなにかっこいい名前でも、お前がかっこ悪ければ、その名前もかっこ悪くなる』と言われて、なるほど、それならなんでもいいや!と思って決めました」。
これは店名だけではなく、お店のロゴも同じ。当時、パソコンが使えなかった鎧塚さんに代わって作業した人がパパっと作った案がそのまま採用になったとか。
しかし「Toshi Yoroizuka」の白と黒を使ったお店のロゴマークには周囲からの相当な反対に合った。
「日本では白と黒は喪の色。洋菓子はおめでたい時にいただくものですから、絶対にやめた方がいいと何人にも反対されました」。しかし鎧塚さんはブレずに自分の思いを貫く。
6席のカウンターデザートの店にこだわったのも同じ。
「周囲からは『失敗する典型』だと言われました(笑)客単価が低くて、回転率も悪いから絶対儲からないよ!と」。
カウンターデザートをやりたいと考えるパティシエは多い。だが、採算が取れないからあきらめる人がほとんど。しかしこの時の鎧塚さんの挑戦は、連日長蛇の列を生んだ。
「実際、いまだに儲かっていません(笑)。でも、でもカウンターデザートは私の顔であり、ポリシーですから、これからもやめるつもりはありません」。
鎧塚さんにとって、お店の収益よりも、表現のほうが勝るのだ。
恵比寿の「Toshi Yoroizuka」一号店。当時の写真。
「決断にいいも悪いもない。何かを決断したとき、選択しなかった要素をすべて頭の中から消し去って、選んだ道を信じて努力することが大切なんです。もし失敗した場合は、自身の決断が間違っていたのではなく、その後の努力が足りなかったのだと思います」。
自分のスタイルを貫くことで、周りからの評価が変わっていく
常に業界の最前線に立つ鎧塚さん。トップを走り続けるためには、いつも新しいお菓子を生み出さねばならない使命感やプレッシャーがあるのでは?──そう尋ねると、不思議そうな表情でこちらを見る。
「数年前にピスタチオのブームがありましたが、私は20年前からピスタチオのクレームブリュレを作っています。ブームと呼ばれるのはちょっと不愉快ですね。なぜならブームは終わるものだから。でも美味しいは時代を超えるんです」
本当に美味しいものは、姿が変わっても根底は変わらない。洋菓子の道を切り開いてきた鎧塚さんよりも前の世代、諸先輩たちの作るお菓子や、昔ながらのケーキ屋さんの定番ケーキは今でも変わらず美味しいのだ。
「私が20年間全く変えずに作っているお菓子も、やっぱり変わらず美味しいと自負しています。それが『Toshi Yoroizuka』のスフレです。最初は“これ、焼けてないんじゃない?”と言われたこともありましたが、今ではあのスフレが食べたいと日本中からお客様がお越しになります。ブームなんてものに振り回されずに、自分のスタイルを貫くことが大切だと思っています」。
洋菓子は進化していると感じていたが、それは見た目や素材などのことであって、美味しいという感性は確かに変わらない。ブレずに、独自のスタイルを貫く。やがてそれが定番になり、そしてブランドとして確立されていくのだ。
Toshi Yoroizuka 東京は、一階がショップ、二階がサロン(要予約)となっている。
追い続ける7つの夢。その一つである第一次産業と地方の活性化を成し遂げる
鎧塚さんは新しいことへの挑戦もいとわない。2010年エクアドルに『ToshiYoroizuka Cacao Farm』開設。2011年には小田原石垣山山頂に約2000坪の農園を併設したパティスリー&レストラン『一夜城Yoroizuka Farm』をオープンさせた。
これらの活動の根底には鎧塚さんの7つの夢があると言う。それが何であるかは教えてはもらえなかったが、その一つに地方の農園や農家の方々と交流を深め、地方の活性化を目指すこと。
「農業は人間が生きていく上での根幹。そこを大切にしていかないと、これから先どうなってしまうのか心配です。AIなどの新しい技術にばかり注目が集まり、農業や漁業などを軽視するような風潮には強い憤りを覚えます。第一次産業に携わる人々をもっとリスペクトしていきたいではありませんか」と鎧塚さんは語気を強める。
常に言葉を選びながらも、自身の夢や熱い思いはあふれ出てくる。
現在、地方活性のために、6つの県の顧問やアドバイザーしたり、地方へ足しげく通って農業の方々と交流を深め、共に協力をして課題解決に努めている。
「農家の方々を支援すると言っても、お互いにとってWin-Winの関係でなければダメ。ボランティアということではなく、お互いにメリットがある関係性でなければ意味はないと考えています。我々は規格外の農産物を安く仕入れさせていただき、美味しい洋菓子をつくり、その果物や野菜の魅力を広めていくことで農家や県へ貢献していきます」。
昨今、お米問題などから、第一次産業への関心は高まってはいるが、都心に暮らしていると見えてこない部分は多くある。鎧塚さんは現地へ出向いて農家と交流し、そこで見聞きした課題を体感して課題と向き合っている。そしてそこから洋菓子業界の未来や地方創生へ自身の発想で挑んでいるのだ。
地方から日本へ、日本からアジアへ。お菓子作りを通してできること
地方創生の取り組みと共に、鎧塚さんの目はさらにアジアへと広がっているようだ。
「さまざまな課題は日本だけではなく、アジアにおいても同じです。アジアが一つになることで得られること、乗り越えられるものがあるのではないかと思っています。これはあくまでもお菓子作りを通してですが、アジアの平和に貢献したいという想いを常に抱いています。国家という隔たりを無くして、共に手を携えていくことで、平和な世の中へとつながっていけたらいいじゃないですか」。
いままで走り続けているけれど、年齢的にそろそろ新たな働き方を考える時かなとも語る。
この何事へも意欲的に取り組む姿は、やはりあっぱれである。しかし鎧塚さんは有名になればなるほど、批判的な言葉も耳にする機会は増えているとも話す。
「私は敢えてSNSなどでの発信の機会を増やすように努力しているのですが、同時に発信した言葉の意味が正しく伝わず、自分の意図と違う書かれ方をメディアにされることもあります。なぜそうなるのかな?そんな気持ちはありますが、これからも自分の言いたいことは言い続け、自分が信じた道を進むという姿勢は変えずにいこうと思っています」。
鎧塚さんの活動の根底にあるものは、ただ美味しいお菓子を提供し、そして少しでも多くの方々へ幸せを届けることなのである。
カウンターデザートがいただける「Toshi Yoroizuka」東京の2階サロンで。
鎧塚 俊彦 Toshihiko Yoroizuka
1965年、京都府宇治市生まれ。関西のホテルで修業後、渡欧。スイス、オーストリア、フランス、ベルギーで8年間修業を積む。ヨーロッパで日本人初の三ツ星レストランシェフパティシエを務めた後、帰国。2004年、恵比寿に6席のカウンターデザートを提供する「Toshi Yoroizuka」をオープン。その後、六本木にライヴ感覚を重視した14席のカウンターデザート「Toshi Yoroizuka MIDTOWN」、杉並区の八幡山駅近くに「Atelier Yoroizuka」開設。また、世界初となる、畑からの一貫した自社生産のショコラ作りを目指し、南米エクアドルにカカオ農園「Yoroizuka Farm Ecuador」を設けた。長年の夢を実現し、2011年には小田原石垣山山頂に2000坪以上の農園を併設したレストラン&パティスリー「一夜城 Yoroizuka Farm」、2012年には地方の農家の方々との連携を目指した「Yoroizuka Farm TOKYO」を渋谷ヒカリエにオープン。スイーツを通して、農業と地方の活性化に尽力している。また、2014年よりロカボ(低糖質)スイーツを専門にした、Toshi Healthy Sweetsを展開している。
島村美緒 Mio Shimamura
Premium Japan代表・発行人兼編集長。外資系広告代理店を経て、米ウォルト・ディズニーやハリー・ウィンストン、 ティファニー&Co.などのトップブランドにてマーケティング/PR の責任者を歴任。2013年株式会社ルッソを設立。様々なトップブランドのPRを手がける。実家が茶道や着付けなど、日本文化を教える環境にあったことから、 2017年にプレミアムジャパンの事業権を獲得し、2018年株式会社プレミアムジャパンを設立。
Photography by Toshiyuki Furuya
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 パティシエ 鎧塚俊彦 唯一無二のお菓子への追求と共に、地方創生へ情熱を傾ける は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
「ル・ショコラ・アラン・デュカス」7月限定のサントノレ
2025.7.10
フランスの伝統菓子を再構築「サントノレ・ショコラ」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
フランス・パリ発のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」が、7月31日(木)まで開催される「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク 2025」に参加。今年のテーマ「サントノレ」にちなんだ新作が、東京・日本橋のデザートサロン「ル・サロン」にて期間限定で販売中だ。
“サントノレ”は、パン職人とパティシエの守護聖人「サントノレ(聖オノレ)」に由来する伝統菓子。本国フランスで永く愛される華やかで芸術的なデザートを、ル・ショコラ・アラン・デュカス流に再構築したのが、7月末まで味わえる「サントノレ・ショコラ」だ。
サントノレ・ショコラ 1,980円
ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京⼯房 ル・サロン限定(提供期間:2025年7月1日~7月31日)
ベースとなるのは、六角形のショコラ風味のパイ生地。その上に、薄いキャラメリゼを施した小さなショコラシューを並べ、カカオ分75%のショコラクリームと、軽やかなバニラクリームをトッピング。中央と外周のシューには濃厚なショコラクリームが詰められ、香ばしく焼き上げたショコラ風味のシュー生地と、口溶けのよいクリームが織りなす調和が楽しめる。
サクサクとした食感とビターなショコラの深み、そしてエレガントなビジュアル――伝統と革新が交差するル・ショコラ・<wbr />アラン・デュカスならではのサントノレを、この機会に楽しんでみては。
◆ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京⼯房 ル・サロン
【住所】東京都中央区日本橋本町1-1-1
【TEL】03 5614 5313
【営業時間】11:00 – 18:00 (LO17:30)
※金曜・土曜のみ 11:00 – 19:00 (LO18:30)
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 フランスの伝統菓子を再構築「サントノレ・ショコラ」 は Premium Japan に最初に表示されました。
昨春からラグジュアリー客船のチャーターを開始したジャパネット。2025年は北欧スタイルの「バイキング・エデン」を全船チャーター、2026年春には同船で3航海を実施します。ジャパネットならではの船旅の魅力を専門家が解説! ※画像:村田和子撮影
2025~2026年に日本発着を実施する北欧スタイルの客船「バイキング・エデン」。北欧のナチュラルな空間美で食やアートを満喫でき、日本語OKで快適に船旅が楽しめると評判です。 18歳以上限定の大人の船旅をレポートします。※画像:村田和子撮影
Features
青森で、涼を感じる夏のひとときを
2025.7.9
⻘森屋 by 星野リゾートで開催。「しがっこ金魚まつり」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
青森の文化を満喫できる温泉宿「⻘森屋 by 星野リゾート」では、300個以上の金魚ねぷたが彩る夏の恒例イベント「しがっこ金魚まつり」が、8月31日(日)まで開催中だ。
⻘森の夏祭りの時期に街中で飾られる金魚型の灯篭「金魚ねぷた」をテーマにしたこのお祭り。「しがっこ」とは、青森の方言で「氷」のことで、その名の通り、暑い夏に涼を感じられる体験が楽しめる。
「巨大金魚鉢」イメージ 無料(終日開催)
今年の注目は、高さ2メートルのフォトスポット「巨大金魚鉢」。青森の伝統工芸「津軽びいどろ」を用いたステンドグラス風の金魚ねぷたが泳ぐ金魚鉢に入ると、まるで水中にいるような映える写真を撮影できる。
「貸し金魚ねぷた風鈴」イメージ 無料(時間 15:00〜20:00)
また今年は、金魚ねぷたと風鈴を組み合わせた「貸し金魚ねぷた風鈴」も登場。卓上タイプは客室の装飾として、提灯タイプを散策のお供に。夕涼みのひとときが、より心地よく感じられるはずだ。
「金魚ねぷたりんご飴」イメージ 1個770円(時間 15:00〜18:00 提供数 1日30個)
「ポイみくじ」イメージ 1本 550円(15:00〜20:00)
「金魚ねぷた灯篭回廊」イメージ
このほかにも、金魚ねぷたをかたどった「金魚ねぷたかき氷」や、りんごの酸味と甘味を楽しめる「金魚ねぷたりんご飴」、金魚すくいをするような感覚でおみじく体験ができる「ポイみくじ」、300個以上の金魚ねぷたが並ぶ「金魚ねぷた灯篭回廊」など、夏祭り気分を楽しめるスイーツや演出も充実している。
露天風呂「浮湯」
金魚ねぷたはその昔、津軽藩の藩士のみが飼うことができた希少な金魚「津軽錦(つがるにしき)」に人々が憧れ、作ったものとされ、今なお青森の夏の風物詩として親しまれている。
早くも厳しい暑さが続いている今シーズン。「⻘森屋 by 星野リゾート」が提案する涼体験楽しんでみては。
◆⻘森屋 by 星野リゾート
【所在地】青森県三沢市字古間木山56
【TEL】050-3134-8094(星野リゾート予約センター)
【料金】1泊23,000円~(2名1室利用時1名あたり、税込、夕朝食付)
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.7.9
高輪「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN」サントリー「ROKU〈六〉」ブランドを深く知り愉しむ
関連記事
投稿 ⻘森屋 by 星野リゾートで開催。「しがっこ金魚まつり」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Stories
Premium X
日本のプレミアムなホテル
2025.6.30
「軽井沢・森四季」VILLA森の静寂に佇む、一棟貸しの別荘ホテルで豊穣な時間を
「緑~MIDORI」広い庭から建物を見る。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
四季が美しく移ろう軽井沢の地に「軽井沢・森四季」VILLAはある。星野温泉まで1㎞の徒歩圏内という利便性が高い環境ながら、喧騒から遠く離れた自然に囲まれた森の私邸とも呼べる空間である。敷地内には四棟のヴィラがあり、すべてが一棟貸しとなっている。ここは旅館でもホテルでもない、滞在者のためだけの特別な空間なのだ。
自然に囲まれた環境の中で、周囲を気にすることなくゆっくりと自分たちの時間を過ごしたい人には最高の環境である。
広い庭やデッキのある四棟のヴィラでは、周囲を気にせずくつろげる
「軽井沢・森四季」VILLAが何よりも大切にしているのは、「四季とともに生きる」という思想。宿泊棟は4棟あり、それぞれの棟には「緑~MIDORI~」「光~HIKARI~」「風~KAZE~」「時~TOKI~」という名前がつけられ、春の息吹、夏の風、秋の実り、冬の静謐を体現している。
「風~KAZE」木々に囲まれた静かな空間。
広い庭には露天風呂がある。
「緑~MIDORI~」は、家族や友人との滞在に理想的な3ベッドルームある空間。50坪を超える庭と24坪のウッドデッキがあり、室内にはデンマーク製薪ストーブがあるなど、まさに軽井沢の緑や風を心行くまで体感できる。
「光~HIKARI~」は三角屋根が特徴的で、プライベートな苔庭でBBQやたき火、北欧露天薪風呂、ハンモックなどがある。宿泊者だけのプライベートな時間を過ごすことができる。
「風」は、高級北欧ヴィンテージの家具、北欧露天風呂を備えた2名向けの静謐な棟。苔庭に面したバスタブに身を沈めるひとときは贅沢な時間が過ごせるはずだ。
2024年8月オープンした「時~TOKI~」は、3ベッドルームあり、さらにウッドデッキには足湯が備えられており、心の緊張をゆっくりと解いていく空間になっている。
冬は暖炉で火の揺らめきを楽しむことができる。
各棟には広いデッキがあり、食事をしたり、読書をしたり、それぞれの楽しみ方で。
「時~TOKI~」のテラスには足湯がある。
全棟にはBang & Olufsenのオーディオ、LE LABOのアメニティなど、上質な調度品や環境が揃っているので、自然の中でも、自宅にいるような快適さが整っている。もちろんペットの滞在もOKなのが嬉しい。
さらに24時間バトラーサービスがあるので、守られた環境での滞在が約束されている。
地元の旬の食材を自然の中で味わう贅沢、レストラン&バー「HONO」
滞在中は、各棟でBBQを楽しむこともできるが、敷地内にはレストラン棟「HONO」もある。まるで森の中に浮かぶような設計になっているダイニングは、信州の豊かな旬の恵みを活かした炭火グリル料理が堪能できる。
希少な赤身肉や和牛、豚リブを、キロ単位で豪快にワイルドな炭火<wbr />焼きするスタイルは、日本のレストランではなかなか味わえない迫力とジューシーさを、大自然の中で体験できる。
「HONO」からはVILLAを見る。
炭火で焼くことで、肉の旨味が存分に楽しめる。
またワインも充実しており、ナチュールからグランヴァンまで幅広く揃えるほか、地元のクラフトジンや日本酒とのペアリングも楽しめる。バータイムには、焚き火の炎を眺めながらグラスを傾けるゲストも多く、静けさの中で記憶に残る一夜が過ごせることだろう。
森を楽しむ滞在が豊かさの本質を教えてくれる
このヴィラでは“ただ泊まる”のではなく、“森に滞在する”ことができるのが大きな魅力である。朝は小鳥のさえずりで目覚め、昼は木漏れ日の下でゆるりとした時間を過ごし、夜は星を眺めながら焚き火を囲む。都会では味わえない時間や空気感に包まれ、自分自身や大切な人としっかり向き合うこともできるだろう。何もしない時間、心から安らぐ空間は、別荘ではなく、ホテルでもない場所だからこそ実現する贅沢。季節の移ろいを五感で楽しみながら、自然の恵みに抱かれる滞在はまさに非日常。
美しい軽井沢の四季に寄り添いながら、自分自身に戻る旅に相応しい宿が「軽井沢・森四季」VILLAである。本物の豊かさを知る大人たちにこそ、おすすめしたい私だけの“森の私邸”と呼べる空間だ。
Text by Yuko Taniguchi
長野県北佐久郡軽井沢町長倉2147-118
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Premium X
日本のプレミアムなホテル
【管理栄養士が解説】「間食=太る」と思われがちですが、選び方やとり方によってはダイエットや健康につながることもあります。今回は、間食で避けたい食品の特徴と、間食を上手に活用するためのポイントをご紹介します。
【管理栄養士が解説】「間食=太る」と思われがちですが、選び方やとり方によってはダイエットや健康につながることもあります。今回は、間食で避けたい食品の特徴と、間食を上手に活用するためのポイントをご紹介します。
Stories
Japan Premium
星のやに泊まる、星のやを知る
2025.7.1
「星のや富士」宿泊記 その3 雨を五感で楽しむ非日常体験「梅雨グランピング」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「非日常」をテーマに、各施設それぞれが独自のホスピタリティでゲストを迎える「星のや」。そのホスピタリティのひとつが、ゲストが参加する多彩なプログラムです。土地の文化や伝統をベースにして作り込まれた各プログラムは、「星のや」の新たな魅力となっています。
「星のや富士」宿泊記の第3回では、季節の恵みや魅力を楽しむグランピング企画「梅雨グランピング」をご紹介します。雨の森だからこそ感じる音や色、香りなど、雨が作り出す自然の美しさを五感を通じて体験できるプログラムです。この企画開発に携わった「星のや富士」のスタッフによる開発秘話をご紹介します。
日本初のグランピングリゾート「星のや富士」で非日常体験
昨今すっかり定着した感の「グランピング」。日本に広まったきっかけとなったと言われるのが、「星のや」の4施設目「星のや富士」の誕生でした。河口湖を見下ろす広大な敷地には、アカマツをはじめとする針葉樹を中心とした木々で構成した森が広がり、その中にキャビンと呼ばれる客室やダイニング、クラウドテラスがあり、まさに自然を体感できる空間とともに遊び心と発見の多いアクティビティが人気の施設であり、目前には富士山という好立地を求めて、世界中から多くの観光客が訪れています。
レセプションで受付を済ませたら、車を乗り換えて、ホテルへ。
6月10日から7月20日までの期間、雨の森を楽しむ、新しい発想のグランピング「梅雨グランピング」がスタートしました。
雨の中でグランピング? どんな楽しい提案があるのか、その企画をご紹介していきます。
雨の中で体験する、香り、音、雨音のリズムで心が解き放たれていく
新緑が芽生える梅雨の時季には、雨が葉に当たる音や湿った土の匂い、霧に包まれた森や山の景色などの非日常を五感で楽しむのが「梅雨グランピング」です。梅雨限定のスイーツやカクテルのほか、五感で楽しむ「雨の森のディスカバーウォーク」や、梅雨の期間のみ登場する「雨音カウンターテーブル」、さらに「絵はがきづくり」など、雨を存分に楽しむ仕掛けについて、この企画の担当をした「星のや富士」の広報であり、グランピングマスターの北垣沙野さんにお話を伺いました。
自然の中で育ったと語る北垣さんですが、ここの自然は別格だと語ります。
「『星のや富士』は森の中の施設ですので、季節の移ろいを五感で楽しんでいただくことができるのが自慢のホテルです。グランピングというと、晴れの日の楽しみと思っていらっしゃる方も少なくないと思いますが、ここでは雨の日には雨がつくり出す美しさを体験いただきたいと思っております。お部屋にポンチョと長靴を用意していますので、ぜひ外に出かけていただき、雨の森を体感いただきたいと思います」。
敷地最上位にあるクラウドテラス。焚き火やライブラリーカフェがあります。
階段状のクラウドテラスでは、お気に入りの場所を見つけてゆっくりくつろぐことができます。
特に梅雨の頃の森は、芽吹いて間もない葉が優しく輝き、そこに降る雨の粒はより緑を引き立て、また土の香りや雨音が私たちの心をゆっくりと解きほぐしていくと言います。
「『星のや富士』に配属になって6年経ちます。ここに来る前は、雨だとちょっとイヤだな~と思うこともありましたが、雨の美しさ、雨の日にだけ見える神秘があることを知って、この五感を満たす自然の神秘を皆さまにも体験いただきたいと強く思うようになりました。この体験が今回の企画を考えるきっかけです」。
梅雨限定の特別シート「雨音カウンターテーブル」で絶景を楽しむ
まずご紹介するのが、「梅雨グランピング」の期間だけクラウドテラスに登場する「雨音カウンターテーブル」です。一見、テラスに無作為に置かれているように見えるカウンターテーブルは、北垣さんが選んだ絶景ポイントなのだとか。さらにカウンターテーブルの屋根には美しい布が張られており、その雨音が自然に織りなうリズム「1/fのゆらぎ」を感じることができると教えてくれました。
。
「カウンターテーブルは、椅子に座った時に景色がどう見えるのかを考えて、設置場所を微調整しながら決めました。そしてカウンターテーブルのルーフに張られた青色の織物は、隣接する富士吉田市の名産地である富士山麓の織物を使用しています」。
古くから機織りの名産地であった富士吉田市は、発色のよさや高密度の技法などが特長の富士山麓の織物をセレクト。かつては着物の裏地に使われていたが、現在はネクタイや洋服の裏地、傘などに使われています。今回は傘に使用される織物を使用していることから、雨に強く、さらに雨音が心地よく響くと言います。さらに青色は、梅雨の頃の緑との相性を考えてセレクトしたと語ってくれました。
こだわり抜いた「雨音カウンターテーブル」について語ってくれる北垣さん。
緑に馴染んだ青のルーフ。
雨雲やバブルの先にある幻想的な世界観のスイーツとカクテル
また、梅雨限定のスイーツやカクテルが登場します。
「季節によってテーマが変わる『森のひととき』と名付けられたスイーツ。梅雨限定の『雨の森のひととき』は、より雨を楽しんでいただけるサプライズを仕込みました。チーズケーキの上に乗った綿あめを雨雲に見立て、ご自身で雨が降るようにブルーキュラソーをかけていただきます。すると綿あめが解けて、中から色鮮やかなフルーツとチーズケーキが現れるスイーツです。甘さと酸味が調和する優しい味わいに仕上げています」。
「雨の森のひととき」は14時30分~17時30分、無料でいただくことができます。
さらに梅雨限定のカクテルにもちょっとした驚きの仕掛けがあります。
「この時期に楽しめるアジサイをテーマに、梅のシロップやベリーの香りを閉じ込めたオリジナルカクテルです。カクテルの上には霧をイメージしたバブルを乗せ、そのバブルがはじけると、霧が晴れるようにベリーの華やかな香りに包まれます」。
雨の日には思いがけない発見がある、そんなメッセージが込められているスイーツとカクテルは思わず笑みがこぼれることでしょう。
球体のバブルが風に揺れ、いつはじけるかドキドキしてきます。
低アルコールの軽い飲み口のカクテル。19時~22時(21時30分ラストオーダー)2,180円(税・サービス込)
グランピングマスターから学ぶ、森の楽しみ方の見つけ方
今回ぜひ体験いただきたいのが、『雨の森ディスカバーウォーク』です。雨降る中、ポンチョと長靴を身に着けて、グランピングマスターと共に森の散策に出かけます。枝や葉が自然に落ちた地面は、まるでふわふわの絨毯の様で、空を見上げれば高く伸びた木々の中から雨粒がゆっくりと落ち、雨に濡れた木々はより深い色となり、どこからか香ばしいような香りが立ち込めます。グランピングマスターによる木々の種類のお話や、季節による森の移り変わり、足元に落ちている松ぼっくりが雨に濡れるとしぼみ、乾くと開く、そんな話を聞きながら、自然の不思議と共に、私たちはこの自然に生かされているのだという敬意の感情も芽生えていきます。
「都会では感じることがない体験が森には多くあります。お子さんだけではなく、大人の方にもぜひ体験いただきたいと思います。お客さまの中には木々に詳しい方もいて、私たちが教えていただくこともたくさんあります」と北垣さん。
雨に濡れるのが不思議と心地よくなってきます。
また、「梅雨グランピング」の時季にはクラウドテラスや散策路に、雨粒が当たると音を奏でる「レインドラム(タングドラム)を設置します。
「個人的には水琴窟をやりたいと思っていたのですが、大きな岩をクラウドテラスに設置するのは難しいので、気軽に楽しめる手のひらサイズのレインドラムを用意して雨音の演奏を楽しんでいただきたいと思っています」。
雨粒が当たることで音が鳴る「レインドラム(タングドラム)。
他にも毎朝体験できる「薫る森の蒸留」体験では、旬の果実である梅を地元の桃農園さんにご協力いただき、梅を蒸留した香りを楽しめたり、雨でにじむ水彩色鉛筆を使った自分だけ「絵はがきづくり」体験も楽しだり、雨の日だからといって部屋に閉じこもることなく楽しめる企画がたくさん用意されています。
「『絵はがきづくり』はここの風景を描いたスケッチに色鉛筆で色を塗っていただき、その後、雨に濡らしていただくと水彩画のような仕上がりが楽しめるものです。スケッチからご自身で描きたい方には真っ白な紙をお渡ししています。雨の日はいつも以上に五感が冴えてくるものです。ご自身の感性でアートに取り組む時間を楽しんでいただくご提案もしています」。
「絵はがきづくり」7時半~19時 無料。
忙しい日々の中では、雨を鬱陶しいと感じることは多くありますが、「星のや富士」に滞在していると、静寂の中に響く雨音や雨でより強くなる木々や土の香り、そのすべてが心地よく、そして心の疲れを洗い流し、パワーチャージがされていくような感覚に包まれます。雨もいいものだな、そんな感情に包まれた滞在でした。
◆星のや富士「梅雨グランピング」
・開催日:2025年6月10日~7月20日
・対象 :宿泊者(雨音BARのアルコールカクテルの提供は、20歳以上の宿泊者限定)
・予約 :不要
◆丘陵のグランピング「星のや富士」とは
河口湖を望む丘陵に建つ、日本初のグランピングリゾートと呼ばれる「星のや富士」。広大なアカマツの森の中で愉しめる体験型の食事や、焚き火を眺めながら過ごすひと時が過ごせます。全40室のキャビン(客室)はテラスにソファや焚き火台があり、室内でもアウトドア気分が味わえます。また全室にグランピングマスターがつき、滞在をサポートしてくれますので、最高の時間と体験が約束されています。
Text by Yuko Taniguchi
Photography by Natsuko Okada(Studio Mug )
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Japan Premium
星のやに泊まる、星のやを知る
Japan Premium
関連記事
投稿 「星のや富士」宿泊記 その3 雨を五感で楽しむ非日常体験「梅雨グランピング」 は Premium Japan に最初に表示されました。
紫外線が気になる季節。十分な対策を行い、エイジングの進行を食い止めたいところです。とはいえ、ただ日焼け止めを塗ればいいわけではありません。今回は、今さら聞けない「日焼け止めの正しい塗り方」と塗り直しについて解説します。
Stories
Premium X
旅館の矜持 THE RYOKAN COLLECTIONの世界
2025.6.30
心躍る和モダン空間に満ちる、アートと極上のホスピタリティ。地域文化の魅力認知に本気で取り組む「花紫」山田耕平社長
新緑が映える1階の「モダンスイート」は川の水面にいちばん近い。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「ザ・リョカンコレクション」に加盟する旅館の女将や支配人を紹介する連載「旅館の矜持」。今回は石川県加賀市・山中温泉の「花紫」の社長・山田耕平氏を紹介する。
山中温泉は石川県で有数の温泉郷である。今から1300年前に、大僧正の行基が山中温泉の源泉を発見したと伝えられている。老舗の旅館だった「花紫」が「凄いことになっているゾ」と言われはじめたのは、2024年頃のこと。若き当主の山田耕平社長による大胆な改修が話題に上るようになり、そのウワサは東京まで届いていた。
旅館「花紫」の屋号は、地域の美しさを讃える言葉「山紫水明」に由来している。白地に二重の円のシンボルが描かれた大きな暖簾をくぐり、館内に入る。まず印象的だったのは、若いスタッフたちの笑顔と爽やかな挨拶だった。
さて、こんなに気持ち良くさせてくれる笑顔を振りまくホテル・旅館は、日本ではめったにお目にかかれない。一瞬、バリ島やプーケットにある上質なリゾートホテルにでも来たかのような錯覚にとらわれた。人が旅館に対して抱く一般的なイメージは一新されるだろう。ここは、社長ご夫妻をはじめ、若い人たちが中心となって動かしている旅館なのだ。出迎えてくれた山田社長に改修・改革の核心について話を聞いた。
旅館業を通してお客様に伝えたいこと
「きっかけになったのはコロナ禍のときの休業です。それまでは日々の仕事に忙殺されてじっくりと考えるのがちょっと難しかった。休業したことによって、宿泊業のあり方とか、旅行ってなんだろうとか、日ごろからモヤモヤと胸に滞留していた疑問について、立ち止まって考えられたことが大きいです。その意味では、休業はコロナ禍がもたらした僥倖だったのかもしれません。
コロナ禍が明けてもこの先そのまま同じように営業を続けるのかと自問したときに、自分には旅館業を通して伝えたいことがあるはずだと思ったのです。自分が思い描く旅館のイメージもありました。それで、改修に着手してみようと決意しました。」
大きな窓から陽が射し込んで、開放感が抜群のロビー。<wbr />宿泊客でなくとも喫茶の利用ができる。
「自分が思い描く旅館の新しいビジョンと切り離すことはできないのですが、何よりも先に前提にしたいことがありました。それは、どのようにしたら、お客様がより満足していただけるような旅館に変えていけるかです。言い換えれば、お客様が当館に来てくださって、温泉に浸かって食べてお休みになられる、それ以外のことで何かできないか。滞在される間に感じることができる『価値』みたいなものを創造できたらいいなと思ったのです。いや、是が非でも、新しい価値を創出したかったのです。
それ以前はサービス業として、お客様に尽くして尽くしまくって、疲弊してしまうような感じでした。もちろん、そうしたエネルギーの使い方もあるのですが、目指すところはそうではないのではないか。よその旅館にはない『価値』を味わい楽しんでいただく。お客様に対してその提案ができるようになれば、自ずと旅館自体の存在価値も上がっていくはずだというふうに考え至ったのです」
日本文化の地域の拠点の一つになる
「その価値のポイントとなるのは、日本の文化を古いままではなくて、現代の形に変えて伝えていくことです。宿泊体験を通して、日本やこの土地の良いものや文化を感じていただける、そういう場所を目指していきたいと考えていました。具体的に言えば、古くからある部分では、新しい食事の提案であったり、新しいお風呂の楽しみ方ですね。新たに生み出す部分では、当館が北陸の工芸やアート、そしてお茶を含めた食文化の一つの拠点となることです。
言い換えますと、食や飲み物にテロワール(その土地ならではの風土や個性)を感じることはよくあります。『花紫』ではそれだけにとどまりません。器や空間、温泉、そしてアートにいたるまで、すべてがこの土地の魅力を伝えるための『テロワール』となっているのです。
工芸やアートに関して言えば、館内で展示することはもちろん、石川県内、北陸の作家さんを中心にして、土地の作家さんと触れ合えるところまで体験できる旅館を目指そうと考えました。その土地の風土で生まれた作品に囲まれて過ごしたり、さらには、希望があれば、作家さんの工房までお連れしてしまうという構想です。地域全体の魅力を感じていただくのが旅館の役目だと私は思っています。また、都会にはない、それだけの魅力がこの土地にはあるのです。」
暖簾は「山紫水明」を象徴的に表したエンブレムを中央に描いた。
「石川・北陸には様々な分野で作家さんがたくさんいるのですが、それは加賀の前田家から連なる文化的な継承であることを実感しますね。前田さんは本当にエラい人でした(笑)。工芸やアート以外の分野では、例えば、野菜の生産者さんであったり、見事なブリを用意してくれる神経締めの達人の漁師さんであったり、美味しいお米やお茶を作っている農家の方だったりです。そうした土地の魅力を総体として、五感全体で感じていただくための装置、それが旅館だと思っています。実際に、そうした土地の魅力のすべてを集めてきて活用できるのが旅館という存在なのではないでしょうか」
突撃スタイル(⁉)が信条
作家とのネットワークはどのように作るのか?
「基本的には突撃スタイルですね(笑)。展示会を見に行ったり、インターネットやSNSを駆使して、この人に会ってみたいという作家さんを発掘します。あとのコンタクトは主として突撃です。どうやっても辿り着けない場合には、紹介してもらうこともあります。
作家さんは人によっては人前に出ることを好まない方もいらっしゃ<wbr />るので、私どもが、<wbr />そういう作家さんとお客様の間で翻訳者的な立ち位置になれればい<wbr />いと考えています。価値を伝えるのが苦手な方ならば、私どもが媒介者になって価値を伝えられたらいいですね。それで例えば、漆芸の作家さんにアートパネルなどを作ってもらって、展示販売したりしています。生活に近い工芸的な作品から現代アートまで、実験的なことも含めて、幅広く魅力を伝えていければと思っています。
ちなみに現在、館内で見られる作品の作家さんは、写真家の河野幸人さん、仏師の長谷川琢士さん、現代アートのLAKAさん、ガラス工芸の佐々木類さん、漆芸の村田佳彦さん、陶芸の中嶋寿子さん、漆芸の鵜飼康平さんなど北陸を拠点とするアーティストの作品です。昨年はロビーフロア全体を使って作家さんと学芸員の方に対談してもらって、作品発表の場を設けたりしました。この空間をもっと使って欲しいのです。これに関してはどんどん発展しているかもしれません。どこまで行くのか、自分でも興味深く見つめています(笑)」
渋いオーラを放つ茶房。ここで専門的な訓練を受けたスタッフが、<wbr />本格的にお茶を淹れてくれる。ここかしこに作家の作品が置いてある。
ロビーの売りは、渋いオーラを放つ「茶房」
すべてのゲストは4階に当たるロビー階に到着する。すぐに気づくのは、随所に様々な作家のアートや工芸が設置してあることだ。フロントを通り過ぎた先が素晴らしい。ゆったりしたラウンジには大きな窓が一面に並び、渓谷に沿って、対岸でまばゆいほどに緑を放つ新緑が目に飛び込んでくる。このラウンジに隣接するのが「茶房」で、ちょっとした陰翳の中にあって、加賀杉のカウンターが伸びている。全体が落ち着いていて渋いオーラを放っている。
アフタヌーンティーは予約制で(6000円)、<wbr />宿泊客でなくても味わえる。お茶はもちろん茶房で淹れたものだ。
「実は、コロナ前の改装する際のぼんやりとしたイメージでは、ゲストが自由に紅茶やコーヒーを楽しめるセルフサービスのラウンジを想定していました。人を減らして生産性を上げていこうみたいな流れですね。しかし、考えているうちから、これは違うんじゃないかと思っていました。人の手をかけずにオートマティックな流れなわけですが、これを旅館でやる意味はどこにあるんだという疑問を抱くようになりました。
効率化した先には何もないなとも思いました。切り詰めて行って利益を出す、そういう考え方もあるのですが、利益が出たところで、自分たちもお客様も満たされないのならば、やるだけ無意味です。とすると、日本の文化を伝えていくとなれば、やっぱり日本の美意識すべてが詰まっているお茶だよねということになったのです。
それでロビー階の改修に際して造ったのが茶房でした。厳選されたお茶を人の手で丁寧に淹れることによって、お客様も集まってきて、その価値を感じてくれる。差別化できるポイントとはそういうことかなと思って、そちらに振り切ってみました。ですから、きっぱりとコーヒーを出すのはやめました(笑)。特に海外のゲストの方はコーヒーを好まれますが、お部屋で淹れてもらっています」
茶房のお茶は、このように10数種類あって、プレゼンを受けた後にゲストがチョイスする。目の前で繊細に淹れてくれる。
茶房チームは東京で研修
とは言え、それで出来上がった茶房なるものは、洗練の度合いが桁違いだ。
「修練を受けた専門のスタッフが、煎茶、加賀棒茶、抹茶、和紅茶などの10数種類のお茶、お茶のカクテルである茶酒などを、作家さんと私で共作しました特別な茶器、例えば九谷焼や珠洲焼、漆器、ガラスなどお茶に合わせた茶器でお出しします」
筆者は煎茶好きなのだが、三煎味わったお茶の味わいにはまさに格別なものがあった。
先代が20年前に作った見事なダイニング。今や世界的な和紙作家である堀木エリ子氏の作品を大胆に配した。先代のアートを見る目も確かなものだったことがわかる。右は奥様の山田真名美さん。
当館の企画・広報を担当する奥様の山田真名美さんが付け加える。
「新しく茶房チームに入ると、東京での研修がありますので、実際にお茶を習って帰ってきます。そのあとは季節ごとに東京から来てもらっています。そのたびにテストがあって、改善点を直していきます。ただお茶を淹れるだけでは意味がありません。そのお茶に価値があるぐらいのレベルにしなければと考えています。
インスタグラムなどでこの茶房があることを知って、今では茶房に入りたくて入社する社員もいるほどです。大体は県内ですが、県外からも応募があります。旅館で働きたいけれども、同時にスキルを身につけたい若い人には、一石二鳥なのでしょうね」
ご主人が続ける。
「年に何回かお茶会を開催しておりまして、展示している作家さんの器を使ってお茶を体験していただくこともやっています。今、茶房チームのトップは、茶房ができる前の時代からいる社員です。以前は私と一緒にコーヒーをポッターに入れて注ぎまくっていました。それが今やいちばん上に立ってお茶の指導をしています。彼女にとってもスキルアップできているので、仕事の付加価値を感じてくれているのではないかと思います。サービス業でもそういうことがないと今の若い社員たちは続きません」
1階の「モダンスイート」にて。渓谷沿いの新緑がダイレクトにまぶしい。部屋のミニマルなデザインが心地よい。
新しいコンセプトを詰める
先代が造り上げた「花紫」は、見事な数寄屋造りの旅館ではあったが……。
「小さい頃から数寄屋造りを見すぎてしまったせいか、何も感じなくなっていまして、むしろ根本的に変えたいとずっと以前から考えていました。しかし、大学生の時にサンフランシスコに2年ほど留学しまして、日本を外側から見たら、すごく美しいものがたくさんあることに気づいたのです。と同時に、それはそのままでは現代の人には伝わらないなとも思いました。
それからですね、どうすれば伝わるのかの模索を始めたのは。様々な宿に出かけたり、また日本のデザインをいろいろと調べるうちに、SIMPLICITYの緒方慎一郎さんに行きついたのです」
デザイナーの緒方慎一郎氏は、建築、インテリア、プロダクト、グラフィック等のデザインやディレクションで知られる。自身のお店である「Ogata Paris」、「Aesop」の店舗や5スターホテルの空間デザインなどを手掛けた。
「緒方さんは技法的には伝統的なものを使われるのですが、アウトプットされたデザインはとても現代的です。そこがすごくシックリきました。今回、当館のリニューアルを進めるに当たっては、普通はいきなりデザインから入る事務所が多いと思うのですが、緒方さんはコンセプトデザインから一緒に考えてくださったので、本当に良かったです。私のイメージを緒方さんにお伝えし、緒方さんからも沢山の提案を頂戴しました。本当に、詰めに詰めた結果がいまある姿になったのです」
以前の数寄屋造りからすると、完全な変貌を遂げた。4階のロビー階で、山田氏が考えた画期的なことがほかにもある。
「一般に旅館というのは、宿泊者しか施設には入って来ないのが当り前です。とても閉鎖的なのです。それを宿泊者じゃない方たちにも開放できないものかというのが、私の長年の課題でした。そこで、ロビー階にラウンジを作って、朝の9時から夕方の5時半まで、茶房を使った喫茶ができるようにしました。予約制でアフタヌーンティーもありますし、夏に向かってはカキ氷などのご用意もあります。地元の方たちにも気軽に使ってもらいたいのです」
ホテルのロビーじゃないのに、従来の旅館にしてみれば、まさに驚くべき発想だ。これも彼の思考が〝お客様ファースト〟に向かっているからこそ生まれてくるアイデアなのだろう。
ゲストルームの秀逸な和モダン
双子のお風呂には衝撃を受けた。ガラス窓の手前は内風呂、向こうがは外風呂で半露天になっている。その発想が凄い。
実は、4階のロビー階から順次下って3階から1階の客室も見事な和モダンに生まれ変わった。例えば1階のモダンスイートのお風呂のデザイン性には目を瞠(みは)った。ガラスの窓を境にして内風呂と外風呂の湯舟が双子のように、内と外に配置されている。もちろん、外風呂は半露天なのだ。しかも、サウナルームに水風呂まで完備しているというオマケ付きである。寝具にも自信があるという。
「金沢の布団屋さんでISHITAYAのものです。特に羽毛が相当な品質で、極薄なのにとても暖かいです」
確かに掛けていることを忘れるぐらいに軽く、存分な保温性がある。マットレスが硬いのも好みで、きわめて快適な寝心地だった。
懐石料理である夕食はそれぞれが素晴らしい。そのうちの一品「とらふぐの白子蒸し」は、白子の濃厚さが背徳的なほどに味蕾をかき乱し、長く記憶に残った。器は同年代の作家、吉田太郎氏との共作で花紫オリジナルのもの。
もちろん、食は夜も朝も素晴らしい。
夜は料理長の中村雅和氏の手による本格的な懐石である。地野菜、地元のお造り、蛤、海苔、能登牛に特別栽培のこしひかり……。石川県の海と山の恵みをふんだんに使った、どれもが味わい深い品々に感嘆の声をあげたくなる。能登鮪のお造りだって、醤油で食すのではない。上に載せられたのは海苔の佃煮だ。新しい食べ方である。ほかにも、とらふぐの白子蒸し、地蛤の飯蒸し、能登牛のローストが印象深かった。日本酒好きにとっては、あの中田英寿氏も一推しの地元・松浦酒造「獅子の里」や、白山の吉田酒造店「手取川」などの銘酒もズラリ。ついつい飲み過ぎてしまう。
「にほんの朝ごはん」は、一品一品に魂が宿る。七輪で焼くノドグロや蛍烏賊は干物だけに旨味が深く、出汁巻きたまごのジューシーな味の濃さに目が覚める。特筆すべきは地元のこしひかりの美味しさだ。4種の漬物や海苔の佃煮に至るまで吟味されているからたまらない。ご飯のお代わりは必至である。
朝食はおかずの一つ一つに心がこもっている。蛍烏賊やノドグロの干物を目の前の七輪で燻すのも格別で、漬物や海苔の佃煮に至るまで美味しい。特別栽培の白米と浅利椀が秀逸だった。
冒頭の若いスタッフたちの話に戻す。
「いまスタッフは半分以上が20代で、平均年齢は32歳です。最近は新卒採用にすごく力を入れてやっていますので、全国から入社志望者がやってきます。サービス業は大変で、特に旅館はそうしたイメージがあると思いますが、水曜と木曜を休館にして、働きやすい環境作りにも取り組んでいます。英語研修や茶道、華道、ソムリエによるドリンクの研修など、専門知識が養えますから、スキルアップも望めます。こういうところなら働いてみたいなと思ってもらえたら嬉しいですね」
実は、山田社長の〝野望〟は留まることを知らない。
「具体的にはまだ言えないのですが、昔からやりたかった新たなプロジェクトを考えています。発表までもう少々お待ちください」
山田 耕平 KOHEI YAMADA
石川県加賀市山中温泉にある老舗旅館「花紫」六代目当主。<wbr />2021年に創業120年を超える花紫を継承した。<wbr />10代の頃からストリートアートに傾倒し、Academy of Art University(サンフランシスコ)に進学、<wbr />アートとフォトグラフィーを学ぶ。帰国後はその感性を活かし、<wbr />2022年より花紫のリニューアルプロジェクトを始動。<wbr />館内には現代アートや工藝を展示し、<wbr />地元の若手作家を支援するギャラリーや、<wbr />日本文化に触れられる茶房を設けるなど、「<wbr />現代における日本の文化サロン」<wbr />をコンセプトとした空間やコミュニティを創出している。<wbr />豊かな自然と暮らしとものづくりが交差する山中温泉に可能性を見<wbr />出し、唯一無二の滞在体験を目指し、<wbr />新たな魅力を発信し続けている。
構成/執筆:石橋俊澄 Toshizumi Ishibashi
「クレア・トラベラー」「クレア」の元編集長。現在、フリーのエディター兼ライターであり、Premium Japan編集部コントリビューティングエディターとして活動している。
photo by Toshiyuki Furuya
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Premium X
旅館の矜持 THE RYOKAN COLLECTION…
Premium X
関連記事
投稿 心躍る和モダン空間に満ちる、アートと極上のホスピタリティ。地域文化の魅力認知に本気で取り組む「花紫」山田耕平社長 は Premium Japan に最初に表示されました。
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
2025.6.28
伊勢神宮 式年遷宮に向けて 御神木は木曽から伊勢へ
外宮の陸曳の様子。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
令和15年(2033)に第63回式年遷宮が行われる伊勢の神宮。その壮大な準備が、令和7年(2025)5月2日の山口祭から始まったのは、この連載の第4回でご紹介したとおり。その山口祭から約1ヶ月、今度は新たな御正殿、つまり新宮を造営するための御用材を伐り出す「御杣始祭(みそまはじめさい)」が、長野県木曽郡上松(あげまつ)町の木曽谷国有林内で6月3日に執り行われた 。
祭場に立つ2本の大木は、樹齢およそ300年。これらは式年遷宮で用いられる特別な御用木(ごりょうぼく)の中でも、御神体を納める「御器(みうつわ)」となる最も重要な「御樋代木(みひしろぎ)」として選ばれた 。今回は、木曽の山中で育まれた大木が「御樋代木」として神宮へ迎えられる過程を通し、日本人が木という生命といかに向き合ってきたか、その精神と祈りを紐解く。
御用材を木曽で伐り始めるおまつり「御杣始祭」
「御杣始祭」は、御杣山(みそまやま)に坐す大神などに、これから御料木を伐り出すことを告げまつり、お供え物を捧げて新宮造営の安全を祈る祭儀。古くは、御料木を実際に伐り出す杣夫(そまふ)と呼ばれる人々が、御料木の根元に榊と御幣を立ててしめ縄を張り、御神酒を捧げて執り行っていたという。
内宮の「御樋代木」となる御料木。樹齢約300年で、直径は64㎝、樹高26mの大木。「太一(たいいつ)」は、天照大御神の御料であることを示している。
御杣始祭には、神宮祭主の黒田清子さんをはじめ、神宮大宮司、少宮司も参列。祭中、大宮司が御料木の前に進み出て、2礼2拍手1礼の参拝を行った。
祭儀は、内宮、外宮それぞれの御料木に対して行われ、常の通り、粛々と厳かに進められる。祭中には、神宮祭主の黒田清子さんが、御料木に向かって拝礼。祭儀の後は、「三ッ緒伐り(「三ッ紐伐り」とも言う)」と呼ばれる伝統技法によって、2本の御料木がともに伐り出された。
ちなみに「御杣山(みそまやま)」とは、式年遷宮のための御用材を伐り出す山を指し、遷宮が始まった持統天皇の時代から、神宮の背後にそびえる神路山(かみじやま)と高倉山が御杣山とされてきた。現在も式年遷宮の最初のおまつりで、山の口に坐す大神に対して行われる山口祭が、内宮は神路山のふもと、外宮は高倉山のふもとで行われるのは、その伝統を受け継いでいるからだ。
しかし、時代とともに良材を伐り出すことが困難になり、他の地にも御杣山が求められるようになった。ちなみに、他の地の御杣山の選定は、「御治定(ごじじょう)」、つまり、天皇陛下のお定めによって行われる。平安時代の中期以降さまざまな変遷を辿った御杣山が、現在の長野県、岐阜県の両県にまたがる木曽山に定められたのは、江戸時代からのこと。以後300年ほどは、木曽山中から御用材が伐り出され、今回の遷宮でも、「御治定」により、長野県の木曽谷国有林と岐阜県の裏木曽国有林から伐り出されることになったのだ。
樹齢約300年、高さ約26mの2本のヒノキを伐り出す
「三ッ緒(紐)伐り」を行うのは、内宮の御料木は「三ッ紐伐り保存会」のメンバー、外宮は神宮式年遷宮造営庁の職員の、それぞれ7人。作業を始めるにあたっては、まず内宮の御料木の総指揮を執る杣頭(そまがしら)が、斧(よき)の背の部分で、軽く3回ほど、御料木を叩くならわしになっている。
御杣始祭は、内宮、外宮それぞれの御料木の前で行われる。時折、お供えされた白い鶏(「生調(いきみつぎ)」と呼ばれ、祭儀がお供えされた後で生かされる)の鳴く声が、山に響き渡った。
「これは木にいる鳥などの生き物に対し、『申し訳ないけど、これからうるさくするよ』という心遣いです。もし何か生き物がいたら、どこかへ行ってくれますから」
そう話すのは、杣夫の1人で、前回の式年遷宮でも「三ッ緒(紐)伐り」を行った倉本豊さん。現在70歳の倉本さんは、木曽の御嶽山(おんたけさん)の強力(ごうりき=登拝者の荷物を持ち、地形や天気などを考慮した道案内や、御嶽山内の全山小屋と関わりを持つ総合職)を50年近く務める、まさにお山とともに生きてきた人だ。「三ッ緒(紐)伐り」を行うにあたっては、道具となる斧の手入れや、食事の節制など体調管理に心を配り、当日は身を清めて臨むという。なにせ斧を振り回す作業である。「怪我なく無事に」が、何より求められるのだ。
「三ッ緒(紐)伐り」は、木曽地方で古くから用いられてきた、斧のみで木を伐採する方法。並び立つ2本の御料木は、最終的に、それぞれがたすきがけのように交差して寝かさなければならない(杣夫は御料木を「倒す」と言わず、「寝かす」と表現する)ため、まず寝かせる方向を杣頭が確認。その後3点の「弦(つる)」、つまり、伐り残す部分を決めて、その弦だけを残すように、木の外側の3方向から中心に向かって斧を入れ、幹に空洞を作っていく。
貴重な御神木の伐り出しに立ち会う場に響く声
ちなみに、「御杣始祭」の当日は雨。降りしきる雨音に混じって、斧が木に当たる重く湿った音が聞こえてくる。何より鮮烈だったのは、ふとした瞬間に立ち上ってくる、清涼感あふれる檜の香り。
7人の杣夫が交代で、3人がかりで3方向から斧を入れ、幹に空洞を作っていく。
御料木が倒れる瞬間に出す音を、杣夫たちは「木がなく」と表現する。「鳴く」、「啼く」など、人によってさまざま解釈が違うようだ。こちらは6月5日に裏木曽国有林で行われた「裏木曽御用材伐採式」の様子。
やがて、1時間ほど経ったろうか。杣夫たちが作業を止めて傍に控え、入れ替わるように杣頭が1人御料木の前に進み出て、山に語りかけるように声を上げた。
「大山の神〜、左斧(ひだりよき) 横山(よこやま)1本 寝〜るぞ〜」
続いて、杣頭が3本の弦のうち、御料木を寝かす方向とは反対側にある弦を、力強く斧で叩いた。さらに、その動作を何度か続けた後、今度は木を見上げながら再び声を上げる。
「いよいよ寝〜るぞ〜」
なおも杣頭が斧を入れ、御料木がぐらっと動いたその瞬間、2人の杣夫が、見計らっていたように残りの弦を手早く斧で叩き始めた。すると……。
ギィーッ
鈍い音を立てて御料木がゆっくりと傾いていき、大きな振動とともに大地に横たわった。
続けて外宮の御料木である。
やがて、すべての作業を終えた杣夫たちは、先端が重なるように横たわった2本の御料木の前で1列に並び、深々と一礼。
御料木を無事寝かせた後、杣夫全員が1列に並び、御料木に向かって深々と1礼。
杣夫の経験を通し、「数百年も生きてきた木の生命をいただく、そのありがたみを強く感じるようになった」という倉本さんの言葉は、杣夫全員の想いでもあるのだろう。
美しい木曽ヒノキの再生と成長を祈る「鳥総立(とぶさたて)」
「三ッ緒(紐)伐り」はこれで終わりではない。最後に「鳥総立(とぶさたて)」が行われる。
『万葉集』にもみられるこの「鳥総立(とぶさたて)」は、伐り倒された木の先端の梢を根株に刺し、山の神から樹木の幹をいただくことに感謝を捧げる儀式。古来、木曽や飛騨地方だけでなく、東北などの各地で行われていたという。加えて、この儀式には、梢と根株を山の神にお返しし、樹木の再生を願う祈りも込められている。
樹木への感謝と再生を願う「鳥総立」。杣夫の間では「株祭(かぶまつり)」と呼んでいるという。裏木曽御用材伐採式で。
内宮、外宮の2本の御料木は、たすぎがけのように交差するよう寝かされる。こちらも「裏木曽御用材伐採式」の様子。
「またここに生命が宿って、立派な木になりますようにという願いです」と倉本さん。その言葉に続けた「鳥総立」についての説明は、この儀式が決して形だけではないことを実感させてくれるものだった。
根株に刺した梢は、正確に言えば、そのまま成長するわけではない。だが、御料木に斧を入れる際は、根株の中心に「酒1枡分」ほどが入る窪みができるよう意識しているという。もともと斧は平行に振れず、根株の窪みも自ずとできる。だが、「酒1枡分」を意識して作ることで、その窪みに雨水が溜まり、やがて苔むして、周囲の木から落ちた種を育てる、育苗の場所になるという。その種子は、根株の養分を吸収して徐々に根を伸ばし、その根がしっかり張ったところで、根株は土に還る。そんなふうに、木の生命は繋がっているのだ。
「木は伐って終わりではなく、ちゃんと管理して誘導していけば、また育ちます。そういうサイクルの中で、木も人間も生きているのだと思います」
木曽の街中での御木曳き行事の後、木曽川から伊勢へ奉搬
こうして伐り出された御料木は、その日のうちに、両先端を16面の「菊の御紋」の形に削る「化粧がけ」が施され、「御祝木(おいわいぎ)」、「御神木」として、沿道各地で丁重におまつりされながら、数日かけて伊勢へと奉搬される。
伐採された御料木に「化粧がけ」を施す杣夫。
御杣始祭の翌日に、長野県上松町で行われた御神木祭の様子。
岐阜県中津川市にある護山(もりやま)神社での御神木祭を終え、奉搬される御神木。荷台には榊8本を立て、紅白の幕としめ縄を四方に張り巡らせる。木曽谷からは長野県、岐阜県、愛知県を経て、裏木曽は岐阜県内を巡って三重県へ。
地域によっては、地元の人々が「御神木」を奉曳。なかでも長野県上松町では、御木曳車(おきひきぐるま)に「御神木」を載せ、多くの人々が木曽の木遣唄(きやりうた)とともに町中を練り歩いた。
「木曽の深山で育てたる 日の本一のこの檜、伊勢の社に納めます」。
誇らしくも一抹の寂しさを感じさせる木遣唄の歌詞や曲調は、まるで大事な娘を名家に嫁がせる親心を表現したよう。
伊勢へと向かう道中は、木曽の山中で育った大木が、「御神木」となって沿道各地の人々に奉迎、またおまつりされ、それによって神聖さを増していく時間のようにも思われた。
長い旅の最終地、内宮、外宮の両宮域にお運びする際は、内宮は御木曳橇(おきひきぞり)に載せて五十鈴川を「川曳(かわびき)」で、外宮は御木曳車に載せて「陸曳(おかびき)」で曳き入れられる。神職など多くの奉仕員が出迎えるなか、御榊(みさかき)と御塩(みしお)でお祓いを受け、清浄さが保たれるよう細やかな心配りがなされた御料木は、「御樋代木」という新たな役目を得て、その生命を繋いでいくのだ。
内宮で御樋代木を出迎える神職など奉仕員。数の多さからも、御樋代木の重要性がうかがえる。
五十鈴川での川曳を終え、内宮の五丈殿前に曳き入れられた御樋代木。御榊(みさかき)と御塩(みしお)でお祓いを受け、その後、清筵(きよむしろ)、清薦(きよこも)で丁重に包まれ、数日間五丈殿内に安置される。
1本の御料木が、多くの人々の手を経て、御神体をお納めする「御樋代」となる。その過程には、数百年を生きた生命に対する、人々の礼を尽くす姿があった。
Text by Misa Horiuchi
伊勢神宮
皇大神宮(内宮)
三重県伊勢市宇治館町1
豊受大神宮(外宮)
三重県伊勢市豊川町279
文・堀内みさ
文筆家
クラシック音楽の取材でヨーロッパに行った際、日本についていろいろ質問され、<wbr />ほとんど答えられなかった体験が発端となり、日本の音楽、文化、祈りの姿などの取材を開始。<wbr />今年で16年目に突入。著書に『おとなの奈良 心を澄ます旅』『おとなの奈良 絶景を旅する』(ともに淡交社)『カムイの世界』(新潮社)など。
写真・堀内昭彦
写真家
現在、神宮を中心に日本の祈りをテーマに撮影。写真集「アイヌの祈り」(求龍堂)「ブラームス音楽の森へ」(世界文化社)等がある。バッハとエバンス、そして聖なる山をこよなく愛する写真家でもある。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
Premium Calendar
関連記事
投稿 伊勢神宮 式年遷宮に向けて 御神木は木曽から伊勢へ は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
将軍の側に仕えた女性たちの、知られざる暮らしに迫る
2025.6.30
特別展「江戸☆大奥」。東京国立博物館で開催
『千代田の大奥』より「千代田大奥 御花見」 楊洲周延筆 明治27年(1894)東京国立博物館蔵
※会期中、展示替えがあり
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
将軍の身の回りを支えた女性たちが暮らした“奥”の世界を、貴重な史料や美術品を通して紹介する特別展「江戸☆大奥」が、東京国立博物館 平成館にて開催される。会期は7月19日(土)から9月21日(日)まで。
竹菱葵紋散蒔絵婚礼調度 鶴樹院(豊姫)所用 文化13年(1816) 東京国立博物館蔵
※通期展示
重要文化財 振袖 黒綸子地梅樹竹模様 桂昌院(お玉の方)所用 江戸時代 17世紀 東京・護国寺(文京区)蔵
※前期展示(7/19〜8/17)
江戸幕府の隠された歴史ともいえる、大奥。会場では、この閉ざされた世界での生活がわかる絵画や、将軍の妻妾たちが身につけていた衣装、婚礼調度品、生活用品や遊び道具などを展示。政治や武家社会とも密接に関わっていた大奥の役割や、そこでの暮らしぶりを重層的に紐解いていく。
『千代田の大奥』より「千代田の大奥 お櫛あげ」 楊洲周延筆 明治27年(1894) 東京国立博物館蔵
※会期中、展示替えがあり
『千代田の大奥』より「千代田の大奥 滝見のお茶や」 楊洲周延筆 明治28年(1895) 東京国立博物館蔵
※会期中、展示替えがあり
見どころのひとつが、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した絵師・楊洲周延が、大奥の様子を懐古的に描き人気を博した『千代田の大奥』の全場面一挙公開(※会期中、展示替えあり)。期間中、全40場面を見られる、またとない機会となっている。
重要文化財 刺繡掛袱紗 浅葱繻子地杜若と撫子に酒器「長生」字模様 瑞春院(お伝の方)所用 江戸時代 17~18世紀 奈良・興福院(奈良市)蔵
※前期展示(7/19〜8/17)
春日局像 伝狩野探幽筆 江戸時代 17世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵
※通期展示
さらに、五代将軍徳川綱吉が側室である瑞春院(お伝の方)にあてて送ったとされる、重要文化財 奈良・ 興福院の刺繡掛袱紗全31枚も公開。元禄期における最高の刺繡技術を用いて制作された逸品から、当時の高い染織技術と美的感覚を感じ取ることができるはずだ。また、大奥の構造や女中たちの生涯にもフォーカスしている。
徳川種姫婚礼行列図巻 上巻 (部分) 山本養和筆 江戸時代 18~19世紀 東京国立博物館蔵
通期展示 ※会期中、場面替えがあり
展示には、NHKドラマ10「大奥」で用いられた衣装を展示し、ドラマなどでおなじみの「御鈴廊下」のセットを再現するなど、視覚的にもわかりやすい構成に。ドラマや映画の世界と実際の大奥ではどのような違いがあるのか、比較しながら鑑賞するのも面白そうだ。
奥奉公出世双六 万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館蔵
※前期展示(7/19〜8/17)
大奥という特殊な空間の成り立ちや、その中で生きた人々の姿を丁寧に掘り下げる特別展。華やかなる世界に、足を踏み入れてみてはいかがだろうか。
特別展「江戸☆大奥」
【会期】2025年7月19日(土)~9月21日(日)
【休館日】月曜日、7月22日(火)
※ただし、7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)は開館
【開館時間】9:30~17:00
※毎週金曜・土曜、7月20日(日)、8月10日(日)、9月14日(日)は20時まで。
※入館は閉館の30分前まで
【会場】東京国立博物館 平成館
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.6.30
高輪「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN」サントリー「ROKU〈六〉」ブランドを深く知り愉しむ
関連記事
投稿 特別展「江戸☆大奥」。東京国立博物館で開催 は Premium Japan に最初に表示されました。