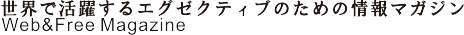人気記事
About&Contact
Stories
Premium X
旅館の矜持 THE RYOKAN COLLECTIONの世界
2025.6.30
心躍る和モダン空間に満ちる、アートと極上のホスピタリティ。地域文化の魅力認知に本気で取り組む「花紫」山田耕平社長
新緑が映える1階の「モダンスイート」は川の水面にいちばん近い。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「ザ・リョカンコレクション」に加盟する旅館の女将や支配人を紹介する連載「旅館の矜持」。今回は石川県加賀市・山中温泉の「花紫」の社長・山田耕平氏を紹介する。
山中温泉は石川県で有数の温泉郷である。今から1300年前に、大僧正の行基が山中温泉の源泉を発見したと伝えられている。老舗の旅館だった「花紫」が「凄いことになっているゾ」と言われはじめたのは、2024年頃のこと。若き当主の山田耕平社長による大胆な改修が話題に上るようになり、そのウワサは東京まで届いていた。
旅館「花紫」の屋号は、地域の美しさを讃える言葉「山紫水明」に由来している。白地に二重の円のシンボルが描かれた大きな暖簾をくぐり、館内に入る。まず印象的だったのは、若いスタッフたちの笑顔と爽やかな挨拶だった。
さて、こんなに気持ち良くさせてくれる笑顔を振りまくホテル・旅館は、日本ではめったにお目にかかれない。一瞬、バリ島やプーケットにある上質なリゾートホテルにでも来たかのような錯覚にとらわれた。人が旅館に対して抱く一般的なイメージは一新されるだろう。ここは、社長ご夫妻をはじめ、若い人たちが中心となって動かしている旅館なのだ。出迎えてくれた山田社長に改修・改革の核心について話を聞いた。
旅館業を通してお客様に伝えたいこと
「きっかけになったのはコロナ禍のときの休業です。それまでは日々の仕事に忙殺されてじっくりと考えるのがちょっと難しかった。休業したことによって、宿泊業のあり方とか、旅行ってなんだろうとか、日ごろからモヤモヤと胸に滞留していた疑問について、立ち止まって考えられたことが大きいです。その意味では、休業はコロナ禍がもたらした僥倖だったのかもしれません。
コロナ禍が明けてもこの先そのまま同じように営業を続けるのかと自問したときに、自分には旅館業を通して伝えたいことがあるはずだと思ったのです。自分が思い描く旅館のイメージもありました。それで、改修に着手してみようと決意しました。」
大きな窓から陽が射し込んで、開放感が抜群のロビー。<wbr />宿泊客でなくとも喫茶の利用ができる。
「自分が思い描く旅館の新しいビジョンと切り離すことはできないのですが、何よりも先に前提にしたいことがありました。それは、どのようにしたら、お客様がより満足していただけるような旅館に変えていけるかです。言い換えれば、お客様が当館に来てくださって、温泉に浸かって食べてお休みになられる、それ以外のことで何かできないか。滞在される間に感じることができる『価値』みたいなものを創造できたらいいなと思ったのです。いや、是が非でも、新しい価値を創出したかったのです。
それ以前はサービス業として、お客様に尽くして尽くしまくって、疲弊してしまうような感じでした。もちろん、そうしたエネルギーの使い方もあるのですが、目指すところはそうではないのではないか。よその旅館にはない『価値』を味わい楽しんでいただく。お客様に対してその提案ができるようになれば、自ずと旅館自体の存在価値も上がっていくはずだというふうに考え至ったのです」
日本文化の地域の拠点の一つになる
「その価値のポイントとなるのは、日本の文化を古いままではなくて、現代の形に変えて伝えていくことです。宿泊体験を通して、日本やこの土地の良いものや文化を感じていただける、そういう場所を目指していきたいと考えていました。具体的に言えば、古くからある部分では、新しい食事の提案であったり、新しいお風呂の楽しみ方ですね。新たに生み出す部分では、当館が北陸の工芸やアート、そしてお茶を含めた食文化の一つの拠点となることです。
言い換えますと、食や飲み物にテロワール(その土地ならではの風土や個性)を感じることはよくあります。『花紫』ではそれだけにとどまりません。器や空間、温泉、そしてアートにいたるまで、すべてがこの土地の魅力を伝えるための『テロワール』となっているのです。
工芸やアートに関して言えば、館内で展示することはもちろん、石川県内、北陸の作家さんを中心にして、土地の作家さんと触れ合えるところまで体験できる旅館を目指そうと考えました。その土地の風土で生まれた作品に囲まれて過ごしたり、さらには、希望があれば、作家さんの工房までお連れしてしまうという構想です。地域全体の魅力を感じていただくのが旅館の役目だと私は思っています。また、都会にはない、それだけの魅力がこの土地にはあるのです。」
暖簾は「山紫水明」を象徴的に表したエンブレムを中央に描いた。
「石川・北陸には様々な分野で作家さんがたくさんいるのですが、それは加賀の前田家から連なる文化的な継承であることを実感しますね。前田さんは本当にエラい人でした(笑)。工芸やアート以外の分野では、例えば、野菜の生産者さんであったり、見事なブリを用意してくれる神経締めの達人の漁師さんであったり、美味しいお米やお茶を作っている農家の方だったりです。そうした土地の魅力を総体として、五感全体で感じていただくための装置、それが旅館だと思っています。実際に、そうした土地の魅力のすべてを集めてきて活用できるのが旅館という存在なのではないでしょうか」
突撃スタイル(⁉)が信条
作家とのネットワークはどのように作るのか?
「基本的には突撃スタイルですね(笑)。展示会を見に行ったり、インターネットやSNSを駆使して、この人に会ってみたいという作家さんを発掘します。あとのコンタクトは主として突撃です。どうやっても辿り着けない場合には、紹介してもらうこともあります。
作家さんは人によっては人前に出ることを好まない方もいらっしゃ<wbr />るので、私どもが、<wbr />そういう作家さんとお客様の間で翻訳者的な立ち位置になれればい<wbr />いと考えています。価値を伝えるのが苦手な方ならば、私どもが媒介者になって価値を伝えられたらいいですね。それで例えば、漆芸の作家さんにアートパネルなどを作ってもらって、展示販売したりしています。生活に近い工芸的な作品から現代アートまで、実験的なことも含めて、幅広く魅力を伝えていければと思っています。
ちなみに現在、館内で見られる作品の作家さんは、写真家の河野幸人さん、仏師の長谷川琢士さん、現代アートのLAKAさん、ガラス工芸の佐々木類さん、漆芸の村田佳彦さん、陶芸の中嶋寿子さん、漆芸の鵜飼康平さんなど北陸を拠点とするアーティストの作品です。昨年はロビーフロア全体を使って作家さんと学芸員の方に対談してもらって、作品発表の場を設けたりしました。この空間をもっと使って欲しいのです。これに関してはどんどん発展しているかもしれません。どこまで行くのか、自分でも興味深く見つめています(笑)」
渋いオーラを放つ茶房。ここで専門的な訓練を受けたスタッフが、<wbr />本格的にお茶を淹れてくれる。ここかしこに作家の作品が置いてある。
ロビーの売りは、渋いオーラを放つ「茶房」
すべてのゲストは4階に当たるロビー階に到着する。すぐに気づくのは、随所に様々な作家のアートや工芸が設置してあることだ。フロントを通り過ぎた先が素晴らしい。ゆったりしたラウンジには大きな窓が一面に並び、渓谷に沿って、対岸でまばゆいほどに緑を放つ新緑が目に飛び込んでくる。このラウンジに隣接するのが「茶房」で、ちょっとした陰翳の中にあって、加賀杉のカウンターが伸びている。全体が落ち着いていて渋いオーラを放っている。
アフタヌーンティーは予約制で(6000円)、<wbr />宿泊客でなくても味わえる。お茶はもちろん茶房で淹れたものだ。
「実は、コロナ前の改装する際のぼんやりとしたイメージでは、ゲストが自由に紅茶やコーヒーを楽しめるセルフサービスのラウンジを想定していました。人を減らして生産性を上げていこうみたいな流れですね。しかし、考えているうちから、これは違うんじゃないかと思っていました。人の手をかけずにオートマティックな流れなわけですが、これを旅館でやる意味はどこにあるんだという疑問を抱くようになりました。
効率化した先には何もないなとも思いました。切り詰めて行って利益を出す、そういう考え方もあるのですが、利益が出たところで、自分たちもお客様も満たされないのならば、やるだけ無意味です。とすると、日本の文化を伝えていくとなれば、やっぱり日本の美意識すべてが詰まっているお茶だよねということになったのです。
それでロビー階の改修に際して造ったのが茶房でした。厳選されたお茶を人の手で丁寧に淹れることによって、お客様も集まってきて、その価値を感じてくれる。差別化できるポイントとはそういうことかなと思って、そちらに振り切ってみました。ですから、きっぱりとコーヒーを出すのはやめました(笑)。特に海外のゲストの方はコーヒーを好まれますが、お部屋で淹れてもらっています」
茶房のお茶は、このように10数種類あって、プレゼンを受けた後にゲストがチョイスする。目の前で繊細に淹れてくれる。
茶房チームは東京で研修
とは言え、それで出来上がった茶房なるものは、洗練の度合いが桁違いだ。
「修練を受けた専門のスタッフが、煎茶、加賀棒茶、抹茶、和紅茶などの10数種類のお茶、お茶のカクテルである茶酒などを、作家さんと私で共作しました特別な茶器、例えば九谷焼や珠洲焼、漆器、ガラスなどお茶に合わせた茶器でお出しします」
筆者は煎茶好きなのだが、三煎味わったお茶の味わいにはまさに格別なものがあった。
先代が20年前に作った見事なダイニング。今や世界的な和紙作家である堀木エリ子氏の作品を大胆に配した。先代のアートを見る目も確かなものだったことがわかる。右は奥様の山田真名美さん。
当館の企画・広報を担当する奥様の山田真名美さんが付け加える。
「新しく茶房チームに入ると、東京での研修がありますので、実際にお茶を習って帰ってきます。そのあとは季節ごとに東京から来てもらっています。そのたびにテストがあって、改善点を直していきます。ただお茶を淹れるだけでは意味がありません。そのお茶に価値があるぐらいのレベルにしなければと考えています。
インスタグラムなどでこの茶房があることを知って、今では茶房に入りたくて入社する社員もいるほどです。大体は県内ですが、県外からも応募があります。旅館で働きたいけれども、同時にスキルを身につけたい若い人には、一石二鳥なのでしょうね」
ご主人が続ける。
「年に何回かお茶会を開催しておりまして、展示している作家さんの器を使ってお茶を体験していただくこともやっています。今、茶房チームのトップは、茶房ができる前の時代からいる社員です。以前は私と一緒にコーヒーをポッターに入れて注ぎまくっていました。それが今やいちばん上に立ってお茶の指導をしています。彼女にとってもスキルアップできているので、仕事の付加価値を感じてくれているのではないかと思います。サービス業でもそういうことがないと今の若い社員たちは続きません」
1階の「モダンスイート」にて。渓谷沿いの新緑がダイレクトにまぶしい。部屋のミニマルなデザインが心地よい。
新しいコンセプトを詰める
先代が造り上げた「花紫」は、見事な数寄屋造りの旅館ではあったが……。
「小さい頃から数寄屋造りを見すぎてしまったせいか、何も感じなくなっていまして、むしろ根本的に変えたいとずっと以前から考えていました。しかし、大学生の時にサンフランシスコに2年ほど留学しまして、日本を外側から見たら、すごく美しいものがたくさんあることに気づいたのです。と同時に、それはそのままでは現代の人には伝わらないなとも思いました。
それからですね、どうすれば伝わるのかの模索を始めたのは。様々な宿に出かけたり、また日本のデザインをいろいろと調べるうちに、SIMPLICITYの緒方慎一郎さんに行きついたのです」
デザイナーの緒方慎一郎氏は、建築、インテリア、プロダクト、グラフィック等のデザインやディレクションで知られる。自身のお店である「Ogata Paris」、「Aesop」の店舗や5スターホテルの空間デザインなどを手掛けた。
「緒方さんは技法的には伝統的なものを使われるのですが、アウトプットされたデザインはとても現代的です。そこがすごくシックリきました。今回、当館のリニューアルを進めるに当たっては、普通はいきなりデザインから入る事務所が多いと思うのですが、緒方さんはコンセプトデザインから一緒に考えてくださったので、本当に良かったです。私のイメージを緒方さんにお伝えし、緒方さんからも沢山の提案を頂戴しました。本当に、詰めに詰めた結果がいまある姿になったのです」
以前の数寄屋造りからすると、完全な変貌を遂げた。4階のロビー階で、山田氏が考えた画期的なことがほかにもある。
「一般に旅館というのは、宿泊者しか施設には入って来ないのが当り前です。とても閉鎖的なのです。それを宿泊者じゃない方たちにも開放できないものかというのが、私の長年の課題でした。そこで、ロビー階にラウンジを作って、朝の9時から夕方の5時半まで、茶房を使った喫茶ができるようにしました。予約制でアフタヌーンティーもありますし、夏に向かってはカキ氷などのご用意もあります。地元の方たちにも気軽に使ってもらいたいのです」
ホテルのロビーじゃないのに、従来の旅館にしてみれば、まさに驚くべき発想だ。これも彼の思考が〝お客様ファースト〟に向かっているからこそ生まれてくるアイデアなのだろう。
ゲストルームの秀逸な和モダン
双子のお風呂には衝撃を受けた。ガラス窓の手前は内風呂、向こうがは外風呂で半露天になっている。その発想が凄い。
実は、4階のロビー階から順次下って3階から1階の客室も見事な和モダンに生まれ変わった。例えば1階のモダンスイートのお風呂のデザイン性には目を瞠(みは)った。ガラスの窓を境にして内風呂と外風呂の湯舟が双子のように、内と外に配置されている。もちろん、外風呂は半露天なのだ。しかも、サウナルームに水風呂まで完備しているというオマケ付きである。寝具にも自信があるという。
「金沢の布団屋さんでISHITAYAのものです。特に羽毛が相当な品質で、極薄なのにとても暖かいです」
確かに掛けていることを忘れるぐらいに軽く、存分な保温性がある。マットレスが硬いのも好みで、きわめて快適な寝心地だった。
懐石料理である夕食はそれぞれが素晴らしい。そのうちの一品「とらふぐの白子蒸し」は、白子の濃厚さが背徳的なほどに味蕾をかき乱し、長く記憶に残った。器は同年代の作家、吉田太郎氏との共作で花紫オリジナルのもの。
もちろん、食は夜も朝も素晴らしい。
夜は料理長の中村雅和氏の手による本格的な懐石である。地野菜、地元のお造り、蛤、海苔、能登牛に特別栽培のこしひかり……。石川県の海と山の恵みをふんだんに使った、どれもが味わい深い品々に感嘆の声をあげたくなる。能登鮪のお造りだって、醤油で食すのではない。上に載せられたのは海苔の佃煮だ。新しい食べ方である。ほかにも、とらふぐの白子蒸し、地蛤の飯蒸し、能登牛のローストが印象深かった。日本酒好きにとっては、あの中田英寿氏も一推しの地元・松浦酒造「獅子の里」や、白山の吉田酒造店「手取川」などの銘酒もズラリ。ついつい飲み過ぎてしまう。
「にほんの朝ごはん」は、一品一品に魂が宿る。七輪で焼くノドグロや蛍烏賊は干物だけに旨味が深く、出汁巻きたまごのジューシーな味の濃さに目が覚める。特筆すべきは地元のこしひかりの美味しさだ。4種の漬物や海苔の佃煮に至るまで吟味されているからたまらない。ご飯のお代わりは必至である。
朝食はおかずの一つ一つに心がこもっている。蛍烏賊やノドグロの干物を目の前の七輪で燻すのも格別で、漬物や海苔の佃煮に至るまで美味しい。特別栽培の白米と浅利椀が秀逸だった。
冒頭の若いスタッフたちの話に戻す。
「いまスタッフは半分以上が20代で、平均年齢は32歳です。最近は新卒採用にすごく力を入れてやっていますので、全国から入社志望者がやってきます。サービス業は大変で、特に旅館はそうしたイメージがあると思いますが、水曜と木曜を休館にして、働きやすい環境作りにも取り組んでいます。英語研修や茶道、華道、ソムリエによるドリンクの研修など、専門知識が養えますから、スキルアップも望めます。こういうところなら働いてみたいなと思ってもらえたら嬉しいですね」
実は、山田社長の〝野望〟は留まることを知らない。
「具体的にはまだ言えないのですが、昔からやりたかった新たなプロジェクトを考えています。発表までもう少々お待ちください」
山田 耕平 KOHEI YAMADA
石川県加賀市山中温泉にある老舗旅館「花紫」六代目当主。<wbr />2021年に創業120年を超える花紫を継承した。<wbr />10代の頃からストリートアートに傾倒し、Academy of Art University(サンフランシスコ)に進学、<wbr />アートとフォトグラフィーを学ぶ。帰国後はその感性を活かし、<wbr />2022年より花紫のリニューアルプロジェクトを始動。<wbr />館内には現代アートや工藝を展示し、<wbr />地元の若手作家を支援するギャラリーや、<wbr />日本文化に触れられる茶房を設けるなど、「<wbr />現代における日本の文化サロン」<wbr />をコンセプトとした空間やコミュニティを創出している。<wbr />豊かな自然と暮らしとものづくりが交差する山中温泉に可能性を見<wbr />出し、唯一無二の滞在体験を目指し、<wbr />新たな魅力を発信し続けている。
構成/執筆:石橋俊澄 Toshizumi Ishibashi
「クレア・トラベラー」「クレア」の元編集長。現在、フリーのエディター兼ライターであり、Premium Japan編集部コントリビューティングエディターとして活動している。
photo by Toshiyuki Furuya
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Premium X
旅館の矜持 THE RYOKAN COLLECTION…
Premium X
関連記事
投稿 心躍る和モダン空間に満ちる、アートと極上のホスピタリティ。地域文化の魅力認知に本気で取り組む「花紫」山田耕平社長 は Premium Japan に最初に表示されました。
海外で暮らすと決めるとき、「とりあえず行ってみよう」という意気込みは大事ですが、いくつか事前に覚悟しておくと役立つことがあります。特に長期滞在の場合はなおさらです。実務的な準備だけでなく、不測の事態に備えた心の準備もしておきましょう!
『少年が来る』は、ハン・ガン作家の代表作のうちの1つ。韓国光州で起こった民主化運動を描いた作品である。2025年初夏、小説ゆかりの場所を巡る文学紀行が開催された。主要な史跡と共に、その様子をリポートする。※画像:筆者撮影
Features
世界で大人気のサントリーブランド「ROKU〈六〉」の体験拠点が期間限定オープン
2025.6.26
高輪「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN」サントリー「ROKU〈六〉」ブランドを深く知り愉しむ
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」初のコンセプトショップ「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN(以下ROKKAN)」が、グランドプリンスホテル高輪に6 月 18 日より約 1 年間だけオープンする。
日本の伝統技法を用いた光の少ない空間は、私たちの五感を研ぎ澄ますことでより味わい深く、そして心静かに過ごせる、知る人ぞ知る大人のBarである。
なぜ「ROKU〈六〉」がここまで世界で高く評価されているのか
2017 年の発売以来、約60 カ国で販売され、海外の販売ボリュームが約 9 割を占め、世界のプレミアムジンランキングで第 2 位という世界でも評価の高いグローバルブランドだ。かねてから海外ではジャパニーズウイスキーが高い評価を得続けているが、日本のボタニカル素材が醸し出すジャパニーズクラフトジンもまた、海外の愛好家たちを魅了している。
「ROKU〈六〉」と、2025年限定品が並ぶ。
「ROKU〈六〉」ブランドは、日本の四季が生んだ 6 種のボタニカル(桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子)を使用して、繊細な職人技で完璧な香味バランスを追求。華やかな香りとともに、優しい飲み口は他にはない、まさに本格的なジャパニーズクラフトジンと呼べる。サントリーの強いこだわりによって生まれた「ROKU〈六〉」ブランドは年々売り上げを伸ばしていることからも、その評価がいかに高いのかがうかがい知れる。
もっと「ROKU〈六〉」ブランドを深く知り、そして愉しむ空間が「ROKKAN」である
「ROKKAN」は事前予約制の「ジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉体験コース」と予約なしで利用できるBarがあり、用途によって使い分けることができる茶室Barである。
和の要素を取り入れた静謐な空間。
予約が必要な体験コースは、趣の違う3つの和空間を巡りながら、原料であるボタニカルに触れる体験やジンを学んだり、「ROKU〈六〉」を使用した四季のカクテルと和菓子のフードペアリングを楽しんだり、よりジンを知り、そして「ROKU〈六〉」に触れることができるコース構成になっている。
「ジャパニーズクラフトジン ROKU〈六〉体験コース」(事前予約制/税込み 1 名 5,000円)予約可能時間:①15:30~17:00 / ②17:00~18:30
また予約なしで訪れることができるBarは、「ROKU〈六〉」を使用したオリジナルカクテルを楽しむことができるほか、「ROKU〈六〉」ブランドの飲み比べをすることができる。
さらに予約をすれば、カクテルと和菓子のペアリングコース(事前予約制/1 名 5,000 円)の体験も可能だ。ジャパニーズクラフトジンならではの、季節ごとの香りや素材を表現したカクテルと和菓子のペアリングは思わぬ発見があることだろう。
抹茶マティーニ1,400円
寿ネグローニ 1,400円
朝涼とアイスみつ豆のペアリング ※単品2,000円
世界的に人気の高い「ROKU〈六〉」をとことん味わう体験できる「ROKKAN」は、クールで洗練された大人の隠れ家Barである。日本の美意識に包まれた時間をゆっくりと味わってみてはいかがだろうか。
◆「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN」
【営業期間】2025 年 6 月 18 日(水)~2026 年 6 月 30 日(火)※日・祝日休
【場所】グランドプリンスホテル高輪内 B1(〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1)
【営業時間】体験コースとバー営業の二部制で営業します。
・体験コース: ①15:30~17:00 / ②17:00~18:30
・Bar Time:18:30~23:00(ラストオーダー22:30)
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 高輪「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN」サントリー「ROKU〈六〉」ブランドを深く知り愉しむ は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
W大阪で開催。カクテルとカルチャーが交差する3日間限定イベント
2025.6.25
ソウルの最旬バー「GONG GAN」がW大阪に登場
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
W大阪にて、韓国・ソウルで注目のバー「GONG GAN」のトップバーテンダー、Evan氏とJoon氏を迎える限定イベント「REFRESH」が、7月4日(金)、5日(土)、6日(日)に開催される。
韓国・ソウルのバー「GONG GAN」
(左)「GONG GAN」オーナーバーテンダーEvan氏 (右)「GONG GAN」初代バーテンダーJoon氏
「REFRESH」は、Wホテルと南フランス生まれのナチュラルミネラルウォーター「Perrier」とのパートナーシップによる、世界各都市を巡るグローバルイベント。Wホテルならではのカクテルカルチャーに、ペリエの爽快なスパークリングのエッセンスを加え、カクテル、食、音楽を融合させた唯一無二のプログラムを展開する。
3階「LIVING ROOM」
3階ソーシャルハブ「LIVING ROOM」で行われる初日は、韓国・ソウルのナイトシーンに迷い込んだようなDJイベント「REFRESH ビート」を開催。韓国のビートに乗りながら、「GONG GAN」の2人によるスペシャルカクテルを楽しめる。
3階「Oh.lala…」
2日目は、同じく3階のニューブラッセリー「Oh.lala…」にて、W大阪の遊び心が光る「REFRESH カクテルペアリングディナー」を開催。ディナー後は、同フロアの「LIVING ROOM」で行われるラテン音楽イベント「Salsa & Latin Night」への招待も。
4階「WET DECK」
最終日となる3日目は日中の開催。海外リゾートのような開放的な空間が広がる4階「WET DECK」にて、韓国スイーツを取り入れたアフタヌーンティーとともに、「GONG GAN」の2人が手がけるカクテル、モクテルを楽しめる。
W大阪を舞台に、伝統と革新が交差するアジアのバーシーンの現在地を体感できるイベント。味覚、聴覚、そして美意識までも潤す“REFRESH”な時間を楽しんでみては。
◆W大阪「REFRESH」
≪DAY1≫「REFRESH ビート」
【日時】2025年7月4日(金)20:00~24:00
【場所】3 階 ソーシャルハブ「LIVING ROOM」
【料金】
〈VIPシート〉 1シート 60,000円(最大4名様まで)
(W大阪オリジナルラベルシャンパンニューボトル1本+「GONG GAN」オリジナルカクテルの2種)
〈一般〉1名 3,000 円(1 ドリンクチケット付き)
≪DAY2≫ 「REFRESH カクテルペアリングディナー」
【日時】2025年7月5日(土) 18:30~21:30
【場所】3 階 ニューブラッセリー「Oh.lala…」
【料金】 ディナー 1名15,000 円(4品コースと「GONG GAN」 カクテル4種のペアリング)
≪DAY3≫「REFRESH コリアンアフタヌーンティー」
【日時】2025年7月6日(日) 12:00~15:00
【場所】4階 「WET DECK」
【料金】1名 8,500 円(コリアンアフタヌーンティー+「GONG GAN」カクテル2種のペアリング※モクテルに変更可。コーヒー、紅茶のフリーフロー付き。)
※要予約
※料金はすべて税・サービス料 15%込。
※写真はすべてイメージです。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 ソウルの最旬バー「GONG GAN」がW大阪に登場 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
約200点の絵画と資料でひもとく、日本人の旅の原風景
2025.6.24
茨城県近代美術館にて開催「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」
初代歌川広重《東海道五拾三次之内 庄野 白雨》天保初期(1830年代) 郵政博物館蔵 ※8/16~8/31 展示
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
茨城県近代美術館にて、江戸時代から現代にいたるまで、“旅”の魅力がつまった約200の作品を紹介する「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」が開催される。会期は7月16日(水)から8月31日(日)まで。
初代歌川広重《東海道五拾三次之内 御油 旅人留女》天保初期(1830年代) 郵政博物館蔵 ※8/1~8/15 展示
東山魁夷《白夜光》1965 年 東京国立近代美術館蔵
見どころのひとつが、初代歌川広重が手がけた「東海道五拾三次」の浮世絵シリーズや、横山大観がインドで出逢った光景を描いた「流燈」、旅とともに生きた国民的風景画家・東山魁夷の北欧連作のひとつ「白夜光」など、時代や地域を超えて人々の心を動かしてきた名作の数々。
横山大観《流燈》1909年 茨城県近代美術館蔵
小杉未醒《水郷》1911年 東京国立近代美術館蔵
また、展示されている絵画を通じて、ヨーロッパやアジアなど、画家たちが訪れて描いた世界各地の名所めぐりを疑似体験できるのも魅力だ。国内の景勝地では、数多の名画に登場してきた富士山をはじめ、潮来や霞ヶ浦、筑波山、袋田の滝など、茨城ならではの風景を描いた作品も登場する。
吉田博《槍ヶ岳》1921-26年 茨城県近代美術館蔵
このほかにも、江戸時代に人気を博したガイドブック『旅行用心集』や、日本初のグラフィックデザイナー杉浦非水が装丁を手掛けた旅行雑誌『ツーリスト』、鉄道のポスターなど、旅の“エトセトラ”を彩る資料類も展示。当時の旅文化や社会の空気感までも伝える貴重な資料が揃う。
三代歌川広重《東海名所改正道中記 六郷川鉄道 川崎 神奈川迄ニり半》1875 年 郵政博物館蔵 ※7/16~7/31 展示
絵画を通して、その時々に生きた人々が抱いた、旅することへの憧れや喜びを体感できる展覧会。この機会に、日本の旅情を深く味わってみてはいかがだろうか。
◆「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」
【会期】2025年7月16日(水)~8月31日(日)
※会期中、一部展示替えあり
【会場】茨城県近代美術館(茨城県水戸市千波町東久保666-1)
【開館時間】9:30~17:00(入場は16:30まで)
【休館日】毎週月曜日
※7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)は開館、翌日休館
【入場料】一般 820円、満70歳以上 410円、高校生 550円、小中生 270円
※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持参の方および付き添いの方(1名)は無料
※7月19日、8月30日は高校生以下無料
※7月19日は満70歳以上の方無料
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 茨城県近代美術館にて開催「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」 は Premium Japan に最初に表示されました。
今やベースメイクの定番となったクッションファンデーション。そのパイオニアといえば、韓国のアモーレパシフィックです。そこで今回は、韓国のベースメイクのトレンドとともに、アモーレパシフィックのおすすめクッションファンデーションをご紹介します。
クルーズ船に英国女王の名を冠することが許された唯一の船会社、キュナード。昨春就航した「クイーン・アン」は、伝統を継承しつつ、時代のニーズにあわせたデザインや施設が魅力。英・サウサンプトンを母港にショートクルーズも。 ※画像:キュナード提供
Events
【7/23日(水)、7月24日(木)ホテル椿山荘東京】
2025.6.21
英国の紅茶文化とマナーを家族で学べる「英国式アフタヌーンティーマナー教室」を夏休みに初開催
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
ホテル椿山荘東京は、紅茶の国・英国の紅茶文化とマナーを家族で楽しく学べる体験教室「英国式アフタヌーンティーマナー教室」を、2025年7月23日(水)、24日(木)に初開催する。
国家検定資格を持つスタッフが、アフタヌーンティーの歴史や、マナー、紅茶についてなど、初めての方にも分かりやすく説明。ホテル特製の三段スタンドで提供する「サマーハニーアフタヌーンティー」を味わいながら、ティーカップの持ち方や紅茶の注ぎ方、スコーンの食べ方など、日常でも役立つ英国式の基本マナーを親子で一緒に楽しく学ぶことができる。
このほか、7月26日(土)から 8月17日(日)までの特定日には、ナイフとフォークで食事をするレストランや、かしこまった席に欠かせないテーブルマナーを学ぶ体験教室「夏休み 家族で楽しむテーブルマナー教室」も開催する。子供も食べやすく工夫した特製フレンチコースを、大人用のカトラリーやグラスを使って味わいながら、楽しく学ぶテーブルマナー教室だ。
あなたも親子で夏休みの素敵な思い出を作ってみてはいかが。
◆家族で楽しむ 英国式アフタヌーンティーマナー教室
【期間】2025年7月23日(水)、7月24日(木)※事前WEB決済予約制
【時間】2部制 約120分 ①11:00~13:00 ②14:30~16:30
【会場】ホテル棟3階 ル・ジャルダン「サロン」
【料金】一人 13,800円(消費税・サービス料込み)
※本イベントは小学生以上が対象
◆夏休み 家族で楽しむテーブルマナー教室
【期間】2025年7月26日(土)〜 8月17日(日)※期間中、特定日開催 ※事前WEB決済予約制
【時間】12:00~14:00 ※30分前より受付開始
【会場】ホテル宴会場
【料金】20歳以上 一人12,000円、小学生~19歳 一人9,600円(消費税・サービス料込み)
※本イベントは小学生以上が対象
※いずれも詳細は公式ホームページで要確認
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 英国の紅茶文化とマナーを家族で学べる「英国式アフタヌーンティーマナー教室」を夏休みに初開催 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
夏の銀座で出合う、涼やかな美食の旅
2025.6.20
福岡の食材を味わう「アルマーニ / リストランテ」夏のシーズナルメニュー
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
モダンイタリアンの名店「アルマーニ / リストランテ」で、夏季限定のシーズナルメニューがスタート。その⽇に仕⼊れた最⾼の⾷材を⽤いたシグネチャーコース「OMAKASE」や、ランチ限定コース「TRADIZIONE LUNCH」「CLASSICO」などで楽しめる。
タリオリーニ【提供コース︓OMAKASE】
今季フォーカスしたのは、「福岡」。豊かな大地が育む野菜や、三方を海に囲まれた地形がもたらす海の幸といった、福岡ならではの食材を厳選。エグゼクティブ シェフ ブルノ・昼間の感性によって、土地の魅力が皿の上で美しく昇華される。
カッペリーニ【提供コース︓TRADIZIONE LUNCH】
カプレーゼ【提供コース︓OMAKASE】
なかでも注目は、冷製仕立ての「カプレーゼ」や「カッペリーニ・アル・ポモドーロ」など、イタリアで長く親しまれてきた料理を、日本の夏に合わせて涼やかに再構築したメニュー。イタリアを連想する“トマト”を主役に、軽やかながらも繊細な旨みがあふれる⼀⽫に仕上がっている。
うなぎ 【提供コース︓OMAKASE】
また、日本の夏の風物詩である“うなぎ”をイタリア伝統の「スカペーチェソース」でモダンにアレンジした一品など、日本の繊細さと南イタリアの個性が交差するメニューも必食だ。
桃 酒粕【提供コース︓OMAKASE】
食後には、福岡県産の酒粕と桃を組み合わせたデザート「桃 酒粕」を。ナポリの伝統菓子「ババ」に和のエッセンスをまとわせた一皿が、五感を満たす甘美なフィナーレを演出する。
ハラミ【提供コース︓OMAKASE】
銀座の高層階に佇むモダンイタリアンの名店で味わう贅沢なランチ。イタリアのエッセンスと日本の風土が織りなす軽やかな味わいを、ぜひ堪能してみては。
アルマーニ / リストランテ
【住所】東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 10階&11階
【営業時間】ランチ 11:30~15:00(L.O. 14:00) ディナー 18:00~23:00(L.O. 20:00)
【定休日】日曜日(8月31日まで)・月曜日
【電話番号】03-6274-7005
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 福岡の食材を味わう「アルマーニ / リストランテ」夏のシーズナルメニュー は Premium Japan に最初に表示されました。
パサディナはロサンゼルスの北にあるおしゃれなエリアです。中心のコロラドブルーバード沿いには、たくさんのカジュアルなショップがあり、ぶらぶらショッピングを楽しむことができます。また、ハンティントンライブラリーやノートンサイモン美術館などのアート施設も充実しています。
【管理栄養士が解説】朝の果物は健康や美容にいいとされていますが、選び方や食べ方によっては、かえって体重増加につながる可能性もあります。今回は、朝に果物をとる際の注意点とおすすめの食べ方をご紹介します。
全顔用のシートマスクは面倒だけれど、頬の乾燥など部分的な悩みがある人もいるのではないでしょうか。そこでおすすめなのが「部分用シートマスク」。気になるパーツに貼るだけなので、手軽に取り入れることができます。今回は、おすすめ4品をご紹介します。
【管理栄養士が解説】朝の果物は健康や美容にいいとされていますが、選び方や食べ方によっては、かえって体重増加につながる可能性もあります。今回は、朝に果物をとる際の注意点とおすすめの食べ方をご紹介します。