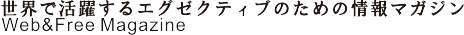人気記事
About&Contact
Features
「星のや軽井沢」バードウォッチングステイ
2026.2.24
日本屈指の探鳥地へ。春の軽井沢で楽しむアドベンチャーツーリズム
国設「軽井沢野鳥の森」でのバードウォッチング
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
「星のや軽井沢」では、2026年4月15日から5月31日までの期間、日本屈指の探鳥地として知られる国設「軽井沢野鳥の森」を舞台にした特別な滞在プログラム「軽井沢バードウォッチングステイ」を提供する。
幸せの青い鳥「オオルリ」
森のピッコロ奏者「キビタキ」
上信越高原国立公園内に広がる「軽井沢野鳥の森」は、年間約80種の鳥類が観察される自然豊かな森。春には南国からの渡り鳥が繁殖のために訪れ、約25種類もの野鳥を観察できる。
国設「軽井沢野鳥の森」でのバードウォッチング
本プログラムでは、この「<wbr />軽井沢野鳥の森」を動植物の専門家「ピッキオ」とともに巡る「プライベートバードウォッチング」を開催。鳥の特徴や行動、さえずりの違いなどを学びながら観察を深めていく。観察には、世界最高水準の光学機器メーカー「SWAROVSKI OPTIK」の双眼鏡を用意。息をのむほど美しい鳥たちの姿を鮮明に捉えることができる。
客室には双眼鏡と望遠鏡に加え、マウンテンパーカーや野鳥図鑑、オリジナルマップ、特製リュックとウォーターボトルも完備。滞在中いつでも本格的なバードウォッチングを楽しめる。
さらに、時を超えた森の奥深さを知る体験「バードタイムトラベラー」も実施。これは、半世紀前にこの森で録音されたという秘蔵レコードに記録された鳥の声と、現代の鳥のさえずりを聴き比べるもの。森に仕掛けられたタイムカプセルを開くような経験を通じて、自然環境や生態系にどのような変化があったのかを考察する。
黄昏の森でのバードコンサート
黄昏時には、森に響く鳥のさえずりを楽しむ「バードコンサート」体験も。鳥たちの合唱に包まれながら、静寂に包まれる森でリクライニングチェアに身を委ねる。そんな癒しの時間を過ごせるのも魅力だ。
朝食は、敷地内で最も高い場所に位置する客室テラスで「バードテラスモーニング」を提供。旬の山菜を用いたスープ朝食で心身を温めながら、テラスの木々に集まる鳥たちの歌声を楽しめる。
「森のほとりバードBar」
野鳥をイメージしたストーリーカクテル
夜は、野鳥の森の入り口にたたずむバーで、鳥にインスピレーションを得たストーリーカクテルを堪能。春に見られる幸せの青い鳥「オオルリ」をイメージした一杯など、鳥にまつわる物語とともに味わうカクテルが、翌朝の早朝バードウォッチングへの期待を高めてくれる。
「観る・聞く・味わう」という三つの感覚を通して、渡り鳥の世界や自然への理解を深める滞在。春の軽井沢で、知的好奇心を満たす時間を過ごしてみてはいかがだろうか。
◆「軽井沢バードウォッチングステイ」
【期間】2026年4月15日~5月31日(除外日あり)
【料金】1名・90,000円(税・サービス料込)*宿泊料別
含まれるもの:プライベートバードウォッチング1回、バードコンサート1回、バードテラスモーニング1回、森のほとりバードBar1回(ワンドリンク付き)、SWAROVSKI OPTIK製双眼鏡・オリジナルマップの貸し出し、特製リュック&ウォーターボトル
【定員】1日1組(4名まで)
【予約】公式サイトにて10日前までに要予約
【対象】星のや軽井沢宿泊者、4歳以上対象
※天候により時間やツアー内容が変動する可能性があります。
※仕入れ状況により料理内容が一部変更になる場合があります。
※雨天開催、荒天時は中止となります。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2026.2.19
フォーシーズンズホテル丸の内 東京「桜 アフタヌーンティー」
Features
2026.2.17
国立新美術館で開催。『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』
Features
2026.2.16
第60回「京の冬の旅」開催。豊臣秀長・秀吉ゆかりの地をめぐる特別公開や体験プランなど
投稿 日本屈指の探鳥地へ。春の軽井沢で楽しむアドベンチャーツーリズム は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
避粉地・沖縄で、眠りを整える
2026.2.13
星のや沖縄、春限定スリープツーリズム「うりずん調眠滞在」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
スギやヒノキの花粉が飛散しない“避粉地”として知られる沖縄。春は朝晩の寒暖差も穏やかで、1年でもっとも過ごしやすい季節とされる。星のや沖縄では、そんな春ならではの快適な環境を生かし、良質な睡眠を得るためのスリープツーリズム「うりずん調眠滞在」を、2026年3月1日から6月30日まで提供する。
冬から春へと移ろうこの時期は、寒暖差の影響や花粉による眠りの妨げなどで睡眠の質が低下しやすく、身体の不調を感じやすい。本プログラムでは、自然の中での運動やスパトリートメント、食事などを組み合わせることで身体のリズムをととのえていく。
夕日とともに海辺で乗馬体験
インフィニティプールで行うエクササイズ
滞在の軸となるのは、花粉を気にせず屋外で過ごせる環境を生かしたアクティビティ。1日は、全身に光を浴びる「朝日浴」からスタート。日中には乗馬体験やアクアティックエクササイズなどで全身の筋肉をバランスよく使い、冬の寒さでこわばった身体をゆるめていく。
自然に包まれながらのスパトリートメント
就寝前のリラックスタイム
スパトリートメントの内容も、上質な眠りを意識。月桃の香りと肌触りが心地よい「月桃玉」で睡眠前の身体をほぐし、就寝前後にはオリジナルハーブティーを味わい、快適な眠りと爽やかな目覚めをサポート。また滞在中のパジャマには、血行促進作用や筋肉のコリ、冷えの改善に効果のあるセルフメディケーションウェアが用意される。
沖縄の食文化を感じる琉球朝食
植物性の食材をたっぷり味わう客室での夕食
食事もまた、1日のリズムと眠りを意識したメニューに。上質なたんぱく質である「豆腐」や食物繊維豊富な「アーサ(あおさ)」など、良質な眠りに導くといわれる栄養素を含む食材を取り入れ、眠りに向かう身体をやさしく整える。
避粉地沖縄で、穏やかな自然とゆったりとした時間の流れに身をゆだね、快適な眠りを味わう「うりずん調眠滞在」。心身をいやし、夏に向けて体を調律するためのウェルネスな旅となりそうだ。
◆「うりずん調眠滞在」
【期間】2026年3月1日(日)~6月30日(火)
【料金】1名 150,000円(税・サービス料込)※宿泊料別
【定員】1組2名まで
【含まれるもの】
・ゆんたく庭めぐり(クヮンソウ茶づくり)
・乗馬体験
・朝日浴(2回)
・スパトリートメント「月」(1回)
・夕食1回、朝食2回、昼食1回
・アクアティックエクササイズ・浮遊浴
・セルフメディケーションウェア
【予約】公式サイトにて14日前まで受付
※18歳以上。仕入れ状況により、食事内容や食材が変更になる場合があります。天候によって実施内容が変更する場合があります。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 星のや沖縄、春限定スリープツーリズム「うりずん調眠滞在」 は Premium Japan に最初に表示されました。
昨秋から続く中国・香港の訪日警戒。そんな状況下で気になるのが「日本人が現地を旅して楽しめるのか?」ということ。卒業旅行や春休みを前に、現地の状況はどうなのか? 安近短で行けると人気の旅先「香港」のリアルをお届けします。
Features
「星のや奈良監獄」2026年6月25日開業
2026.1.24
国の重要文化財「旧奈良監獄」が、ラグジュアリーホテルとして新たな時を刻む
星のや奈良監獄 ティザー映像
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」が、2026年6月25日に開業する。
「星のや」は、「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、土地の歴史や文化を生かした圧倒的な非日常体験を提供するラグジュアリーブランドであり、「星のや奈良監獄」は9つ目の施設として誕生する。
ここは、明治政府によって計画された五大監獄のうち、唯一現存する貴重な建築物「旧奈良監獄」を舞台としている。
旧奈良監獄の外観
赤レンガの外壁や、旧監獄を象徴する放射状の舎房など、歴史的価値の高い建築意匠を継承しながら、「明けの重要文化財」をコンセプトに、現代的な感性を取り入れた新たなデザインを融合。
100年以上の時を刻んできた旧奈良監獄が、その歴史を受け継ぎながら、ラグジュアリーホテルとして新たな役割を担う。
星のや奈良監獄 全景イメージ
全48室の客室はすべてスイートルーム。往時の舎房を複数連結し、寝室、リビング、ダイニングなどを備えた、ゆとりある空間構成となっている。
重厚なレンガ壁に守られた室内には、時間とともに移ろう光が差し込み、静謐で贅沢なひとときを過ごすことができる。
客室タイプ「The 10-Cell」は、独居房という最小単位の空間を10房分つなぎ合わせた、象徴的な一室。
漆喰の下から現れた100年を超える手積みレンガ、新たな時代の建築を支える太い鉄柱、そしてウッドパネルが調和し、重要文化財の歴史と現代の感性が美しく重なり合っている。
客室タイプ「The 10-Cell」間取り図
リビング
寝室
別棟のダイニングでは、西洋から伝わった伝統的な技法を、日本人の感性で進化させた日本のフランス料理を提供予定。そのほかにも、「星のや」ならではの非日常を体感できる空間演出やアクティビティが計画されている。
また、旧奈良監獄の敷地内では、ラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」に加え、旧奈良監獄の歴史や建築を伝える「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」(日帰り利用可)を展開する。
奈良監獄ミュージアムは、「美しき監獄からの問いかけ」をコンセプトに、2026年4月27日に開館予定。
「奈良監獄ミュージアム」展示イメージ
◆星のや奈良監獄
【住所】奈良県奈良市般若寺町18
【TEL】050-3134-8091(星のや総合予約)
【客室数】48室
【チェックイン/チェックアウト】15:00/12:00
【開業日】2026年6月25日
【予約受付開始】2026年1月20日
【料金】1泊147,000円~(1室あたり、税・サービス料込、食事別)
【アクセス】JR奈良駅より車で約10分/近鉄奈良駅より車で約6分
【併設施設】奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート(日帰り利用可)
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 国の重要文化財「旧奈良監獄」が、ラグジュアリーホテルとして新たな時を刻む は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
春の京都で、雅な舞に酔いしれる
2026.1.22
祇園甲部の芸妓舞妓が華やかに舞う。第百五十二回公演「都をどり」
令和7年公演より(第1景 置歌)
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
京都最大の花街・祇園甲部の芸妓舞妓の舞を鑑賞できる「都をどり」。第百五十二回公演が、4月1日(水)から4月30日(木)まで、祇園甲部歌舞練場にて開催される。
毎年テーマを変え、立方、地方、鳴り物を受け持つ芸妓たちが呼吸を合わせ、華やかで洗練された舞台世界を作り上げる「都をどり」。令和八年は、寛永行幸四百年にちなんだ『寛永行幸都華麗』を上演する。
令和八年 第百五十二回公演「都をどり」 ポスター 原画
寛永行幸とは、徳川幕府の大御所・秀忠と三代将軍・家光が、後水尾天皇を二条城へ迎え入れた際に行われた饗応のこと。朝廷と江戸幕府の融和、そして平和な世の到来を示すために執り行われた、一大行事である。
その寛永行幸から四百年という大きな節目を迎える今年は、二条城を舞台に繰り広げられた華やかな饗応の様子と、寛永文化の気風に思いを馳せる構成となっている。
令和7年公演より(第8景 平安神宮桜雲)
「都をどり」は、明治五年の初演以来変わらず、「ヨーイヤサァー」の掛け声とともに、揃いの明るい浅葱色の着物に身を包んだ踊り子たちが一斉に登場する「総をどり」から幕を開ける。今年もこの「総をどり」を皮切りに、寛永文化と京都ゆかりの風景が、美しい四季のモチーフとともに描き出される。約一時間にわたる舞台のあいだ、一度も幕を下ろすことなく行われる舞台転換も、大きな見どころのひとつだ。
芸妓たちが魅せる華麗な舞はもちろん、毎年新調される京友禅の着物や西陣織の帯の美しさ、三味線・唄・鳴物による生演奏、そして歴史を重ねてきた劇場空間のしつらえまで、見どころは尽きない。
茶券付一等観覧券を購入すると、公演前に、京風島田まげに黒紋付の衿裏返しという正装に身を包んだ芸妓によるお点前を鑑賞し、お菓子と抹茶を味わうことができる。
お茶屋とのご縁がなくとも、誰でも鑑賞できる「都をどり」。うららかな春の京都で、雅な舞の世界に身を委ねてみてはいかがだろうか。
◆都をどり
【会期】2026年4月1日(水)~4月30日(木)
1日3回公演(各公演約1時間)
1回目12:30~ 2回目14:30~ 3回目16:30~
【会場】祇園甲部歌舞練場(京都府京都市東山区祇????園町南側570-2)
【料金】観劇チケット(全席指定・税込)
・茶券付一等観覧席 7,000円
・一等観覧席 6,000円
・二等観覧席 4,000円
・学生料金(二等席限定)2,000円
※公演プログラム 1,000円
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 祇園甲部の芸妓舞妓が華やかに舞う。第百五十二回公演「都をどり」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
神話のふるさと、出雲で良縁を祈る
2026.1.20
「界 玉造」冬限定の特別滞在「八重垣神社開運プラン」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
日本最古の美肌の湯と称される玉造温泉に佇む星野リゾートの温泉旅館「界 玉造」から、縁結びの聖地として知られる八重垣神社での祈願と湯浴みを組み合わせた、期間限定の開運プランが登場。
2月28日まで提供される「八重垣神社開運プラン」は、心身を整えながら良縁を祈る、2日間の“静かな開運旅”。
プランの要となるのは、素盞嗚尊(すさのおのみこと)と稲田姫命(いなたひめのみこと)の夫婦神を祀る、八重垣神社での特別祈祷。界 玉造の宿泊者限定で奏上される祝詞(のりと)によるご祈祷を受けたあと、神職の案内によって国指定重要文化財の壁画を拝観。祈祷後は、占い用紙に硬貨を乗せて占う「鏡の池」での縁結び占いを体験し、運を開くひとときを過ごすことができる。
参拝前には、浄化作用をもち、邪気を払うとされる「真菰(まこも)」を用いたオリジナルのバスセットで湯浴みを。心身を清め、神域へ向かうための身支度を整えたい。
さらに、八重垣神社で授与されたお守りを大切に持ち帰るための、オリジナル勾玉チャーム付きお守り袋も用意。三種の神器の一つとして知られる勾玉は、古来より魔除けや幸運の象徴として親しまれてきたもの。このお守り袋は、松江で142年の歴史を持つ、めのう細工の老舗「秀玉堂」が制作を手がけている。
滞在中には、界 玉造で開催するご当地楽の「石見神楽 大蛇(おろち)」の演舞を最前列で鑑賞できる特別席も用意。この演目は、翌日参拝する八重垣神社に祀られる素盞嗚尊と稲田姫命の神話を描いたもので、参拝前に神話に触れることで、祈りの時間がより立体的な体験へと変わるはずだ。
神話、湯、そして祈りが静かに重なり合い、心身を整える冬の出雲。神話のふるさとならではの開運旅を、ぜひ体験してみてはいかがだろうか。
◆「界 玉造」冬限定の特別滞在「八重垣神社開運プラン」
【期間】2026年1月13日~2月28日
【料金】56,000円~(2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込)
【含まれるもの】祈祷料(撤饌授与品含む)、壁画拝観料、真菰バスセット、オリジナルお守り袋、夕朝食
【場所】界 玉造、八重垣神社
【定員】1組3名まで
【予約】公式サイトにて宿泊7日前までに要予約
※八重垣神社までの送迎は含まれません。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 「界 玉造」冬限定の特別滞在「八重垣神社開運プラン」 は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
富士山から最も近い関東最大級のグランピングリゾート「B&V富士山河口湖」誕生
2026.1.8
富士を望む絶景、バナジウム鉱泉の客室風呂、プライベートサウナを楽しめる新リゾート
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
都心から車で約90分。山梨県の河口湖エリアに、全23棟からなるグランピングリゾート「グランピングB&V富士山河口湖」がオープンした。
最大の魅力は、すべての客室から富士山を一望できる圧巻のロケーション。客室風呂には富士山の深層水を用いたバナジウム鉱泉を配湯し、さらに全棟に完全プライベートサウナを完備。サウナで汗を流した後は、雄大な自然の中での外気浴へとつながり、誰にも邪魔されない没入体験を楽しめる。
スイートヴィラ -プライベートプール付き-
客室タイプは4種類。プール付きの「スイートヴィラ」、少人数からグループに対応する「ドームテント」、最大20名が宿泊できる「ツインドームプレミアム」、そして500㎡の専用ドッグランが隣接する「ドッグキャビン」が揃う。
なかでも8棟ある愛犬同伴可能なドッグキャビンは、リードフリーで過ごせる広大なドッグランと、サウナ・バス・トイレ付きのキャビンを備え、飼い主の安心と愛犬の自由を両立している。
食事は、富士山麓で育てられたブランド牛「富士山黒牛」のステーキをメインに、旬の野菜やスープ、デザートを組み合わせたメニューを提供。冬季限定では「甲州牛」「甲州信玄豚」を用いたすき焼きが登場し、山梨の味覚を堪能できる。
さらに管理棟には、ドリンク飲み放題のBARスペースを完備。各棟には焚き火を楽しめるファイヤーピットも設置され、焚き火のぬくもりと満天の星空を同時に楽しめる、贅沢なひとときを過ごすことができる。
富士山を独り占めできる絶景ロケーションが広がる新リゾート。家族や愛犬とともに、開放的な滞在を楽しんでみては。
◆グランピングB&V富士山河口湖
【住所】⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町富⼠ヶ嶺1188-1
【アクセス】
[中央自動車道(東京)方面]河口湖ICから約30分
[新東名高速道路(静岡)方面]新富士ICから60分
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 富士を望む絶景、バナジウム鉱泉の客室風呂、プライベートサウナを楽しめる新リゾート は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
「星のや軽井沢」自分をリセットする冬の温泉滞在
2026.1.7
冬の森×源泉かけ流し。静寂の温泉リトリートを提供
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
都会で忙しく過ごす日々のリズムを、深い静寂に包まれる地で静かに調え直す――。長野県 浅間山麓の谷に広がる「星のや軽井沢」では、身も心も温まる冬限定の温泉滞在を提供している。
星野温泉 トンボの湯 露天風呂
時間:9:00~22:00(最終入場:21:15) 料金:無料 予約:不要
※9:00~10:00は宿泊者専用時間
メディテイションバス
時間:15:00~翌10:00 料金:無料 予約:不要
本滞在の中心となるのは、趣の異なる二つの源泉かけ流し温泉で叶える贅沢な温泉体験だ。「星野温泉 トンボの湯」では、雪景色を望む露天風呂と内湯で開放的な冬の入浴を楽しめる。一方、宿泊者専用の「メディテイションバス」では、光と闇の陰影が織りなす静寂の空間で、自身と向き合う特別な時間を過ごすことができる。
「星見湯治」
時間:19:30~21:30 料金:無料 予約:不要
また、高台にあり満点の星を眺められる「メディテイションバス」のテラスでは「星見湯治」を開催。温かいすり流しを味わいながら、降り注ぐような星の輝きを堪能できる。
「森のほとりCafe&Bar」
時間:20:00~23:00 料金:有料 予約:公式サイトにて当日20:00まで受付
池が凍り、スケートリンクに様変わりした景色が広がる「森のほとりCafe&Bar」では、薪ストーブの炎が揺らめく空間で、ゆったりとした夜のひとときを過ごすことができる。
「のびのび深呼吸」
時間:8:00~8:40、8:45~9:25(全2回) 料金:無料 予約:公式サイトにて前日19:00まで受付
さらに朝には、雪景色の中でストレッチを行い心身を整える「のびのび呼吸」を開催。新鮮な空気を取り込み、身体を内側から温めることで清々しい一日の始まりを迎えられるはずだ。
「棚田アフタヌーンティー」
時間:13:00~15:00 料金:1名12,000円 予約:公式サイトにて5日前まで受付
星のや軽井沢を象徴する棚田の景色を一望できる「棚田ラウンジ」は、冬限定で炬燵席に変わり、1日1組限定のアフタヌーンティーを提供。信州ならではの食材を使った和菓子を、オリジナルシールドとともに味わうことができる。
星のや軽井沢「山路地の部屋」
2つの源泉と澄んだ空気が導く温泉リトリート。新しい一年を迎えるにあたり、冬の軽井沢の澄んだ空気の中で、心身を整えてみてはいかがだろうか。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 冬の森×源泉かけ流し。静寂の温泉リトリートを提供 は Premium Japan に最初に表示されました。
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
2025.12.27
人生一度は訪れたい伊勢神宮 Premium Japanがおすすめする参拝とは?
内宮のお参りは宇治橋から。五十鈴川を渡る前に、まず1礼。この鳥居は外宮の旧御正殿の棟持柱を用いている。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
今年、2025年の1月から始まった当連載も、いよいよ最終回。これまでさまざまな視点で、ときに式年遷宮のおまつりに触れながら伊勢の神宮について紹介してきた。今回はその締めくくりとして、ちょっとツウなお伊勢参りを提案したい。改めて参拝方法について整理し、またお伊勢ファンには人気のある遙宮(とおのみや=伊勢から遠く離れた別宮)の瀧原宮(たきはらのみや)、伊雑宮(いざわのみや)も含めた別宮(べつぐう)にも焦点を当て、ご紹介しよう。
お伊勢参りは外宮からはじめる
お伊勢参りは、できれば午前中、それも早朝に行いたい。朝一番の生まれたての光に包まれた神域は、すがすがしさや神々しさが一段と際立って感じられる。
まずは、外宮先祭(げくうせんさい=外宮で先におまつりが行われること)のならわしに倣って、皇大神宮(内宮)より先に豊受大神宮(外宮)を参拝。正門の火除橋を渡って、いざ神域へ。頭上を覆う木々の緑と、ところどころに木漏れ日が差し込む豊かな森に包まれた参道を進むごとに、不思議と心が落ち着いてくる。
お参りは、参道の左側にある手水舎から始まる。柄杓で掬った水で手と口を清め、日々の暮らしで知らず知らずのうちに身に付いてしまった、目には見えない穢れを流し、清浄にするのだ。身体の外を表す手と、身体の中を表す口、両方を清めることによって、心身の禊を行っていると考えられている。
外宮の御敷地(みしきち=次の式年遷宮で御正殿が造営される場所)に立つ大木。
参道を歩くときに気をつけること
外宮の参道は、手水舎が左側にあるため左側通行。右手にある御正宮に対し、遠い側を歩くという敬虔な気持ちを表しているとも言われている。
ちなみに、参道の中央を人が通るのは遠慮した方がよいとされている。
「室町時代の書物『参拝式類聚(さんぱいしきるいじゅう)』にも、参拝作法の心得として、参道の真ん中––––正中(せいちゅう)と言いますが––––を通るときは、慎みの心を持つようにと書かれています。
そもそも参道の正中は、昔は少し高くなっていて、おまつりのときに天皇陛下に代わって、陛下の祈りを捧げる勅使がお通りになる、『置道(おきみち)』と呼ばれる道がありました。ですから、正中は尊いところであり、絶対通ってはいけないというわけではないけれども、通るときは慎みの心が必要だとする考え方が、古くから伝わってきたのでしょう。それが、やがて神様の通り道という信仰的なものに変わっていった。おそらく日本人は、正中には何か特別な、敬虔な気持ちにさせるものがあると、古来感じてきたのだと思います」。
神宮の広報室次長の音羽悟さんは言う。
参道を歩くときは、足元の小さな自然や生き物にも目を向けながら、ゆっくりと。
もっとも、御正宮でのお参りに関しては、
「真ん中でされたいと思われるのは当然ですし、みなさん敬虔な気持ちでお参りされると思いますから、間違ったことではないと私は思います」
外宮の別宮をお参りしよう
御正宮のお参りの後は、外宮の別宮である多賀宮(たかのみや)へ。別宮とは、御正宮に対する「わけ(別)のみや(宮) 」という意味で、御正宮に次いで格式が高いとされている。
ちなみに、一般の神社でも、「宮」は「社」よりも格上の存在。古くは天皇陛下より、「社」から「宮」への昇格を認める「宮号宣下(きゅうごうせんげ)」が下されて、はじめて「宮」を名乗ることができたという。
特に多賀宮は、外宮の主祭神、豊受大御神の荒御魂(あらみたま=ときに臨んで、格別に顕著な神威をあらわされる御魂のお働きを指す)をお祀りする、外宮第1の位にある別宮。外宮創建と同時にお祀りされ、豊受大御神と御一体の関係にあるとされている。
もとは「高宮(たかのみや) 」と称され、社殿は100段近くある急な階段を登った小高い丘の上にあるが、ぜひお参りしたいお宮である。
参道から頭上を見上げる。
外宮の別宮、土宮は、なぜ神宮の中で唯一東を向いているのか
多賀宮の下には、やはり外宮の別宮、土宮(つちのみや)と風宮(かぜのみや)が御鎮座。
土宮には、古くは外宮のある山田原の鎮守の神で、外宮創建後は、宮域の地主神になったという神様が祀られている。
「土宮の社殿は、神宮の中で唯一東に向いていますが、これは御祭神が東を向いているわけではないんです。よく神様はどちらを向いていらっしゃるんですかと聞かれるのですが、神様は大地に根付いてその土地を守っていらっしゃって、一方向だけでなく全体を見渡していらっしゃるんです。
大事なのは、お祀りする側がどちらの向きに祈りを捧げるかで、土宮の場合は西、つまり宮川の方を向いています。古来宮川水域は肥沃な土地でありながら、氾濫による被害に悩まされていたことから、鎮守の神として、宮川に敬意を表するようにお祀りされたのでしょう」。音羽さんは言う。
一方、風宮には、風雨を司る神様がお祀りされている。
ちなみに、両宮が別宮に昇格したのは、神宮のなかでは比較的新しく、土宮は大治3年(1128)、風宮は正応6年(1293)のことという。
夜之食国(よるのおすくに)を治める神様をお祀りする外宮の別宮
別宮のお参りの後は、北御門(きたみかど)から宮域を出て、そのまま北へ。神路通りという名の道を300mほど歩くと、こんもりした森が見えてくる。外宮の別宮、月夜見宮(つきよみのみや)である。
この別宮の御祭神は、月夜見尊(つきよみのみこと)と月夜見尊の荒御魂(あらみたま)。
外宮の別宮、月夜見宮にある楠の大木。伊勢市駅からも近いながら、豊かな森が広がる。
『古事記』や『日本書紀』によれば、月夜見尊は、御祖神(みおやがみ)である伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が海で禊をされたときに、天照大御神に次いでお生まれになった弟神とされている。このとき右目からお生まれになった姉神、天照大御神は、神々の世界である高天原を、左目からお生まれになった月夜見尊は、夜之食国(よるのおすくに)を治めるよう、伊弉諾尊から委任されたという。
ここまでお参りしてきた別宮の名称に付く「土」、「風」、「月」、そして、内宮にお祀りされている神宮の主祭神、天照大御神の象徴として例えられる「太陽」……。お伊勢参りは、常日頃存在して当たり前だと思っている、さまざまな自然に対する感謝を捧げる行為かもしれないと、ふと思う。
内宮のお参りの前に、内宮の別宮、
倭姫宮(やまとひめのみや)と月読宮(つきよみのみや)以下4別宮のお参りを
さて、お伊勢参りは外宮から内宮へ。もっとも、その途中には、内宮の別宮である倭姫宮(やまとひめのみや)と、月読宮(つきよみのみや)など4つの別宮が御鎮座している。
倭姫宮の御祭神である倭姫命(やまとひめのみこと)は、天照大御神の御鎮座の地を求めて、大和(現在の奈良県)の笠縫邑(かさぬいむら)から、天照大御神の御杖代(みつえしろ=神の杖の代わりとなって奉仕する者)となって各地を巡行されたと伝えられる、第11代垂仁天皇の皇女。
その後、天照大御神の御神託により、倭姫命は現在の伊勢の地に御鎮座の地をお定めになったが、功績はそれだけではない。天照大御神へのお供え物である御料や、お米をはじめとする野菜、果物、海産物といった神様のお食事である神饌の内容、さらに、その御料を調達する場所までお定めになったほか、神嘗祭などの祭祀や奉仕者の職掌など、神宮の経営の規模や組織に関わる基礎を確立されたと伝えられている。
倭姫宮の春の大祭の様子。倭舞や舞楽が奉納される。なお、倭姫宮の創立は、神宮の緒宮社のなかでも格別に新しく、大正10年(1921)。近くには、神宮のおまつりに関する資料や重要文化財を展示する神宮徴古館などもある。
しかも、鎌倉時代初期には『倭姫命世紀(やまとひめのみことせいき) 』が編纂され、倭姫命の巡行地の詳細やその教えが、後世に伝え継がれることとなった。
教えのなかには、たとえば、人の心のなかにはもともと神が存在し(=「心神」 )、その心のなかの神を、汚すことなくそのままに生きる姿(=「正直」 )が理想とされている。だが、日々の生活のさまざまな雑念や私欲によって、穢れはどうしても生じるもの。その穢れを祓によって清め、本来の境地である「清浄(しょうじょう) 」に戻す、というような、参拝の意義について、一般の我々にも参考になる内容も盛り込まれている。
一方、月読宮の御祭神は月読尊。外宮の別宮、月夜見宮の御祭神と漢字こそ違うものの同じ神様で、月の満ち欠けを司るとともに、月齢を読むという解釈から、暦をもたらすと考えられている。
加えて、月読宮の左隣には、月読尊の荒御魂がお祀りされている、月読荒御魂宮(つきよみあらみたまのみや)の社殿。
神域には、ほかにも月読尊の御親神である伊弉諾尊をお祀りする伊佐奈岐(いざなぎの)宮と、その妻(ただし、月読尊がお生まれになったときはすでに他界し、黄泉の国にいた)の伊弉冉尊(いざなみのみこと)をお祀りする伊佐奈弥(いざなみの)宮もあり、4つの社殿が横1列に建ち並んでいる。
なお、ご神名に「尊」が付くのは、『日本書紀』に「至って尊きを尊(みこと)といい、その他を命(みこと)という」の記述に則ってのことだという。
内宮のすがすがしい空気を五感で感じたい
内宮のお参りでは、まず宇治橋の鳥居に注目したい。五十鈴川の手前にある鳥居は、外宮の旧御正殿の屋根を支えていた棟持柱(むなもちばしら)。橋を渡り切ったところにある鳥居には、内宮の、やはり旧御正殿の棟持柱が使われている。
内宮は、外宮と逆で右側通行。
参道の右手に現れる御手洗場(みたらし)で、俗世の垢を祓った後は、別宮ではないものの、祭祀に関しては別宮に準じて執り行われるという五十鈴川の守り神、瀧祭神をお参りしよう。
御正宮をお参りした後は、天照大御神の荒御魂をお祀りする内宮の別宮、荒祭宮(あらまつりのみや)と、風日祈宮(かざひのみのみや)へ。神域のすがすがしさを五感で感じたい。
内宮の別宮、風日祈宮へ向かう際に渡る風日祈宮橋。内宮は右側通行が基本だが、この橋に限り、神職など神宮関係者は左を歩く。
早朝の神域に、清らかな陽の光が降り注ぐ。
お伊勢ファンに人気の高い内宮の別宮で、
遙宮(とおのみや)と呼ばれる瀧原宮(たきはらのみや)と伊雑宮(いざわのみや)
さらに、お伊勢ファンなら1度はお参りしたいのが、内宮の別宮で、遙宮(とおのみや)とも呼ばれる瀧原宮(たきはらのみや)と伊雑宮(いざわのみや)。ともに天照大御神をお祀りしている。
瀧原宮の御鎮座は、約2000年前まで遡る。前述の『倭姫命世紀』によれば、倭姫命が天照大御神の御鎮座の地を求めて、宮川の下流から上流へ向けて進まれたときに、「大河之瀧原国(おおかわのたきはらのくに)」という麗しい土地があり、神殿を造立されたのが起源という。
瀧原宮の宮域にある御手洗場。頓登(とんど)川は、宮川に合流する大内山川の支流。この川を伝って、古くから南方との交通が行われていたという。
瀧原宮の社殿。左には、瀧原竝(たきはらのならびの)宮が並んで御鎮座。2宮並べてお祀りするのは、内宮の御正宮で天照大御神を、荒祭宮で天照大御神の荒御魂をお祀りする形態の古い姿とも言われている。
樹齢数百年の杉の大木が立ち並ぶ参道、その脇を流れる頓登(とんど)川の清らかな水と御手洗場。内宮の佇まいを彷彿とさせながらも、お参りする人はさほど多くなく、ゆっくり参拝できるのも魅力である。
一方伊雑宮は、伊雑の浦にも近い三重県志摩市に御鎮座する別宮。
天照大御神が伊勢の地に御鎮座された後、倭姫命が天照大御神へのお供え物を採る御贄地(みにえどころ)を定めるために、志摩の国を巡行した際、伊佐波登美命(いざわとみのみこと)が豊かに稔った稲を奉ったことがきっかけで、創建されたという。
現在も、当宮の御田植式は有名で、千葉の香取神宮、大阪の住吉大社とともに、日本3大御田植祭の1つに数えられ、国の無形文化財に指定されている。
伊雑宮の宮域にある古木。さほど広くはないが、風格があるお宮。
伊雑宮の御田植式は、「おみた」とも呼ばれ、郷土色豊かな内容。褌(ふんどし)1つの青年たちによる竹取の神事が終わった後、太鼓やササラ、笛などが奏でる田楽の調べに合わせて、早乙女が田植えを行う。
そもそも志摩の国は、『古事記』にも「島の速贄(はやにえ=志摩から朝廷に納められる初物の海産物) 」として登場するなど、古くから御食都国(みけつくに)として知られた地。神宮でも、この地の鮑を神嘗祭などの三節祭でお供えするよう、延暦23年(804)編纂の『皇太神宮儀式帳』で指定されているという。
知れば知るほど奥深い神宮の世界。興味は尽きないが、ひとまずこれで区切りとしたい。なお、神宮では大晦日の夜から「どんど火」と呼ばれる大かがり火が1晩中焚かれ、内宮、外宮ともに、12月31日の朝5時から1月5日の20時まで、夜間を含めて終日参拝が可能という。一般でも夜間参拝が叶う貴重な機会。ぜひお参りをしたい。
伊勢地方の注連縄。1年中飾るのが特徴。
年に数度、お伊勢参りをするようになって10数年。なぜこんなにもお伊勢さんに惹かれるのか、自分でもよくわからない。強いて言えば、理由なく足を運びたくなる。それがお伊勢さんの魅力かもしれない。何より、感謝の気持ちのみを捧げるお参りは、あれこれお願いばかりするよりも、ずっと爽快で、心根にさっぱりとした感覚を残す。
頭で理解するのではなく、目と心、そして耳を澄ませて日々の自分をリセットする、そんなお伊勢参りを、これからも続けていけたらと思っている。
Text by Misa Horiuchi
伊勢神宮
皇大神宮(内宮)
三重県伊勢市宇治館町1
豊受大神宮(外宮)
三重県伊勢市豊川町279
文・堀内みさ
文筆家
クラシック音楽の取材でヨーロッパに行った際、日本についていろいろ質問され、<wbr />ほとんど答えられなかった体験が発端となり、日本の音楽、文化、祈りの姿などの取材を開始。<wbr />今年で16年目に突入。著書に『おとなの奈良 心を澄ます旅』『おとなの奈良 絶景を旅する』(ともに淡交社)『カムイの世界』(新潮社)など。
写真・堀内昭彦
写真家
現在、神宮を中心に日本の祈りをテーマに撮影。写真集「アイヌの祈り」(求龍堂)「ブラームス音楽の森へ」(世界文化社)等がある。バッハとエバンス、そして聖なる山をこよなく愛する写真家でもある。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
Premium Calendar
関連記事
投稿 人生一度は訪れたい伊勢神宮 Premium Japanがおすすめする参拝とは? は Premium Japan に最初に表示されました。
Lounge
Premium Salon
京都通信
2025.12.25
京都のゆく年くる年──年越しからお正月まで暮らしの中に息づくしきたり
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
こうした習わしに込められた意味を知ることで、京都の年の瀬と新年を、より深く、豊かに味わうことができるでしょう。
京の年越し──をけら詣りと除夜の鐘
大晦日の夜、八坂神社ではその年最後の神事・除夜祭が執り行われたあと、境内に設けられた灯籠に「をけら火」が夜を徹して焚かれます。この火をいただくための参拝が「をけら詣り」です。
をけらとは、キク科の薬草「白朮(おけら)」のこと。燃やすと独特の強い香りを放つことから、古くから邪気を払う力があるとされてきました。
大晦日の夜に焚かれる「をけら火」。をけら詣りは八坂神社のほか、北野天満宮でもできる。
この白朮と護摩木をくべた灯籠の火を火縄(吉兆縄)に移して持ち帰り、神棚の灯明やお雑煮の火種に使うことで、1年の無病息災を祈願するのです。火が消えないように縄をくるくる回しながら歩く人々の姿は、京都の年越しの風物詩。燃え残った火縄は火伏せのお守りとして、台所に祀られます。
夜が更けるにつれ、聞こえてくるのは除夜の鐘の音。17人僧侶が「えーいひとつ」「そーれ」の掛け声のもと大きな梵鐘を打ち鳴らす知恩院のものが有名ですが、約1700もの寺院があるといわれる京都市内では、まちのあちこちで鐘が撞かれます。
しんと静まりかえった夜に響く鐘の音とその余韻が冷えた空気に溶け込んで、静かに年が改まっていくのを感じさせてくれます。
年の瀬から新年へ──にしんそば・大福茶
京都のそばと聞いて、にしんそばを思い浮かべる人も多いでしょう。甘辛く炊いた身欠きにしんをのせた一杯は、京都の年越しの定番として広く親しまれています。でもなぜ、海から遠い京都で「にしん」なのでしょうか。
流通の少ない時代、北海道から北前船で運ばれてくる「身欠きにしん」などの干魚類は、新鮮な魚介類が手に入りにくかった京都の人々にとって貴重なたんぱく源。保存が利くため、おばんざいの食材としても使われるなど、京都の食文化と深く結び付いてきたのです。
にしんそばが生まれたのは明治時代。祇園・南座の隣にある蕎麦屋「松葉」が発祥とされている。
新しい一年の始まりに「大福茶(おおふくちゃ)」をいただくのも、京都ならではの習わし。
梅干しと結び昆布を入れたこのお茶は、古くから伝わる縁起もの。平安時代に京都で流行した疫病を、六波羅蜜寺の空也上人が梅干し入りの薬茶を振る舞って鎮めた故事にちなんで、一年を元気に過ごせますようにという願いが込められています。
正月を迎える京の味──白味噌雑煮と花びら餅
元日の朝、台所から漂ってくるのは白味噌のやさしい香り。地域によって雑煮のかたちはさまざまですが、京都は茹でた丸餅と頭芋、大根、金時人参などを入れた白味噌仕立ての雑煮が定番です。
汁はポタージュのように濃厚でまろやか。甘みのある白味噌と、やわらかく煮た具材が合わさり、体にすっとなじんでいく、上品で味わい深いお雑煮です。
うっすらと透けて見える淡いピンクが、新春の華やぎを感じさせる「花びら餅」
お正月の縁起菓子にも、白味噌の風味をいかしたものがあります。白味噌餡と蜜煮にしたごぼうを、やわらかな求肥や羽二重餅で包んで半月状に折った「花びら餅(菱葩餅)」です。
その由来は、平安時代の宮中で行われた正月行事「歯固めの儀式」。鏡餅、大根、押鮎(塩漬けした鮎)、橘などを食べて歯の根を固め、長寿を願う儀式で、この歯固めの品が「菱葩(ひしはなびら)」という餅に変化。それが花びら餅の原形になっています。
新年の装い──根引きの松と正月飾り
年の瀬からお正月にかけて、京都のまちを歩いていると、家々の軒先に松が掛けられているのに気づきます。根を残したままの松を、和紙や紅白の水引などで飾ったお正月飾り「根引きの松」です。
京都で最も多く見られるお正月の玄関飾り「根引きの松」。門松の原型だといわれている。
根をつけたままなのは「地に足をつけ、成長し続けられるように」という願いが込められているから。生命力の象徴とされ、新しい年に歳神様を迎える依り代として用いられてきました。
自然な枝ぶりをいかしたその姿は、門松と比べると随分控えめ。新しい一年を静かに迎える心持ちにふさわしい凜とした美しさが宿っています。
松や注連縄、裏白など、それぞれに由来があり、願いが込められているお正月飾り。こうしたお正月の装いは、華美でも目立つものでもありません。それでも、年の変わり目をきちんと受け止めるために欠かせない行いなのです。
Text by Erina Nomura
野村枝里奈
京都在住のライター。大学卒業後、出版・広告・WEBなど多彩な媒体に携わる制作会社に勤務。2020年に独立し、現在はフリーランスとして活動している。とくに興味のある分野は、ものづくり、伝統文化、暮らし、旅など。Premium Japan 京都特派員ライターとして、編集部ブログ内「京都通信」で、京都の“今”を発信する。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Lounge
Premium Salon
京都通信
Premium Salon
関連記事
投稿 京都のゆく年くる年──年越しからお正月まで暮らしの中に息づくしきたり は Premium Japan に最初に表示されました。
Stories
Premium X
日本のプレミアムなホテル
2025.12.11
「ヒルトン京都」で大人の京都ステイを イタリアの温もりを届ける“オステリア”がオープン
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
JR京都駅から車で約15分、市内中心部「河原町三条」に位置する「ヒルトン京都」は先斗町や祇園は徒歩圏内、世界遺産の二条城や清水寺にも近く、観光やビジネスに便利なロケーションにある。歴史ある街の魅力が漂う中、現代的で洗練されたデザインを融合させた「ヒルトン京都」は、まさに大人の京都滞在にふさわしいホテルである。
京都の風情あふれる街並みに建つ「ヒルトン京都」。
5フロア吹き抜けのロビーには、織物の「織り糸」をモチーフにしたデザインが施されている。
館内のコンセプトは「京都SYNAPSEシナプス 」。
京都の歴史や伝統、革新、さまざまな魅力をつなぐという想いが込められており、その哲学はホテル全体に反映されている。チェックインを済ませ、吹き抜けの天井を見上げれば、壁面に張り巡らせた糸が織りなす壮麗なデザインが目に入る。
デザインテーマ「ORIMONO織物 」を象徴し、ロビーの片隅にある織り機から糸が空間全体に広がるアートは、まるで京都の伝統技術の物語に包まれているかのようだ。この美しく洗練された空間を手掛けたのは空間デザイナー故・橋本夕紀夫氏。橋本氏のデザイン哲学が至る所に反映されている。
日本の美意識が宿る客室は心地よく、自身の原点を思い起こす
客室は全313室、スタンダードルーム約40㎡からスイートルーム121㎡まで全16タイプ。木のぬくもりが感じられる和のインテリアに、京都の地図を表現したカーペット、大きな窓に設えられた障子など、日本人にとって懐かしく、訪れる人に安らぎを与える空間だ。
畳空間もある「キング京都スイート」。
独立したベッドルームとリビングルームを備えた「キングデラックススイート」。
9階にあるエグゼクティブルームやスイートルーム宿泊者専用のエグゼクティブラウンジは、京都の町家の路地を思わせる通路の奥にある。チェックイン・チェックアウトのほか、朝食、リフレッシュメント、イブニングカクテルをゆったり楽しめる。
この空間や食事などを自由に使えるメリットだけを考えても、エグゼクティブルームやスイートルーム利用が絶対におすすめであると言えるだろう。
9階エグゼクティブフロアのエレベーターホールから中庭を見る。
落ち着いた空間のエグゼクティブラウンジ。
館内の魅力は宿泊だけにとどまらない。
1階にはオールデイダイニング「Téoriテオリ 」、ロビーラウンジバー「LATTICE LOUNGEラティス ラウンジ 」があり、京都老舗「小川珈琲」のオリジナルブレンドや季節のアフタヌーンティーが楽しめる。ペストリーシェフが心を込めて仕上げるフォトジェニックなスイーツ9種とセイボリー4種は見た目も美しく、宇治の日本茶やこだわりの和紅茶とも相性抜群だ。
「ラティスラウンジ」ではアフタヌーンティーも楽しめる。
手作りにこだわったビュッフェが楽しめるオールデイダイニング「テオリ」。
さらにおすすめしたのが隠れ家的な9階のルーフトップバー「CLOUD NEST ROOFTOP BARクラウドネスト・ルーフトップバー 」だ。夕暮れどきの美しい京都市街の景観を楽しみながら、カクテルや軽食、ノンアルコールドリンクを堪能できるのは、知る人ぞ知るスポットである。
季節営業の「クラウドネスト・ルーフトップバー」のおすすめはオリジナルのピニャ・コラーダ。ドリンクのほか軽食やスイーツも楽しめる。
宿泊体験のもうひとつの魅力は、国内初となるヒルトンのスパブランド「eforea SPAエフォリア スパ 」。
北山杉やクロモジなど京都産天然素材から抽出したオリジナルオイルを使用し、フェイシャル、ボディ、フットケアなど豊富なメニューを揃える。宿泊ゲストはペアルームの利用も可能で、日常から解放された贅沢な時間を過ごせる。
国内初のヒルトンオリジナルスパブランド「エフォリア スパ」。ヒノキ風呂を備えたペアルーム。
イタリアの情熱と温もりを届ける、国内ヒルトン初の新コンセプト「オステリア」
2025年秋、1階に南イタリアの温もりあふれるダイニング「オステリア イタリアーナ セブン・エンバーズ」が誕生した。
エグゼクティブシェフを務めるのは、イタリア政府より「ユネスコ世界遺産・イタリア料理のアンバサダー」の称号を授与された、マリアンジェラ・ルッジェーロ氏だ。イタリア出身のエグゼクティブシェフが手掛けるオーセンティックイタリアンの世界観は国内ヒルトンでは初の挑戦だ。
エグゼクティブシェフのマリアンジェラ・ルッジェーロ氏。
「ヒルトン京都は『お客様のお声を大切に聞く』ということを理念のひとつに持つホテルです。ゲストの声はもちろん、品質へのこだわり、心のこもったおもてなしなどを体現するのにふさわしいスタイルを追求したとき、さらにイタリアの情熱と温もりと伝えることを考えると、“オステリア”が最適であると考えました」と語る。
“オステOste”という言葉は、イタリア語で“おもてなしする人”を意味する。
ここでは、心を込めた温かなおもてなしや、胸躍る食体験、笑顔と愛があふれる時間を過ごすことができ、毎日手作りされるフレッシュパスタや窯で焼き上げるピッツァなど、世代を超えて受け継がれたレシピに基づく心温まるメニューの提供をするなど、人々のつながりや温もりに包まれることができる。これこそがヒルトン京都が目指すオステリアなのである。
内装や雰囲気も気負いなく安らげる空間となっている。
「ヒルトン京都を訪れるお客様は、料理にも高い期待をお持ちです。その期待に応えるために、“本物”の味を届けたいと考えました」。
オーセンティックイタリアンが意味する本物とは、食材や季節、そして一緒に食卓を囲む人々への敬意が根ざしたものであり、それはイタリアの家庭の味や温もりの記憶と結びつくものである、とルッジェーロ氏は考えている。本場イタリアの技法を礎にしつつ、今回初めて自身の故郷に伝わる“ファミリーレシピ”をメニューに取り入れた。
「祖母がいつも作ってくれたCavatelli al Ragù di Maiale della Nonna豚肉のラグーソースのパスタや、Polpette al Sugoじっくり煮込んだトマトソースで仕上げるミートボールをはじめ、家族に受け継がれてきた味をヒルトン京都で提供できることは、私のルーツの一部をゲストとシェアすることであり、それは大きな喜びです」と話す。
パルミジャーナ・ディ・メランザーネ手前、カヴァテッリと京丹波高原豚ラグーソース添え中央。
気心の知れた仲間とワイワイ食べたい、窯焼きの手作りピザ。
メニューには、手打ちパスタに京丹波高原豚の旨みを絡めた「カヴァテッリ 京丹波高原豚のラグー」、京都ポークでとろけるチーズを包み香ばしく焼き上げた「プーリア風ボンベッテ」、淡路産モッツァレラとサン・マルツァーノによるナポリ名物「揚げピザ」など、世代を超えて受け継がれたノンナイタリア語でおばあちゃんの味に、京都の食材とシェフの感性を掛け合わせた料理が並ぶ。
「一度だけ訪れる特別なレストランではなく、何度でも来たくなる場所。そして京都から料理が文化の架け橋となることを示すと同時に、伝統に根ざしながらも本物の食体験を提供したい」とルッジェーロ氏の熱い思いを語った。
イタリア料理の真髄である、“食卓を囲む”“料理や喜びの感情などを分かち合える喜び”これらを共有することだとも語る。
「たとえばピザだけ食べたくてふらっと来る、家で食卓を囲むような気軽やさ温もりのあるオステリアでありたいですね。大切なのは“食卓を囲む喜び”を感じていただくことですから」。
もちろんドリンク類もイタリアのものを中心に揃えている。本場イタリアのワインやビールなど、イタリアの雰囲気を存分に楽しめるラインナップになっている。
そして最後にルッジェーロ氏は、レストランが掲げるテーマをこう締めくくってくれた。
「Soul of Italy × Elegance of Kyoto」
イタリアの魂と、京都のエレガンス——「その融合による、忘れられないダイニングエクスペリエンスを」と。
ヒルトン京都の滞在は、客室やラウンジ、スパ、レストランを通して、京都の文化と世界の魅力が調和した特別な時間を提供している。京都観光の拠点としてはもちろん、宿泊者が日常を忘れて心からリラックスできる、そんな空間と時間が約束されている。
京都滞在の楽しみがまた一つ増えた。
Text by Yuko Taniguchi
京都府京都市中京区下丸屋町416番地
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Stories
Premium X
日本のプレミアムなホテル
Features
富士山麓で旧年を振り返り、新年の幸福を願う
2025.12.17
星のや富士の滞在プログラム「富士山麓の開運ステイ」を今冬も開催
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
古来より信仰の対象とされてきた富士山の麓に位置する「星のや富士」では、2026年2月28日までの期間、新年の幸福を願い心身を整える特別なプログラム「富士山麓の開運ステイ」を実施中だ。
「富士山麓の開運ステイ」で提案するのは、自然と向き合いながら一年を振り返り、新たな年を清らかな気持ちで迎えるための滞在体験。
チェックイン当日は焚き火を囲みながら一年を振り返り、翌日の富士山最古の神社への参拝に向けて心を整える新プログラム「開運のひととき」を体験。山梨の正月行事「どんど焼き」に習い、繭玉団子を火で焼き、お汁粉として楽しみ、さらに地元の織物を使用した御朱印帳づくりを行う。
滞在2日目の早朝には、河口湖で「日の出カヌー」に出発。冬の澄んだ空気の中、波ひとつない湖面に漕ぎ出し、刻々と色を変える日の出を眺めながら特製の甘酒ドリンクをいただく。静寂に包まれた湖上で迎える朝は、新しい年への気持ちを整える時間となるはずだ。
翌日は、富士山最古の神社「冨士御室浅間神社」を参拝。祈祷と御朱印を受けることで、新しい年の幸福を願う。
参拝後には、河口湖を望むキャビンで「開運朝食」を味わう。若桃や煮鮑など縁起の良い食材を使った小鉢に加え、“ごぼう”や“蓮根”などを組み合わせた温かい「みみほうとう」などが並び、新年への活力を与えてくれる。
自然、祈り、食を通して一年の節目と向き合う「富士山麓の開運ステイ」。霊峰富士のそばで迎える静かな新年は、心を整えたい大人にこそふさわしい滞在となりそうだ。
◆星のや富士「富士山麓の開運ステイ」
【期間】2025年12月1日~2026年2月28日
【料金】1名35,000円(税・サービス料込)
*宿泊料別、交通費別
【含まれるもの】開運のひととき、御朱印帳、日の出カヌー、ドリンク、冨士御室浅間神社での祈祷、開運朝食
【予約】公式サイトにて2週間前まで受付
【定員】1日1組(2~3名)*小学生以上
※仕入れ状況により料理内容や食材の産地が一部変更になる場合があります。悪天候の場合は、内容を一部変更、中止します。プログラム内容は予告なく変更をする可能性があります。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
関連記事
投稿 星のや富士の滞在プログラム「富士山麓の開運ステイ」を今冬も開催 は Premium Japan に最初に表示されました。
円安でも物価が安く、多文化が共存するマレーシア。おおらかな国民性に癒やされ、デジタル化で旅もスムーズ。2026年の国家的な観光イヤーに向けて、国をあげて歓迎ムードが高まっています。今こそ訪れたいマレーシアのリアルをリポートします。
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
2025.12.5
伊勢神宮 日本人の心が宿る「神宮の森」が意味すること
宮域林のそばを流れる沢。肥沃な土壌に濾過されてミネラル分を多く含む水は、澄み切って頭上の木々を水面に映す。
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
伊勢の神宮の今回のテーマは、神宮を支える豊かな自然。なかでも、参拝者には目に触れにくい存在ながら、“神宮の森”として知られる広大な宮域林に焦点を当て、この森がどのように神宮の営みを支え、式年遷宮に欠かせない役割を担っているかを紹介していく。
内宮の大鳥居をくぐり、宇治橋を渡るとき、いつも1度は足を止め、五十鈴川の清流を眺めて深呼吸をする。背後には、季節ごとに色や趣を変える神路山(かみじやま)。
神宮の豊かな自然は、心身をあるべき姿に落ち着かせるようなリセット作用があるように思う。
お伊勢参りの目的は、もちろん伊勢の皇大神宮(内宮)の主祭神であり、皇室の御祖神で、私たち日本人の総氏神でもある天照大御神に、これまで、何はともあれ無事に暮らせてきたことへの感謝を捧げること。
その一方、たとえば長い参道を歩くときに目に入る大木や、五十鈴川の清流、さらにご正宮をお守りするようにそびえる山々など、周囲のさまざまな自然に目を向け、耳を澄ませて心を開くことで、日々の暮らしでささくれ立ち、淀みがちになっていた心身にすがすがしい風を通して、まっさらな状態になる、そんな効果があるようにも感じている。
神路山の剣峠から南方の宮域林を望む。
“神宮の森”と呼ばれ、広大な面積の神宮の宮域林の役割
神宮の宮域林は、全部で5,500ha。東京都世田谷区とほぼ同じで、伊勢市の4分の1に当たる広さがある。
一般に神宮林とも呼ばれるこの宮域林は、内宮を取り囲むように南側に広がり、3つの区域に分けられている。
1つは、内宮や外宮の神域のように、風致を守り、手入れをする区域。2つめは、宇治橋付近から見渡せる山全体に当たり、できるだけ「自然のまま」が保たれるよう、たとえば枯れた木を取り除くなど、樹木の生育に差し障りがある場合を除いては、極力手を入れない区域で、両者は合わせて第1宮域林と呼ばれている。
一方3つめは、2、300年の長い年月をかけ、式年遷宮の御用材となるヒノキの植林を行う区域で、広さは約3000ha。第2宮域林と呼ばれている。
神職により榊と御塩で祓いを受けた後、大宮司をはじめ、神宮職員や神宮崇敬会の職員などが、手分けして約600本の苗木を植えていく。
令和7年(2025)11月18日、この第2宮域林で、新たなヒノキの苗木、約600本を植える植樹祭が行われた。
200年後の御用材となるヒノキの苗木を植える植樹祭
五十鈴川を遡るように、神路山の頂へ向かって約20分。車は途中で左に折れ、未舗装の林道を進んでいく。両脇にはうっそうと茂る宮域林。ヒノキだけでなく、クスノキやサカキなど広葉樹の木々も混在している。
昭和25年に始まり、今年で第76回を迎える植樹祭は、神宮の長い歴史から見れば新しいおまつり。毎年春に行われているものの、令和7年(2025)は式年遷宮に関するおまつりのスケジュールの関係で、秋に変更になったという。
そもそも、ヒノキの植樹をはじめとする宮域林の育成と保全、管理が始まったのは、大正12年(1923)のこと。当時、200年後の御用材となるヒノキを確保するために、神宮森林経営計画が策定されたのである。
植樹祭の様子。大宮司、少宮司が参列。山の神に向かって祝詞が奏上された。筵にくるまれているのは、植樹するヒノキの苗木。
植樹した苗木に手を合わせる職員。
“神宮の森”が時代と共に変化すること、そして変わらないこと
神宮では、20年ごとに行われる式年遷宮のたびに、内宮と外宮の御正殿をはじめ、65棟の殿社が新たに造営されている。
1回の遷宮に必要なヒノキは、1万本以上。主に、人の胸の高さで直径5、60㎝の木が用いられ、なかには御正殿の棟持柱(むなもちばしら)や御扉(みとびら)のように、直径1mを超える巨木も必要となる。
もっとも、式年遷宮が始まった1,300年ほど前から鎌倉時代までは、現在の宮域林である神路山や島路山(しまじやま)など、神宮周辺の森から御用材を伐り出すことができていた。
だが、次第に適材が得られなくなり、さまざまな変遷を経て、江戸時代以降は、木曽の山々をも御杣山(みそまやま=御用材を伐り出す清らかな山)にして伐り出されることになり、現在に至るという。
樹齢約100年のヒノキ。植樹して3,40年経つと、根の張り具合や枝ぶり、太さなど、木の優劣がはっきりしてくるという。特に優良な木は2本線でマークして目印とし、周囲の木を間伐して大切に育てる。
江戸時代は、お伊勢参りの空前のブームで、神宮周辺の木々の伐採が進んだ時期でもある。膨大な数の参詣者を迎えるには、大量の薪や炭材が必要だったのだ。その影響で、明治時代や大正時代は、五十鈴川の氾濫や山崩れが繰り返し起きるようになったという。
大正12年(1923)に、神宮森林経営計画が策定された背景には、式年遷宮の御用材となるヒノキを植え、育てるのはもちろん、木々がなくなって保水力を失った森を健全な状態に戻し、五十鈴川の水源を涵養(かんよう=自然に水がしみこんで、きれいな水を少しずつ養い育てること)する必要に迫られていたからでもあったのだ。
人が手を入れ、管理することで健全な森が生まれ、良好なヒノキが育つ
今回植樹祭が行われた場所は、内宮のほぼ真南に当たり、広さは0,2ha。実は、平成21年(2009)にも同じ場所に苗木を植えたそうだが、その後台風の被害や鹿の食害に遭ったことから、今回改めて植樹されることになったという。
外宮の神域内にある巨木。自ずと敬虔な気持ちになる。
宮域林をはじめとする神宮の自然は、放任された手つかずのものではない。特に針葉樹であるヒノキは、植樹した後も20年間下草を刈って枝を払い、絡みつく蔓を切って間伐を行わないと、御用材に適したまっすぐな大木に育たず、森もジャングルと化して荒れた状態になるという。
では、効率だけを追求し、ヒノキだけを育てればよいかというと、そういうものでもないらしい。
ヒノキの枝を払い、優良な木だけを残して間伐すると、地面に陽が当たって多種多様な植物が発芽する。広葉樹の木々も自然に芽吹き、やがて、森の上層部にはすっくと伸びたヒノキ、中間層や下層部には、さまざまな葉を茂らせた広葉樹の若木という混交林になる。
つまり、空間に対して樹木の占める割合が高くなり、その分、土に還り、肥料となる枝葉の量が増えることから、土がスポンジのようにふかふかになるのだ。
加えて、木々や草花に花が咲き、実が生れば、それを求めて動物や鳥が集まり、その排泄物をミミズや微生物が分解して、土の肥料濃度が上がる。つまり、肥沃な土壌になることから、ヒノキだけを植えるより、強く良好な木に育つという。
大宮司自ら鍬を振るい、苗木を植える。
森は天然の貯水池である。
長期的な計画によって持続可能な森をいかにつくるか
肥沃な土壌は、森を育て、良質な水を生む。
健全な森に降る雨は、そのまま流れず、1度地下に潜って長い年月をかけ、地中深くにしみこんでいく。やがて、その水は、肥沃な土壌に濾過されてミネラル分を多く含んだ滴(しずく)となって谷に漏れ出す。そして、沢になり、五十鈴川となって下流へ流れ、神々へのお供え物となるお米や野菜、さらに御塩(みしお)を作るための水として使われるのだ。
すべては、森本来の生態系や多様性があってこそ。
天照大御神の御鎮座以降、約2000年という長い歴史の中で、さまざまな局面をくぐり抜けてきた神宮の森は、今、自然を守り保つことと、式年遷宮の御用材であるヒノキを育て、活用すること、この双方のバランスを取りながら、持続可能な森となるよう、長期的な取り組みが進められているのである。
倒木し、苔むした大木を養分にして芽吹いた苗。森ではさまざまな生命が循環している。前回の式年遷宮で用いられた御用材も、解体後は削り直し、再度組み立てられて全国の神宮とゆかりある神社や被災した神社の社殿として用いられるという。
そもそもなぜ、ヒノキなのか
『日本書紀』に記された神話と日本人の自然観
だが、そもそも数ある木の種類のなかで、なぜ神宮の御正殿や別宮以下の社殿には、ヒノキが用いられるのだろう。
たしかに、ヒノキは腐りにくく、香りも長く続いて虫を寄せつけない強靭な性質があるという。現に、7世紀に創建された、奈良・法隆寺の五重塔にもヒノキが用いられ、日本最古の木造建築として、今もその威容が保たれている。
だが、神社仏閣にヒノキを用いる理由は、木の性質だけではないようだ。
日本の古典神話、『日本書紀』によれば、日本の木々はスサノオノミコトと関わりがあるとされている。
つまり、スサノオノミコトが自分の髭を抜き、周囲に散らすとスギの木になり、同様に、胸毛はヒノキ、尻の毛はマキになり、眉毛はクスノキになったと書かれている。木はスサノオノミコトの分身、と読み取ることもできるだろう。
さらに、スサノオノミコトは、それぞれの木の用途についても明言している。たとえば、スギとクスノキは船の材に、ヒノキは立派な御殿を造る材木とし、マキは死者を葬る棺の材にせよ、と。
外宮の御敷地に立つ巨木。
思えば古来、日本では、ヒノキに限らず、巨木や巨岩は神の依り代となる御神木、または磐座(いわくら)として神聖視されてきた。
そして、そんな御神木や磐座を有する山や森も、また当然神聖視され、平地部でも山の神をお祀りするなど、鎮守の杜として守り継がれてきた。
式年遷宮に際しても、御用材となるヒノキを伐り出すときは、そのたび山口祭や御杣始祭(みそまはじめさい)などのおまつりを行って、山の神に感謝の祈りが捧げられる。
その根底には、すべてのものに神が宿るという日本古来の自然観が存在するのだろう。
特に神宮の主祭神である天照大御神は、神々の世界である高天原を統括する神。その御神体をお祀りし、お守りする聖域に、神宿る木、それもスサノオノミコトが「立派な御殿を造る材に」と定めたヒノキを用いることは、ある意味自然なことだっただろう。
加えて、御用材は1度使われて終わりではない。解体後は削り直され、たとえば御正殿の棟持柱は、次の20年間は宇治橋の鳥居に(外宮は宇治橋の外側、内宮は宇治橋の内側)、さらに20年後は、同じ柱が今度は桑名市の七里浜の渡跡の鳥居(外宮)や亀山市の関の追分の鳥居(内宮)に用いられ、その後は地元の神社などに下賜(かし)されるという。
他の御用材も、殿社の解体後に削り直され、再度組み立てられて、全国の伊勢の神宮ゆかりの神社や被災した神社の社殿として、その役割を全うする。
かつて明治時代の文明開化の頃に、御正殿の建材をコンクリートやレンガにしてはどうかという提案がなされたと聞くが、日本古来の自然観や信仰のあり方からすれば、その発想は本末転倒であるように、個人的に思う。
森の循環が、持続可能な永遠の森を造っていく。
話題を植樹祭に戻そう。
今回の祭場は、山の斜面に設けられていた。植樹する前に、まず祭主が山の神に向かって祝詞を奏上。感謝を捧げ、苗木が無事育つよう祈られた。
今回植樹されたヒノキの苗木は、宮域林のヒノキから採取した種を発芽させ、育てたもの。この3年生の苗木が直径約60㎝になる200年後には、遷宮に必要な御用材の90%を超えるヒノキが、この宮域林でまかなえることになるという。
植樹されたヒノキの苗木。神宮宮域林のヒノキから種を採取し、育てたもの。3年生で40㎝ほどの高さがある。
神宮宮域林での取り組みが始まって、ほぼ100年。
周囲を見渡すと、当時植樹されたのだろう。樹齢100年ほどのヒノキが数多く育ち、なかには1重、2重の線でマークされた木もあった。これは、優秀な木を後世に伝えるための目印。
前回の平成25年(2013)の式年遷宮では、御用材の実に23%を宮域林で調達できたという。
木を植え、育てながら森を見守り、活用してまた植える。その循環を続けることが、永遠の「常若(とこわか)の森」へとつながっていくのだろう。
Text by Misa Horiuchi
伊勢神宮
皇大神宮(内宮)
三重県伊勢市宇治館町1
豊受大神宮(外宮)
三重県伊勢市豊川町279
文・堀内みさ
文筆家
クラシック音楽の取材でヨーロッパに行った際、日本についていろいろ質問され、<wbr />ほとんど答えられなかった体験が発端となり、日本の音楽、文化、祈りの姿などの取材を開始。<wbr />今年で16年目に突入。著書に『おとなの奈良 心を澄ます旅』『おとなの奈良 絶景を旅する』(ともに淡交社)『カムイの世界』(新潮社)など。
写真・堀内昭彦
写真家
現在、神宮を中心に日本の祈りをテーマに撮影。写真集「アイヌの祈り」(求龍堂)「ブラームス音楽の森へ」(世界文化社)等がある。バッハとエバンス、そして聖なる山をこよなく愛する写真家でもある。
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Experiences
Premium Calendar
永遠の聖地、伊勢神宮を巡る
Premium Calendar
関連記事
投稿 伊勢神宮 日本人の心が宿る「神宮の森」が意味すること は Premium Japan に最初に表示されました。
Features
光と静けさが満ちる、箱根のプライベートステイ
2025.12.5
強羅花壇の新客室「別邸 東雲」
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
箱根の名宿・強羅花壇に2025年8月に誕生した客室「別邸 東雲(しののめ)」。約250㎡という広さに、ライブキッチン、プライベートサウナ、展望石風呂、和室を備えた、強羅花壇を代表する寛ぎの空間は、特別な“余白の時間”を求める人に最適な空間だ。
名前の由来でもある「東雲」は、夜明け前の淡い光が空に溶け始める瞬間を指す言葉。目の前に広がる枯山水の庭と、その奥に連なる箱根の稜線が重なる光景は、忙しい日常で強張った心をそっとほどいてくれる。特に空が明るみはじめる東雲の時刻には、やわらかな朝焼けが庭全体を包み込み、自然の美と時間の移ろいを全身で感じることができる。
シェフズキッチン
展望石風呂
強羅花壇のこだわりを凝縮した空間には、専属料理人が目の前で懐石料理を仕立てるシェフズキッチン、外気浴スペースを完備した完全プライベートなサウナ、さらに大文字山と石庭を望む源泉かけ流しの展望石風呂も。また、8畳の和室は日本人の琴線に触れる心安らぐ空間。一服の茶を味わう余白の時間が、心を静め精神を整えるひとときをもたらしてくれる。
プライベートサウナ
和室
閑院宮家ゆかりの別邸を起源にもち、ルレ・エ・シャトー加盟、ミシュランキー最高位の獲得など、国内外で高く評価され続ける強羅花壇。その哲学が最も純度高く表現された「別邸 東雲」は、日々の忙しさから離れて心身を整えたいとき訪れたい、箱根の隠れ家だ。
◆箱根・強羅花壇「別邸 東雲」
【客室面積】254㎡
【定員】最大6名
【寝具構成】ツインベッド+布団
【設え】シェフズキッチン、プライベートサウナ、和室、展望石風呂、ダイニング
【泉質】弱アルカリ性単純温泉
【眺望大文字焼きを借景とした枯山水庭園
関連リンク
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>
-
<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>
Features
2025.12.4
「五島リトリート ray by 温故知新」が贈る聖夜のリトリートステイ
関連記事
投稿 強羅花壇の新客室「別邸 東雲」 は Premium Japan に最初に表示されました。