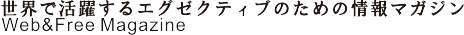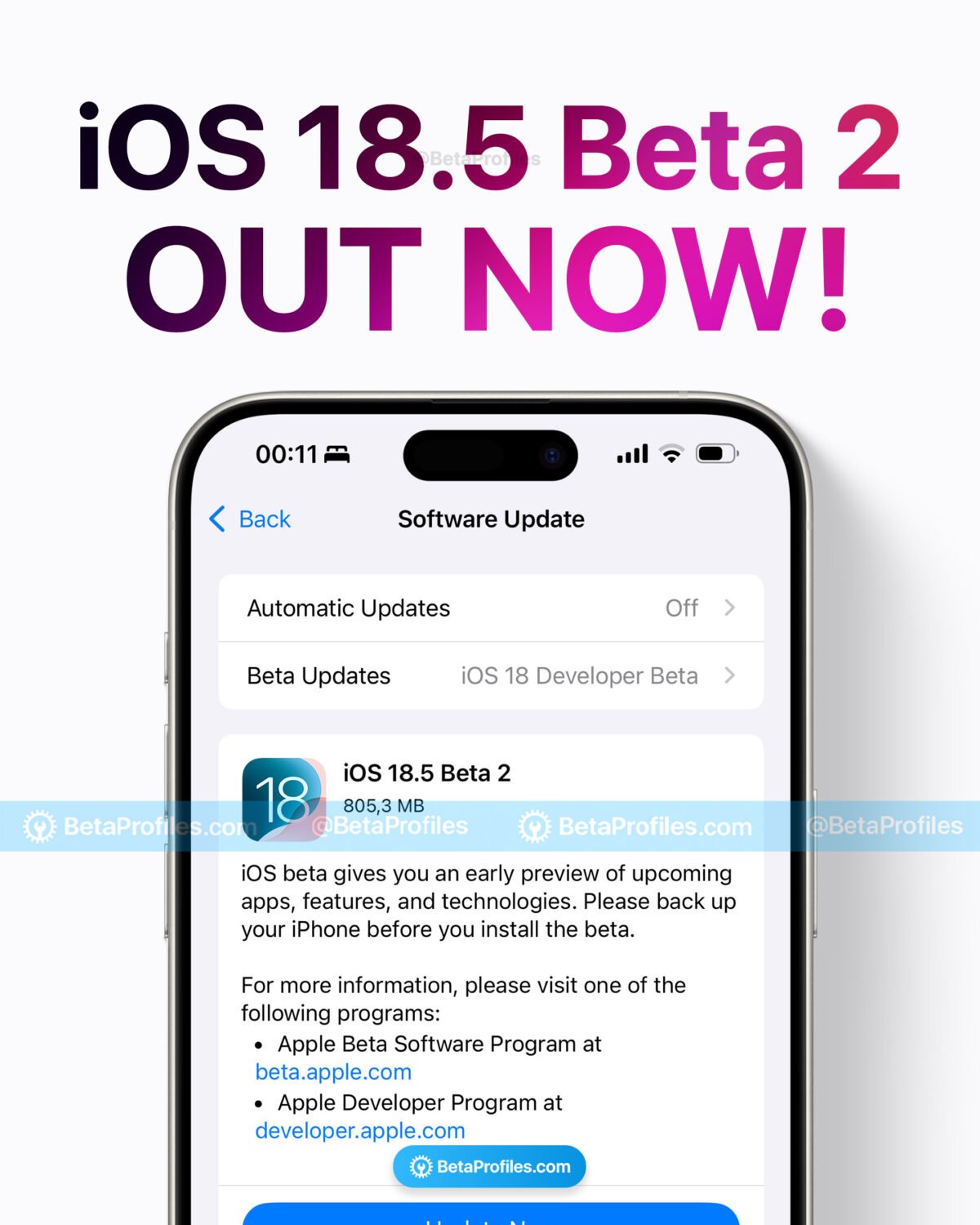人気記事
About&Contact
PREMIUM JAPAN » アート
「明治ザ・チョコレート」とメイジ・デモンストレーション・ファームで収穫したカカオの実
メイジ・デモンストレーション・ファームのあるベトナムを視察させてもらうことになった。嬉しいことにカカオの植樹からチョコレートになるまでをすべて体験できるという。期待に胸を⼤きく膨らませて旅⽴った。
カカオ農園への旅については拙著『ショコラが⼤好き!』でも書いているが、あの事前のアポなしの極めてワイルドな旅とは違い、今回はカカオやチョコレートのスペシャリストで「チョコレート博⼠」こと明治の⼤阪⼯場⻑で農学博⼠の古⾕野哲夫さんの解説付きである。ちなみに連載《第四回》で紹介した古⾕野さんのお話はこの旅中に訊いたことだ。
カカオ農園に到着すると「メイジ・デモンストレーション・ファームにようこそ!」と⾚字で書かれた横断幕が掲げられ歓迎ムード。ここで明治は「メイジ・カカオ・サポート」として技術指導や肥料の無償配布などの⽀援活動を⾏なっているという。
左:カカオの木は周りに植えられた大きな木の陰で、直射日光や強風から守られ育つ。
右:収穫体験。カカオの実一個採るだけでも慣れないとかなり大変な作業。
カカオ農園に⾜を踏み⼊れるとカカオの葉がたくさん落ちていて地⾯がフカフカしていた。カカオが落葉樹であることがよくわかる。農園には、7〜8種類のカカオの⽊が800本あり、コーヒー、コショウ、アボカド、ドラゴンフルーツ、パイナップルといった作物が⼀緒に育てられている。ところどころにカカオ⾖を取った後の実の殻が集められていて半ば堆肥化していた。古⾕野さんによれば、アグロフォレストリーという農法なのだそうだ。
アグロフォレストリーとはアグリカルチャー(農業)とフォレストリー(森林学)をあわせた造語。森林伐採などで荒廃した⼟地に、多種多様な農産物を混合して栽培する農法のことで、事業として成り⽴つうえに、⼗年ほどで森の⽣態系を蘇らせることから「森をつくる農業」と呼ばれ世界的に注⽬されているのだという。
この農法を⽣みだしたのは、ブラジル北東部のトメアスーに⼊植した⽇本⼈移⺠たち。主作物と想定していたカカオの栽培がうまくいかず、アマゾンの過酷な環境の中でジャングルを切り開き、コショウ栽培を始めるなど、紆余曲折を経てたどり着いた農法だった。その壮絶なストーリーは涙なくしては訊けない。古⾕野さんはブラジルでカカオ⾖のリサーチをしているときにトメアスーの⽇系⼈が設⽴した「トメアスー総合農業協同組合(CAMTA)」と出逢い、2009年に明治との共同プロジェクトが始まることになった。今では明治ザ・チョコレートの、エレガントビター、サニーミルク、フランボワーズで使⽤している他、業務⽤のチョコレート「グリーンカカオ」として販売している。「グリーンカカオ」はドライフルーツのような味わいがあって、そのまま⾷べても楽しめるうえ、トメアスーのカカオ農家を応援することにもなるので一消費者としては⼩売も希望したいところだ。
「明治ザ・チョコレート」は日本が世界に誇れる上質な味わいとデザインを目指している。
明治のスペシャリティチョコレート担当の佐藤政宏さん(下、集合写真右)によると、明治のチョコレートは、スタンダード、健康志向、スペシャリティという3つのカテゴリーに分けられている。スペシャリティチョコレートは、選び抜いたプレミアム・カカオを使⽤し、カカオの特徴を際⽴たせた⽇本が世界に誇れる上質な味わいのもので、明治ザ・チョコレートはこのカテゴリーを牽引していく存在だという。
⾃分たちが求める理想のカカオ⾖を安定的に供給してもらうことについては、連載《第四回》で紹介したようにブラジルやベネズエラを始めとする国々のカカオ農家⽀援活動「メイジ・カカオ・サポート」を通じて構築したシステムがそれを可能にしているのだった。
植樹体験。アグロフォレストリーについて話を訊いた後だったので、この農法を生みだしたブラジルの日本人移民に敬意を表して、植樹にはコショウの根が残る場所を希望した。
農園では、ポットで発芽させたカカオの苗を植えて育て、実がつくと収穫して、実からカカオ⾖を取り出して発酵させ天⽇⼲しをする。数年かかる⼯程を数時間で体験させてもらった。実から取り出したばかりのカカオ⾖にはまわりにみずみずしい果⾁がついている。ベトナムのカカオは糖分が⾼く酸味の強いカカオ⾖になりやすいため、果肉がついたままの⾖を絞って⽔分量を減らしてから発酵させる。この時にできるフレッシュな絞り汁(カカオパルプジュース)はたまらなく美味しい。小さなコップに⼊れられた果汁を恍惚として飲み⼲した。
写真:発酵体験。上は実から取り出したばかりのカカオ豆。下は発酵して数日が経ったカカオ豆。
絞った⾖は発酵箱に⼊れて発酵させる。発酵中の⾖の中に⼿を⼊れると、ヌルヌルしていて予想外にかなり熱いがなんだか⼼地よい。⽩い果⾁は数⽇経つとチョコレート⾊に変わり温度も摂⽒50度程になるという。⾖の中に⼊れた⼿は取り出した後もしばらくしっとりとしていた。発酵を終えたカカオ⾖は、⼿作業で外に運び天⽇⼲しをする。
チョコレートに情熱を注ぐ明治の皆さんとベトナムのカカオ農園にて。「チョコレート博士」こと古谷野哲夫さん(中央、ブルーのキャップ帽)を囲んで。カカオの実がたわわに生ったカカオ農園では、その場でココナッツの実をカットして振る舞ってくれた。右端はカカオ農園のオーナー。
こうして乾燥したカカオ豆はチョコレート工場に運ばれて、ローストして砕き皮を取り除いてから、砂糖などを加え磨り潰してチョコレートにする。
明治のカカオクリエイター佐久間悠介さん(上、集合写真左端)が額に汗して準備万端に整えてくれていたおかげで、自分だけの板チョコレートを完成させることができた。
明治のカカオクリエーター佐久間悠介さんの指導で、ベトナムのチョコレート工場で作った farm to bar チョコレート。実際に自分で手がけたのは型に流しただけだけれど出来上がると感激だ。プロの手(佐久間さん)によるテンパリングを経ているので仕上がりはきわめて美しい。
今後は⼀般募集の旅として企画する可能性もあるのだとか。ブラジルの⽇系移⺠が⽣みだしたアグロフォレストリーや、カカオ農家支援活動「メイジ・カカオ・サポート」を通してプレミアム・カカオを安定供給してもらうシステムなど、チョコレートへの情熱と志の⾼さが⽣み出すジャパン・クオリティの魅⼒に触れた旅だった。これから参加する⼈は、知識が豊富になるのはもちろんのことチョコレートへの愛がますます深くなることだろう。
<u>明治ザ・チョコレート その1 ホワイトカカオの記事 >></u>
text © Mika Ogura 2018
【プロフィール】
小椋三嘉(おぐら・みか)
エッセイスト、食文化研究家。
十数年のパリ暮らしを経て帰国。2008 年にはフランス観光開発機構・ パリ観光会議局の名誉ある「プレス功労賞」を受賞。フランスのチョコレート愛好会「クラブ・デ・クロクール・ド・ショコラ」の会員。著書は『高級ショコラのすべて』、『チョコレートのソムリエになる』、『ショコラが大好き!』、『アラン・デュカス進化するシェフの饗宴』、『パリを歩いて―ミカのパリ案内―』など多数。
【商品情報】
明治ザ・チョコレート
写真下段左から:
⼒強い深み コンフォートビター (カカオ 70%)
華やかな果実味 エレガントビター (カカオ 70%)
濃密な深みと旨味 ベルベットミルク (カカオ 51%)
優しく⾹る サニーミルク (カカオ 54%)
写真上段左から:
深遠なる旨味 抹茶 (カカオ 58%)
鮮烈な⾹り フランボワーズ (カカオ 44%)
可憐に⾹る ブリリアントミルク (カカオ 55%)
軽やかな熟成感 ビビッドミルク (カカオ 54%)
各3枚⼊り
東京造形大学がJR東日本・山手線の車両を舞台に、グラフィック作品・映像作品等の展示を行う「山手線グラフィック展」が開催されます。テーマは”TOKYO”。
今、世界中から注目を集めるTOKYOはデザイン先進都市であり、建築、広告、商品、食など、多様な文化を育んできました。私たちも改めてTOKYOを見つめ直し、省みる良いタイミングです。TOKYOを行き交う人々に、見たことや感じたことのないTOKYOに触れ、TOKYOの魅力を再発見してほしい。そんな気持ちから、グラフィックデザインを学ぶ東京造形大学の学生による作品が山手線車内に展示されます。
山手線車内というユニークな開催場所については、デザインは本来、美術館やギャラリーのように限られた空間だけで観賞されるべきものではない、という同校の考えに基づくものです。デザインは社会を形成する大切な要素であり、また、人々の日常に溶け込んでこそ真価を発揮するものという考えのもと、作品展が東京の中心を周回するJR山手線で実施されることになりました。
学生たちの瑞々しい感性・個性が光る作品が山手線を彩る「山手線グラフィック展」は2018年2月28日までの開催です。
東京造形大学 山手線グラフィック展
会期:2018年2月17日(土)~2018年2月28日(水)
*車両整備等の理由で、期間中でも運休となる場合がございます。
実施車両:山手線E231系 ADトレイン 1編成
http://www.zokei.ac.jp/news/2018/7994/
「松風」モネ劇場公演より Photo:Bernd Uhlig
日本の伝統芸能、「能」。そしてルネサンス後期が発祥とされる「オペラ」。それぞれに伝統と格式を持つ舞台芸術がひとつに。能の古典演目として知られる『松風』が1幕5場のオペラに仕立てられた注目の公演・オペラ『松風』が日本で初めて上演されます。
手がけたのはドイツを拠点に世界的に活躍する作曲家・細川俊夫氏。細川氏は欧米の主要なオーケストラや音楽祭、劇場からの委嘱作品が次々と上映される現代音楽をリードする作曲家です。報われなかった愛のため亡霊となった女が狂おしく舞うという筋立ての能『松風』の幽玄の世界が、細川氏の手によって”魂の浄化“という普遍的なテーマを持つオペラ作品として昇華したオペラ『松風』は、ベルギー王立モネ劇場、ルクセンブルク大劇場、ポーランド国立歌劇場との共同制作、ベルリン州立歌劇場の協力により2011年に初演され、以来フランス、香港と上演を拡大に、大きな反響を呼んだ傑作です。
「松風」モネ劇場公演より Photo:Bernd Uhlig
細川俊夫氏と手を組んだのはドイツ・ダンス界を代表する世界有数の振付家のサシャ・ヴァルツ氏。音楽と舞踊、声楽が一体となったコレオグラフィック・オペラという様式を確立した同氏による斬新な演出と自然と幽玄を描いた細川氏の音楽が見事に交錯したオペラ『松風』は「80分があまりに早く過ぎてしまった」(フィナンシャルタイムズ)との賛辞をも得ました。
また、このオペラ『松風』の大きな見どころのひとつがドイツを拠点に世界的に活躍する現代美術家・塩田千春氏のインスタレーションによる舞台演出です。劇場という巨大な空間に黒い毛糸を張り巡らせ、死者と生者を自在に行き来させる効果的な舞台演出を制作しました。音楽、舞踊、美術が一体となって現出したオペラ『松風』はまさに総合芸術として、全てのアートファンを魅了することでしょう。
「松風」モネ劇場公演より Photo:Bernd Uhlig
細川俊夫とサシャ・ヴァルツが創り上げる、壮大なスケールのアートプロダクション・オペラ『松風』は2月16日〜18日の3日間の上演です。全世界で喝采を浴びてきた話題作をお見逃しなく。
新国立劇場開場20周年記念公演 新国立劇場2017/2018シーズンオペラ
細川俊夫/サシャ・ヴァルツ 松風
公演日程:2018年2月16日(金)19:00、17日(土)15:00、18日(日)15:00
会場:新国立劇場 オペラパレス
チケット料金:S:16,200円 A:12,960円 B:8,640円 C:6,480円 D:3,240円 Z:1,620円
http://www.nntt.jac.go.jp/opera/
明治維新から150年となる2018年、佐賀県武雄市の陽光美術館にて、「~明治維新150年~生誕150年 横山大観展」が開催されます。明治維新150年は、横山大観生誕150年でもあります。大観を含め近代日本画の大家は、明治維新、また維新後間もなく産まれ、急速に近代化する激動の時代と共に育ったと言えます。今回の展示はこうした激動の時代にこそ生まれる”新しい価値観” を一つのテーマにしています。そしてもう一つのテーマは変わりゆく中で、”変わらないもの”。そこに、近代日本画の巨匠たちが愛される理由があるのかもしれません。
また、中国陶磁も同時に展示いたします。宋時代から清時代までの約1,000年を、異なるジャンルでありつつも明治維新と同じように、 変革、激動をキーワードに眺めてみようという試みの展覧会です。
陽光美術館所蔵の横山大観を中心とした日本画が初公開される、「~明治維新150年~生誕150年 横山大観展」では、横山大観の他、木村武山、橋本関雪の作品なども展示されます。中国陶磁からは「桃花紅観音瓶」「飛青磁」等が展示。近代日本画と中国陶磁、それぞれに維新・変革・激動の時代に何が生まれたのかを知ることができるテーマ展です。
~明治維新150年~生誕150年 横山大観展
会場/公益財団法人 陽光美術館
佐賀県武雄市武雄町武雄4075‐3
期間/2018年1月1日(月) ~ 5月31日(木)
時間/9:00~17:00
入館料/一般600円、高大生500円
休館日/水曜日 ※4月・5月は無休
http://www.yokomuseum.jp/
ミュージアム・ロードからのメインアプローチ ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
弘前市に残る、吉野町煉瓦倉庫が2020年度春に向けてリニューアルし、「弘前市芸術文化施設」(仮称)として開館します。
吉野町煉瓦倉庫がある土地は、明治時代、青森のリンゴ栽培の開拓期において本格的な栽培がおこなわれた場所のひとつです。1907年に酒造工場として建造した煉瓦倉庫は、戦後はリンゴを原料としたシードルを日本で初めて生産しました。その後、倉庫となり、110年の歳月を経て、今もなお立ち続けています。2002年から2006年の間、弘前市出身の芸術家・奈良美智氏が数回展示会を開催するなど、市内外において知名度が高い建物であり、吉野町緑地とともに中央弘前駅、最勝院五重塔、そして岩木山を望むことができる、市の景観づくりやまちづくりにおいても重要なポイントとなる場所です。
近代文化遺産が壊され、世代から世代へと受け継がれた土地の記憶を失い続けているように見受けられる近年の日本。そんな中、煉瓦倉庫が「世界のアート」が体験できる美術館として生まれ変わります。改修を担うのは、建築家の田根剛氏が主宰するATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS。「きわめて先進的な内外のアートの紹介の場」、「現代の科学技術やデザインの発展を若い人々とシェアすることができるクリエイティブハブ」、「地域の住民がアートやデザインを学び、集うコミュニティのための場」、そして「所蔵品、レジデンス事業、企画展という3つの機能をつなぐ基盤」の4つを理念として掲げ、アートの感動を弘前にもたらし、人々が創造性の喜びへと向かう一連の流れをつくり出すことを目的に活動が始まります。「つくること、みせること、そしてそれを収蔵して歴史に残すこと」、という他に例のない一連の流れが、驚きと感動に満ちた体験の場をつくり出します。
西立案図 ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
新しい風景をつくるシードル.・ゴールドの屋根 ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
老朽化した屋根は光によって移ろう「シードル・ゴールド」の屋根葺に、経年によって傷んだ外壁は全て「赤煉瓦」で覆われます。A棟は市民に開かれた文化施設として様々な活動が行われ、B棟は倉庫の持つ空間性を活かした大型展示空間となります。またC棟は「シードル・カフェ」として再生することでアートと市民を繋ぐ吉野町緑地の中心の場所を担います。そして、「ミュージアム・ロード」はアートと市民を繋ぐパブリック・スペースとなります。
高さ15mの大型展示空間 ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
既存の空間を活かしたアートの展示空間 ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
市民文化交流が出来るライブラリー ©ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
弘前市がアート界における世界と日本の架け橋となる日も近いかもしれません。現代アートのクリエイティブハブとして新しく生まれ変わる煉瓦倉庫、必見です。
≪建築家プロフィール≫
田根 剛
1979年東京生まれ。ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTSを設立、フランス・パリを拠点に活動。2006年にエストニア国立博物館の国際設計競技に優勝し、10年の歳月をかけて2016年秋に開館。また2012年の新国立競技場基本構想国際デザイン競技では『古墳スタジアム』がファイナリストに選ばれるなど国際的な注目を集める。場所の記憶から建築をつくる「Archaeology of the Future」をコンセプトに、現在ヨーロッパと日本を中心に世界各地で多数のプロジェクトが進行中。主な作品に『エストニア国立博物館』(2016年)、『A House for Oiso』(2015年)、『とらやパリ』(2015年)、『LIGHT is TIME 』(2014年)など。フランス文化庁新進建築家賞、フランス国外建築賞グランプリ、ミース・ファン・デル・ローエ欧州賞2017ノミネート、第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞など多数受賞 。2012年よりコロンビア大学GSAPPで教鞭をとる。
ATELIER TSUYOSHI TANE ARCHITECTS
世界各地でキャリアを積んだ多国籍のメンバー約30名で構成する国際色豊かなチームがヨーロッ パと日本を中心に世界中で多数のプロジェクトに従事している。建築の他にもインスタレーションや舞台や展覧会の空間演出を手がけるなど、分野を超えた活動が国際的な注目を集めている。
国内はもちろんのこと、海外からも高い人気を誇る観光都市、京都。その中心である京都駅の中に美術館があることをご存知でしょうか。その名も『美術館「えき」KYOTO』は京都駅ビル内に位置する百貨店「ジェイアール京都伊勢丹」の7階に隣接し、絵画、写真、絵本、工芸、アニメ、ファッションなど、国内外を問わず幅広いジャンルで展覧会を企画しています。
その美術館「えき」KYOTOにて2018年1月2日~21日に開催されるのが「京都市美術館所蔵品展 描かれた“きもの美人”」 です。
京都市美術館は1933(昭和8)年に設立された公立美術館で、開館以来、近現代美術作品の鑑賞と発表のための西日本最大の舞台のひとつとして、戦後日本文化のなかで大きな役割を果たしてきました。同館所蔵のコレクションは多岐にわたり、近現代の日本画・洋画・彫刻・工芸・書・版画など約3,400点を所蔵しています。なかでも京都画壇で活躍した美術家たちの作品群は、他に類を見ない豊かさを誇っています。
2019年度内にリニューアルオープンを予定して、現在本館が閉館中である京都市美術館。その所蔵の数ある珠玉の作品の中から日本画を中心に、美しく艶やかに描かれた“きもの美人”約40点が会期中紹介されます。上村松園《人生の花》、菊池契月《散策》、堂本印象《婦女》、秋野不矩《紅裳》など、近代の画家たちが描いたさまざまな女性像が一堂に展覧されます。
期間中、京都市美術館 館長である潮江宏三氏や、服飾評論家の市田ひろみ氏などが会場内を移動しながら解説するギャラリートークも開催されます。また、着物でご入館の方先着100名さまには便利堂オリジナル絵はがきのプレゼントも。
2018年は“きもの美人観賞”から晴れやかな気持ちで初めてみませんか。
京都市美術館所蔵品展 描かれた“きもの美人”
会場:美術館「えき」KYOTO
〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹7階隣接
午前10時~午後8時(入館締切:閉館30分前)
期間:2018年1月2日(火)~21日(日)
http://kyoto.wjr-isetan.co.jp/museumu/
現在、日本で最も注目されるテキスタイルデザイナー鈴木 マサル氏の九州初となる個展が開催されます。場所は福岡・天神の三菱地所アルティアム、2017年12月9日(土)〜2018年1月14日(日)まで。
鈴木 マサル氏は、自身のブランドOTTAIPNU(オッタイピイヌ)をはじめ、マリメッコやユニクロ、zoffなど国内外のブランドのテキスタイルデザインを手がけています。また、ファッションアイテムやプロダクト、家具へのデザイン提供や空間インスタレーションなど、活動の幅は多岐にわたります。そのデザインの魅力は、見る人を自然と笑顔にするような動物や植物など日常的な温かみのあるモチーフにあります。鈴木氏は「機能面からすれば色や柄などのデザインは、必ずしも重要とは言えない要素。でも、あえてその要素を加えてゆくのは、色や柄には気持ちを高揚させる力があるから。」と語ります。
本展では、“目に見えるもの、すべて色柄”がテーマ。これまで発表してきたテキスタイルや傘、ラグ、ファブリックパネルなど約100点が展示され、鮮やかで、版の重なりから生まれる奥行きのある色彩、ユーモアあふれるモチーフとダイナミックな構図がもたらす空間が出現します。また、会期中には鈴木氏のトークショーやワークショップが開催されるほか、会場に併設するショップ内ではOTTAIPNUのアイテムや書籍が販売されるポップアップショップがオープンします。
本展示会では、会場を色と柄で埋め尽くしたとのこと。
この機会にぜひ、鈴木氏が伝えようとする色がもつ高揚感や魅力を感じてみてはいかがでしょうか。
≪アーティストプロフィール≫
鈴木 マサル(テキスタイルデザイナー)
1968年千葉県生まれ。多摩美術大学染織デザイン科卒業後、粟辻 博デザイン室に勤務。1995年に独立し、2002年有限会社ウンピアットを設立。2004年からファブリックブランドOTTAIPNUを主宰。自身のブランドのほか、2009年よりフィンランドの老舗ファブリックメーカー ラプアンカンクリ、2010年よりマリメッコのデザインを手がける。その他にも、カンペール、ユニクロ、ファミリア、zoffなど国内外のさまざまなメーカー、ブランドのプロジェクトに参画。主な個展として、2012年より「鈴木マサル傘展」(スパイラルガーデンなど/東京)を毎年開催。2014 年からスタートした富山の魅力をテキスタイルデザインで表現した「富山もようプロジェクト」が第35回新聞広告賞を受賞。2016 年4 月にイタリア・ミラノで開催された展覧会「Imagine New Days」(主催 アイシン精機株式会社) に参画、Milano Design Award 2016 “BEST ENGAGEMENT by IED”を受賞。2016 年8 月には初めての書籍『鈴木マサルのテキスタイル』(誠文堂新光社刊)を上梓。 東京造形大学造形学部デザイン学科 教授。
roop / printed textile / OTTAIPNU 2016
MARENCO × Masaru Suzuki / covering textile / arflex japan 2014
umbrella & parasol / OTTAIPNU 2015
http://masarusuzuki.com
http://ottaipnu.com
目に見えるもの、すべて色柄
会場:三菱地所アルティアム(イムズ8F)
福岡市中央区天神1-7-11
日時:2017年12月9日(土)~2018年1月14日(日)
※12月31日(日)、1月1日(祝)は休館日
開場時間:10:00~20:00
入場料:一般400円、学生300円、高校生以下無料再入場可
◆オープニング レセプション
会期初日の夜、本会場にて鈴木氏を囲みレセプションパーティーが開催されます。
日時:2017年12月9日(土) 18:30~20:00
会場:三菱地所アルティアム(イムズ8F) ※参加無料・予約不要
◆トークショー
本展のテーマである色や柄についてなど、デザインジャーナリストの高橋美礼氏を聞き手に、鈴木氏のトークを聞けます。
日時:2017年12月16日(土)
時間:開場 13:45〜、開演 14:00〜 およそ90分
会場:セミナールームA(イムズ 10F)
参加費:500円 ※入場料は別途
定員数:60名(自由席・要予約)
予約TEL:092-733-2050(アルティアム)
※予約開始は12月1日(金)より
◆ワークショップ
OTTAIPNUのテキスタイルを使用して、オリジナル缶バッジを制作できます。
日時:2017年12月17日(日)
受付時間:13:00〜15:00
会場:会議室(イムズ 8F)
講師:鈴木 マサル氏
参加費:1つ 800円 ※限定100個(無くなり次第終了)
※混雑状況によって、整理券を配布する場合あり
◆POP UP SHOP
会場に併設するショップ「アートショップドットジー」にてOTTAIPNUのアイテムが販売されます。
上野恩賜公園と谷中地域を舞台に、アートで日本文化を世界に発信する大型野外アートフェスティバル『TOKYO数寄フェス2017』が11月19日まで開催されます。世界各国から老若男女が集まる上野公園の見慣れた風景が、アーティストによって新たな体験と記憶の場へと変身します。
期間中には巨大な楼閣が上野公園噴水池に建てられるほか、葦舟の進水式、インスタレーションの展示等がされます。
「プラネテス -私が生きたようにそれらも生き、私がいなくなったようにそれらもいなくなった-」 / 大巻 伸嗣
上野公園噴水池に、単管パイプと木材を組み上げた高さ13.5mにも及ぶ巨大な楼閣が出現。かつてこの地に存在した、寛永寺の山門「文殊楼」がモチーフ。蜃気楼のように噴水池の水面に映るその姿は、かつての風景を想起させます。また夜のライトアップでは、幻想的な佇まいを見せます。「空間」「時間」「重力」「記憶」をキーワードに活動する、繊細かつダイナミックな作家による、ここでしか見ることができない作品です。
「上野造船所」不忍池 舟プロジェクト / 日比野 克彦・海部 陽介・石川 仁
不忍池のほとり、弁天堂前広場には、人類学者・海部 陽介氏の「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」の資料などを展示。同時に、探検家の石川 仁氏を中心に日比野 克彦氏デザインの葦舟『TANeFUNe』を会期中制作し、最終日のボート池での進水式を目指します。週末は、だれでも参加可能な舟つくりのワークショップも楽しめます。
「ティーテイスターフォレスト」/ 橋本 和幸 with ITO EN ティーテイスター
噴水前広場に設置された橋本 和幸氏デザインの空間で、日本茶の魅力を楽しんでもらうべく伊藤園の「ティーテイスター」によるお茶の振舞いが行われます。また、作家による移動式住居と茶室も登場。
※お茶の振舞いは11/11、12、18、19の11:00~17:00のみ
「藝大御輿」/ 東京藝術大学
同じく噴水前広場に、9月の東京藝術大学の学園祭にて「上野文化の杜賞」を受賞した藝大生制作の御輿が11月12日まで展示されています。
今後実施予定のイベント
◆「上野造船所」 不忍池 舟プロジェクト / 日比野 克彦 ・ 海部 陽介 ・ 石川 仁
〈ワークショップ~今日の記憶を明後日へ運ぶ舟つくり~〉
葦や上野公園内で集めた落ち葉や枝を素材に、思い思いに自分で舟を作るワークショップ。
日時:11/11(土)、11/12(日)、11/18(土)、11/19(日) 13:00~16:00
場所:弁天堂前広場
申込方法:申込不要
〈『TANeFUNe』進水式〉
会期中に石川氏がワークショップ参加者と共に制作した、日比野デザインの『TANeFUNe』が不忍池に浮かびます。
日時:11/19(日)11:00~12:00
場所:上野公園 ボート場
申込方法:申込不要
◆「ミナモミラー」 / 鈴木 太朗・ 空間演出研究所
不忍池をキャンバスにたとえ、光を不忍池に投影します。風の流れによって時間とともに変化する、水面にたゆたう反射光を楽しむ作品です。不忍池のボート池全周、池に浮遊するオブジェをLEDライトの淡く柔らかい光が囲みます。
日時:11/17(金)~11/19(日) 日没後~20:00
場所:不忍池(ボート池)
申込方法:申込不要
そのほか「こぱんだウインズ」 門前コンサート、藝大生によるミュージアムコンサート等も催されます。詳しくはHPでご確認ください。
芸術の秋、上野に足を運び、普段なかなか体験できないアートの世界に触れてみてはいかがでしょうか。
『TOKYO数寄フェス2017』
期間:11月10日(金)~ 11月19日(日)
実施場所 :上野恩賜公園(不忍池一帯、噴水前広場 ほか)、東京国立博物館、東京都美術館、東京文化会館、谷中地域 ほか
http://sukifes.tokyo/
「キャラヴァン」 ©Rima Fujita 2017
ミクストメディア/紙 32.5x40cm
伊勢丹新宿店のアートギャラリーにて、11月8日(水)~14日(火)の期間、アメリカ在住のアーティストで、ファッショナブルでスピリチュアルな作風が幅広い年齢の女性ファンの心をつかんでいる藤田 理麻(ふじた りま)氏の個展『Home-心の故郷』が開催されます。
藤田氏の絵画はどれも鮮やかで美しく、絵画に登場する人物たちの目は何かを問いかけてくるような、強い眼差しをしているのが印象的です。
最近のニュースを聞きながら「自分の故郷/家」は何で左右されるのだろうかと、ずっと考えていたという藤田氏。
—–自分の「ホーム」とは、住む場所なのか、それとも一緒に住む人なのか。肉体的に住む場所なのか、それとも心の中にあるものなのか。例えば、シリアの難民たちが亡命して、新しい土地に馴染めなくても、そこで生きて行かなくてはならない。その場合、彼らにとっての「ホーム」は、新しい国なのか、それとも心の中でのホームは、やはりシリアなのか。それとも家族と一緒であれば、どこに住もうと、そこが「ホーム」になるのか。
そして、人間だけでなく、動物や他の生き物たちにとってはどうなのか。
「サンクチュアリへ」©Rima Fujita 2017
ミクストメディア/紙 32.5×40cm
「母なる地球」©Rima Fujita 2017
ミクストメディア/紙 32.5×50cm
「木の妖精」©Rima Fujita 2017
ミクストメディア/紙 32.5x40cm
そんな、国際社会が無視できない問題を毎日考え、それをテーマに制作したといいます。
出品は、新作原画約30点に加え、来春にアメリカで出版される絵本の原画も発表され、ポストカードセット、グッズも販売されます。
この機会にぜひ、藤田氏の世界に触れてみてください。
藤田 理麻 新作絵画展『Home-心の故郷』
会期: 11月8日(水)~14日(火) 最終日は午後6時終了
営業時間:午前10時30分~午後8時
会場:伊勢丹新宿店本館5階=アートギャラリー
※会期中毎日作家来店予定
イベント日程:
スライドトーク&サイン会 11月11日(土)午後2時~3時30分
サイン会 11月12日 (日) 午後2時~3時
問い合わせ先: 03-3352-1111
藤田 理麻(ふじた りま)
東京に生まれ、兵庫県芦屋市で育つ。アメリカ在住38年。
ニューヨークとロサンゼルスを拠点に個展活動を続け、世界各地にコレクターを持つ。
2001年に貧しい国々の子供達に絵本を作り贈る機関「Books for Children」を設立、数々の賞を受賞。
https://www.rimafujita.com
11月23(木)~11月29日(水)まで、GINZA SIXのアートギャラリー Artglorieux GALLERY OF TOKYO(アールグロリュー ギャラリーオブトーキョー)にて、「~新版画の美~ 没後60年 川瀬巴水 木版画展」が開催されます。
川瀬巴水(かわせ はすい、明治16年-昭和32年)は、衰退した日本の浮世絵版画を復興すべく、新しい浮世絵版画である「新版画」を確立した人物です。
糸組物職商人の長男として生まれましたが日本画家・鏑木清方(かぶらき きよかた)の門人となり、この時に「巴水」の号を授かりました。同門・伊東深水(いとう しんすい)の<近江八景>を見て木版画に興味を持つと、大正7年に渡邊版画店から塩原三部作を発表。その後も日本各地の旅行先で写生した絵を原画とし数多くの版画作品を刊行し、近代風景版画の第一人者となりました。
日本的な美しい風景を叙情豊かに表現した巴水は「旅情詩人」「旅の版画家」「昭和の広重」などと呼ばれており、海外では葛飾北斎・歌川広重等と並び称される程の人気があります。
今展では、版元である渡邊木版美術画舗協力により、貴重な初期摺作品をはじめ、巴水の魅力溢れる作品の数々が展覧されます。
巴水が描く、古き良き時代の日本の美しい風景画をこの機会にぜひ。
「~新版画の美~ 没後60年 川瀬巴水 木版画展」
会期:11月23(木)~11月29日(水) ※最終日は午後6時閉場
会場:GINZA SIX 5階 Artglorieux
http://artglorieux.jp/